<あらゆる謎が氷解する、超人気エコノミスト渾身の快著!>、<各メディア驚愕の圧倒的わかりやすさ!>、<丸善丸の内本店、丸善日本橋店 新書週間ベストセラー第1位>と帯についており、非常に良い内容だった。
少々、専門用語が難しいが、何故、日本の労働者の賃金が上がらないのかを分かりやすく説明している。
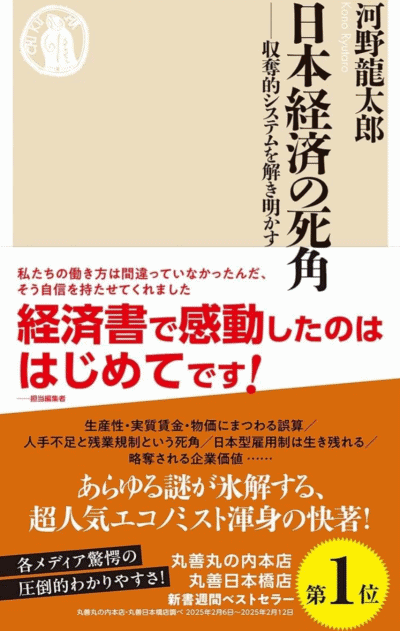
上がらない実質賃金
まず、日本は1998年を100として、生産性は累計で30%上昇しているが、実質賃金は据え置かれたままだという。
一方で、アメリカは1998年末以降、生産性は50%上昇し、実質賃金も30%上昇したという。
欧州でもドイツは生産性が25%上昇し、実質賃金は15%上昇し、フランスは生産性が20%上昇して、実質賃金は20%上昇したという。
ドイツやフランスは、日本よりも生産性の上昇度合いは少ないにも関わらず、それなりに実質賃金も上昇しているが、日本ではよこばいのままで全く据え置かれたままである。
この統計データを見て、著者は、日本は、収奪的な社会に移行したのかと問題提起している。
何故、このように日本では、賃金が上がらないのかについて、著者は以下のように記している。
|
メインバンク制の崩壊と日本版コーポレートガバナンス改革の開始 前置きが長くなりました。本章のテーマは、コーポレート・ガバナンスと雇用制度の関係でした。読者は、第1章で登場した経済学者・青木昌彦氏の言葉を覚えておられるでしょうか。それは「メインバンク制が崩壊すれば、日本型の安定的な企業経営の根幹にある長期雇用制も崩壊する」というものでした。 米国では不況が訪れ、売上が減ると、倒産を避けるためには、人件費の削減を目的に、企業が雇用リストラに踏み切るのは、日常茶飯事です。日本では、不況期も雇用リストラが避けられていたのは、かつてはメインバンクからのサポートがあったからでした。日本の大企業は、株式を互いに持ち合うなど、特定の銀行(メインバンク)と特別な関係を結んでいたのです。 1990年代末の金融危機以降、メインバンク制は文字通り、崩壊しました。しかし、その後も、大企業が不況期に雇用リストラを避けられているのは、長期雇用制を維持するために、自己資本を積み上げるべく、コストカットに邁進したからでした。 人件費を抑えるために、ゼロベアを続け、セーフティネットを持たない非正規雇用に大きく依存するようにもなりました。そのことが、個人消費の低迷の原因ともなり、企業の国内売上の低迷を今も招いていることは、第1章で詳しくお話ししましたが、話はそこでは終わりません。 メインバンク制の崩壊過程で、銀行と企業の株式の持ち合いが解消される際、健全な株式の受け皿を整えるべく、日本政府は、株主の利益に沿った企業経営が行なわれることを目指してコーポレートガバナンス改革を推進しました。時は、1990年代末。グローバル金融市場では、米国流の新自由主義的な株主資本主義時代の真っ盛りでした。 当時、コーポレートガバナンス改革の理論的支柱だったのは、一つは「企業の社会的責任は利益を増やすこと」とするフリードマン・ドクトリンでした。 あの有名な決めゼリフである「インフレは、いつでもどこでも貨幣的現象」と発したマネタリストの総帥であり、1976年にノーベル経済学賞を受賞したミルトン・フリードマンです。 もう一つの理論的支柱は、同じく経済学者のマイケル・ジェンセンのエージェンシー理論でした。 ジェンセンは、企業経営者(エージェント)が株主(プリンシパル)の利益を最大化させるインセンティブ(誘因)を持つためのメカニズムを構築したことで有名です。 (「日本経済の死角 – 収奪的システムを解き明かす – 」P.204~205) |
日本は、戦後の復興期(1945年以降)から高度経済成長期(1950〜1970年代)にかけて、自然発生的に形成されたメインバンク制という企業と銀行の密接な関係があり、会社は資金繰りに苦労すれば、銀行に助けてもらえる盤石な体制だったため、自己資本を積み上げる必要がなかったという。
この体制は、政府(大蔵省)の強い指導・監督の下で、企業を保護、育成する護送船団方式という体制とセットであった。
銀行と会社は株式を持ち合うような体制で、非常に体制的に安定しており、日本の労働者の正社員による長期雇用が維持されていた。
そして、この当時は、アメリカと日本で、労働者の賃金にそれ程の差はなかったという。
1970年代に入ると、戦後に比べて、先進各国で経済成長が滞っていた為、犯人探しが始まったという。
ちょうど1979年にミルトン・フリードマンの『選択の自由』という著作が出されて、政府の介入を排除して、市場に任せるという市場原理主義の理論が世に登場した。
そして、1980年代には、労働組合は、経済効率性の改善に邪魔な存在とされ始め、その力を削ぐような政策が行なわれた。
|
(略) 実際、米英など保守政党が政権を握っていた国では、労働組合は経済効率性の改善に邪魔な存在だとして、1980年代には、陰に陽にその影響力を削ぐ政策が進められました。理由はともあれ、日本でも労組の力を削ぐような政策が中曽根康弘政権の下で進められました。 ミルトン・フリードマンが経済社会全般に強い影響力を持つに至ったのは、1979年のローズ夫人との共著『選択の自由』を通じて、というべきかもしれません。筆者は1983年に大学に入学しましたが、その時、既に日本でも経済学部生の必読書となっていました。 そこでは、①自由市場は最も効率的な経済システムであり、②政府の過剰な介入は、市場の非効率性や腐敗を生み、③個人が自由に選択する権利を保障することが社会の繁栄につながること、が論じられていました。納得のいく論考ですが、同時に、公害などのような「負の外部性」は比較的少さく、政府による規制で対応するより、私的契約での対応や不法行為等で取り締まる方が望ましく、また、市場経済そのものは、概ね平等な所得分配をもたらす傾向があり、社会民主主義的なアプローチよりも望ましい成果をもたらすとも主張されていました。 具体案を提示したのはマイケル・ジェンセン 米国の大企業経営者の、目が飛び出るほどの高額報酬を可能にしたという点では、エージェンシー理論を武器に、企業経営者の報酬を株価に連動させるのが望ましいとした経済学者のマイケル・ジェンセンも再度登場してもらう必要があります。理論の正しさはともあれ、現実にはジェンセンの論考は、経営者が自らの報酬を高めるべく、短期的な株価上昇を狙って、長期的な企業価値の成長やステークホルダーの利益を蔑ろにするための言い訳にされたことは、第6章でもお話ししました。 株式オプションなどを与えられた企業経営者は、株価の上昇で多大なメリットを得られるわけですから、利益を増やすために雇用リストラを断行し、そこで得られた資金を長期投資に充てるのでもなく、配当の支払いに充て、さらに株価を引き上げるための自社株買いの資金に回したことも、既にお話ししました。 そうした行動は経済学的に正しいのだと、アカデミアがお墨付きを与えたのですから、企業経営者は良心の呵責に耐えることも可能だったのでしょう。 このように、フリードマンが企業の社会責任を株主価値の最大化に限定する理論を提供し、ジェンセンがより具体的なインセンティブメカニズムを提案したというわけです。 ■成長の下方屈折とその処方箋 その頃、ミルトン・フリードマンらの新自由主義的な政策が広く受け入れられたのは、先進各国で経済成長が下方屈折したという背景がありました。米国では戦間期から、そして米国を除く先進国では第二次世界大戦後に、成長の第二黄金期が始まったと述べましたが、そこでは、あまりに上手く行き過ぎたことが仇となりました。 というのも、戦間期に実用化された軍事技術が広く民生転換され、新たな財・サービスが多数登場したことや、また、特に欧州や日本では、戦時期に破壊された資本ストックが再蓄積過程に入ったこともあって、第二次世界大戦後は、例外的に高い成長が可能となったからです。 日本では、戦後の高成長を「高度成長期」という名前で呼んでいますが、フランスでは「栄光の30年」と呼ばれています。例外的な30年ではありましたが、30年も続くと、それが当たり前だと、皆考えるようになりました。 振り返れば、それでも1970年代は決して低い成長ではなかったのですが、多くの国では、戦後に比べて冴えない成長の犯人探しが始まり、その犯人とされたのが、雇用保障や適正な賃金、政府の役割を重視する社会民主主義的なアプローチだったということです。 本章第1節でお話したように、歴史を踏まえるなら、労働者が団結し、起業家や資本家に対して対抗する力や手段を持つことで、包括的なイノベーションが生み出されたはずです。 また、それが限界生産性の上昇をもたらして、労働需要を高め、広範囲な人々の実質賃金の上昇を可能とする生産性バンドワゴン効果を作動させるための条件でもありました。 しかし、フリードマンらは、むしろそれらが行き詰まって、高い成長が不可能になったのだと論じ、自らの利益が膨らむと期待した経済エリートは皆、その見解に飛びつきました。 解決策として提示された政策が、むしろ、生産性バンドワゴン効果をストップさせたために、高い成長はますます遠のくことになったわけです。 (「日本経済の死角 – 収奪的システムを解き明かす – 」P.252~255) |
1990年以降になると、この米国の新自由主義的な株主資本主義が、日本の金融市場の改革を要求した。
理論的指導者の一人は、上述したようにミルトン・フリードマン(1976年にノーベル経済学賞を受賞)で、市場原理や小さな政府を主張し、政府は何も規制せず、企業の社会的責任を否定し、規制緩和、民営化などを積極的に主張した。
景気や雇用の安定は、国家の政府支出(財政政策)によってもたらされるのではなく、貨幣供給量(マネーサプライ)のみによって決まる(マネタリズム)と主張した。
ケインズ経済学の政府の財政政策によって、有効需要を創出するという考え方(積極財政)には否定的な考えを示した。
もう一人の指導者が、アメリカの経済学者で、ファイナンス研究者のマイケル・C・ジェンセンで、エージェンシー理論(株主至上主義)により、企業経営者と株主の利害対立を分析し、「株主価値最大化」を企業の目的とすべきと主張した。(この理論により、後に自社株買いが解禁され、企業の経営者は、利益を会社の長期的な発展の為に設備投資や研究開発に回さずに短期的な利益の最大化と、株主への配当に回すことになった)
こうした理論的指導者による経済政策をアメリカの年次改革要望書などで、日本政府が押し付けられて、金融市場の改革を行なった結果、日本のメインバンク制が崩壊し、長期雇用が難しくなり、企業が内部留保などによって、自己資金を積み上げるようになった。
銀行はこれまでのように困った時に金を貸してくれず、貸しはがしを行なう為、利益を従業員に支払わず、内部留保し、なるべく銀行から借りない体制を好んだ。
この1990年頃というのは、ちょうど、ワシントン・コンセンサスが出て来た頃である。
1989年にアメリカの経済学者ジョン・ウィリアムソンによって提唱された概念を元にワシントンD.C.のシンクタンク「国際経済研究所」にて、ラテンアメリカ諸国の経済改革に関する政策提言が行なわれた。
ワシントン(=IMF・世界銀行・米財務省)で合意された政策パッケージを「ワシントン・コンセンサス」と呼び、ラテンアメリカや旧ソ連・東欧諸国などに新自由主義的な構造改革を要求する内容である。
それは、以下の内容が含まれる。
|
【構造改革の内容】 財政規律(政府赤字の削減) 公的支出の優先順位見直し(教育・保健などへ) 税制改革(広い基盤と低税率) 金利の自由化 通貨の為替レートの適正化 貿易自由化 外国直接投資の自由化 国有企業の民営化 規制緩和 所有権の保護強化(財産権の保障) |
因みに国有企業の民営化とは、国営企業を資本家に売り渡すということであり、金利の自由化や貿易自由化、外国直接投資の自由化、規制緩和などは、資本家がより多くの金を稼げるように改革することを意味する。
そのワシントン・コンセンサスの日本版が、アメリカが毎年、年次改革要望書によって日本に突き付けて来る金融市場改革の要求であった。
そして、これが最終的に1990年代後半に「金融ビッグバン」という形で、日本の金融市場が自由化されることになった。
2000年代前半には、小泉純一郎と竹中平蔵が、構造改革を行ない、規制緩和し、郵政民営化をして、日本の郵貯が保持する350兆円をアメリカの保険会社や投資ファンドが運用できるようにし、「小さな政府」路線で、財政健全化・歳出抑制を行なった。
(だから日本政府はこの頃から緊縮財政となった。日本の財務省はアメリカの言いなりである為、この頃から緊縮財政を行なっていることは明らかである。)
日本の企業は、この間、コストカットする為に従業員に支払わない体制を続け、従業員の固定費を変動費にして、利益を内部留保として溜め込み、非正規雇用に依存するようになった。
その後、女性の社会進出による新たな非正規労働力や、外国人労働者(外国人技能実習生制度などにより)などの安い労働力に依存するようになった結果、労働力は常に需要よりも供給の方が多い形になり、日本の労働者の実質賃金は、ずっと低く抑えられた。
最近、少しずつ上がってきていると言われるが、それでも、それはほんのわずかであり、外国の実質賃金の上昇率とは比べ物にならない。
そして、河野龍太郎氏によれば、日本の労働者の実質賃金が上昇しないことこそが、労働者(=消費者)つまりは日本国民の購買力の低下を招き、経済が回らない悪循環をもたらしているという。
そして、税収の減少を消費税などで補おうとし、また社会保険料の値上げなどによって、ますます、国民の生活は厳しくなり、国民の消費が停滞する結果を招いている。
日本の政治家、つまりは自民党の国会議員や財務省の官僚は、長年、アメリカの年次改革要望書に従うように条件づけられており、彼らの要求に屈して、国民の生活を売り渡すことによって、自分たちの安泰を図って来た。
アメリカの要求を受け入れて、日本の国民に不利な要求を呑んできたのである。(日本の国民を奴隷として外国に売り渡してきた)
日本政府(財務省)は、そのアメリカに対して屈辱的な自分たちの姿を日本人に見せないようにメディアを統制している。
日本政府のインバウンド政策とは、外国人を日本に呼び寄せて、日本の労働者の労働力を安売りして、それでかろうじて、外貨を稼ぐという屈辱的な政策となっている。
日本が円安になって、外国人が大量に入って来るまでは、日本人の安いサービスにより、日本人で低所得の人々もそれなりに生活が成り立っていたが、外国人の流入により、外国人向けのインフレが生じ、物価高で、日本人の消費生活がますます困難になっている。
企業は日本市場の内需がないため、海外進出するばかりで、日本人の稼いだ金を日本に投資しないため、日本人はどんどん貧しくなり、赤字国債を発行しまくった結果、日本円は、外国為替市場において、超円安を続けている。
これは、今後、元に戻らないと言われている。
企業は実質賃金を据え置いて、内部留保し、日本政府(財務省)は、社会保険料や消費税を値上げして、自分たちが招いた失策を日本の国民に押し付ける。
結局、日本人の給料が、長い間、増えないのは、1990年以降のワシントン・コンセンサスによる新自由主義政策の為である。
そして、アメリカの要求に屈して、金融制度改革をして、企業と銀行の株式の持ち合いや、メインバンク制を崩壊させ、外国人投資家の経済的侵略を許した日本政府の為である。
そして、その結果、実質賃金を上げず、利益を内部留保して、資金のショートに備える企業の為である。
しかし、根本的に言えば、グローバリゼーションそのものが、経済的、軍事的に強い国が、経済的軍事的に弱い国を支配するという、そのような構造を持っていると言える。
アメリカの支配者階級の中には、おそらく、ワシントン・コンセンサスを提唱し、政策として実施するような巨大な悪が潜んでいる。
彼らは、ジョン・ウィリアムソン、ミルトン・フリードマンとか、マイケル・C・ジェンセンといったアカデミックな経済学者や米シンクタンクを使って、政策として、提言して、政治力(軍事力)で、それらの政策を他国に押し付けて来る。
つまり、新自由主義とは、資本家による経済戦争であり、グローバリゼーションそのものが経済戦争である。
第二次世界大戦後、侵略戦争自体が、大っぴらに出来ない為、米財務省が、IMFや世界銀行や、多国籍企業を使って、他国に対して、経済戦争を仕掛けているというのが、戦後の世界である。
その戦後の経済戦争において、自分たちが経済戦争を戦っているという自覚がなく、そこから目を背けているのが、リベラル派である。
リベラル化した自民党、公明党、立憲民主党は、これらの事実に目をつぶって、それが経済戦争であり、日本が侵略されているという事実を直視しない。
日本がアメリカの属国になっていること、それを公の場で語ることはタブーになっている。
れいわ新選組の山本太郎でさえ、日本の経団連や財務省を批判しても、アメリカのことはそれほど批判しない。(言っても仕方がないからである)
参政党の神谷宗幣が、グローバリゼーションの問題をテレビの党首討論で、口にした時、他の候補者や司会者が凍り付いたように曇った顔になるのは、そのことが長年、財務省が禁止するテーマであり、テレビなど既存のメディアでは語ってはいけない類の話だからである。
財務省がアメリカに屈辱的に隷属していること、日本の国民の生活を売り渡して、彼らに媚びへつらって、自らの利権を確保していることを日本国民に知らせない為にメディアはそうした情報を一切、放送しない。
日本で参政党のような国家社会主義が起こり、もし政権を取得したら、アメリカはそれを潰そうとするだろうか。
しかし、このままリベラル派の政策だけで行く場合、確実にじり貧の状態に陥っていき、日本は、消滅させられるのである。
アメリカ自身もトランプ政権の誕生で、政変が起こっており、ワシントン・コンセンサスを推進したグローバリストが行き詰まりに陥っている。
プーチンのウクライナ侵攻も本質的に言えば、ワシントン・コンセンサスを推進したグローバリストに歯向かう行動である。
日本人もアメリカのグローバリストに逆らう気迫や気概を見せなければ、このまま行くと国家消滅の危機に瀕している。
その為、参政党のような党(「私たちは日本をあきらめない」)が遂に出て来た。
戦後において、日本は、GHQによって、極右勢力が戦犯として、公職から追放され、国家社会主義というものは、完全に消滅していた。
これまで一切、政治の世界に登場することはなかったが、世界の右傾化の流れの中で、ようやく日本にも登場した。
それも生活を追い詰められた日本人の国民運動として盛り上がりを見せている。
政治家がこうしたグローバル資本の問題に無知であってはならず、国家として、このグローバル資本にどう対応するかは国家主権を維持する為の政治家の大切な仕事である。
日本人全員が、常にこうした問題を知り、意識することで、状況は変わって来るはずである。
「日本経済の死角 – 収奪的システムを解き明かす – 」河野龍太郎著では、日本の労働者の実質賃金が上がらない問題を経済学の用語を使って、説明している。
単純化すればするほど、陰謀論のようになってしまうが、本質的に言えば、アメリカによる収奪、そして、その子分である日本政府(財務省)や自民党や経団連が日本人に低賃金を強いているのである。



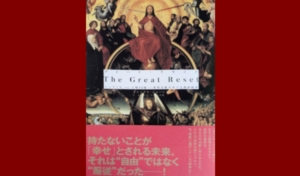


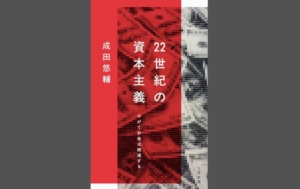
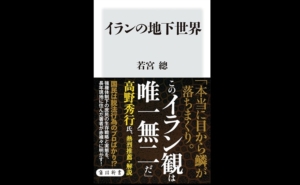

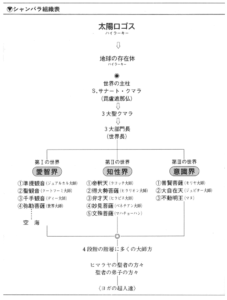
コメント