
私は、2008年頃、出版された安部 芳裕 (著)『
金融のしくみは全部ロスチャイルドが作った (5次元文庫)』を読んで初めて、信用創造の仕組みについて理解した。
経済学部などを出ていれば、そうしたことを多少たりとも勉強するのかもしれないが、それまで、そのような知識を得る機会が全くなかった。
安部芳裕氏のブログなども読んで、お金の仕組みについて学習したが、ユダヤ陰謀論的な本であったが、それでもお金の仕組みについて、全く知らなかっただけに信用創造に関して、重要な理解に到達した。
実は、主流派経済学(特に大学の教科書で使われるマクロ経済学)では、信用創造の現実的な仕組みや、お金がどのように「生まれ・消える」のかをあまり詳しく教えていない。
自ら理解に到達した人間にしかそれは明らかにされない業界の秘密なのであり、信用創造の本当の仕組みについては、一般大衆には隠されて来たのである。
つまり、市中銀行は、民間がお金を借りたい場合にその通帳に数字を記帳するだけでお金を創造できるのである。
その際、銀行はその貸すためのお金を持っている訳ではない。
今ではBIS規制などで自己資本比率というものが決まっていて、信用創造できる金額に上限が設けられているが、昔は、銀行は無限にお金を創造出来たのである。
その数字で記帳されたお金が銀行間をやり取りされるだけで、お金が流通していくことになる。
そして、このように信用創造したお金は、市場に流通しているマネーの90~95%程度である。
つまり、世の中のお金というのは、誰かの借金なのである。
お金が銀行に対する借金としてしか存在し得ないことが現在の悲劇であり、銀行家の陰謀として理解される場合も多い。
お金は経済活動にとって不可欠であるだけにお金を発行して、管理する銀行が、金利も付加することにより、世界経済を支配しているのである。
銀行が生み出したマネーに金利が付与される為、返済する金額は、貸し出したマネーよりも大きな金額となるが、それは市中には存在せず、新たな借金で生み出されたマネーから返すしかないのである。
つまり、借金はどんどん拡大していく仕組みになっており、民間が資金を借りなければ(新たな成長センターが見当たらない為、今は民間が金利を付けて借金を返すことが出来ない)、政府が借金するしかないため、各国政府の財政赤字(借金)は増え続けていくのが普通なのである。
その政府の国債発行(借り入れ)を行なわない場合、市中にはお金がなくなって、非常に国民は経済的に貧しくなってしまう。
この銀行家による介入を阻止するには、高度な物々交換の仕組みを開発するしかないのであるが、それはまだ存在していない。
先日、もう3年前の動画だが、西田昌司参議院議員が参議院の財政金融委員会で財務省の役人に国債の発行は信用創造と言えるかどうか質問するのを見た。
財務省の役人は、国債発行は、信用創造であると認めたのである。
<拡散希望>日銀が認めた!『財政破綻論』が崩れる歴史的瞬間!(参議院財政金融委員会:西田昌司参議院議員による質問 令和4年3月15日)





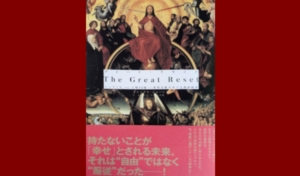


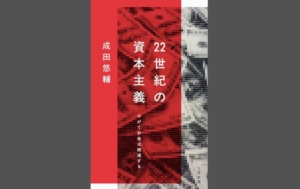
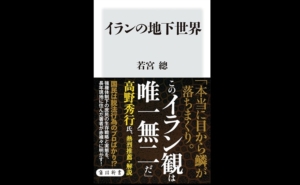

コメント