
2018年1月15日付の記事『独裁者・習近平の失脚のタイミング』で、今年の夏頃、習近平がマハダシャー火星期に移行したタイミングで失脚するのではないかと予想した。
前回の記事の検証では、習近平はこれまでに9回の暗殺未遂を経験している。
暗殺未遂を経験するような場合、身体を表わすラグナやラグナロードが激しく傷ついているはずである。
従って、習近平のチャートは乙女座ラグナで、ラグナロードの水星が3、8室支配の火星と10室でコンジャンクトし、12室支配の太陽と絡んで、6室支配の土星からアスペクトされている為ではないかと考えた。
もしこの考えが正しければ、まもなく習近平の火星期が始まるタイミングが迫っている。
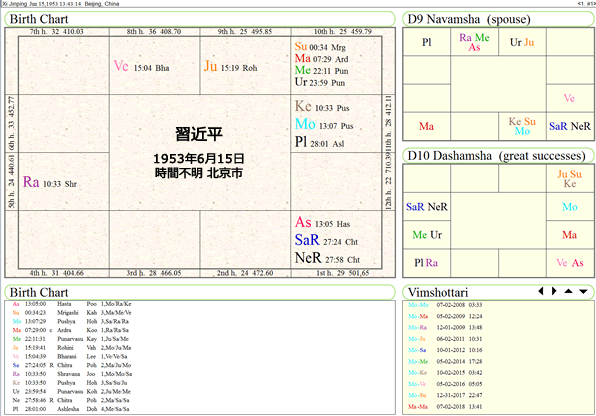
昨年(2017年)末の暗殺未遂の際も「爆発物は軍幹部によって持ち込まれて設置された可能性が高い」との見解が伝えられている。
|
習近平氏 9回目の暗殺未遂にショックを受け一時入院か 2018年1月14日 7時0分 NEWSポストセブン 中国の習近平国家主席が年の瀬の差し迫った昨年12月下旬、人民大会堂での会議が終わった駐車場で専用車両に乗ろうとした際、爆発物が破裂。習氏は腹痛を起こし、そのまま北京市内の中国人民解放軍直属の「中国人民解放軍総医院(略称「301病院」)に緊急搬送されていたことが分かった。今回の病院搬送は極度の緊張が原因との見方もでている。米国を拠点にする中国問題専門の華字ニュースサイト「博聞新聞網」が301病院の関係者から独自に聞いた話として伝えた。 習氏一行が病院に駆け込んだことで、病院は一時的に閉鎖措置をとられ、他の患者は締め出されるなど、厳重警戒措置が敷かれたという。 人民大会堂に仕掛けられた爆発物は軍が使用しているものであることや、人民大会堂には一般市民は立ち入ることが禁止されていることから、爆発物は軍幹部によって持ち込まれて設置された可能性が高いとみられている。当日の防犯カメラ映像などがチェックされているほか、軍の警備担当者も個別に事情を聞かれているもようだ。 中国では昨年、軍最高指導部に当たる中央軍事委員会委員である房峰輝・元中央軍事委連合参謀部長や張陽・中央軍事委政治工作部主任が腐敗容疑で事情聴取を受けたあと、軍の要職を罷免されている。このうち、張氏は自宅で自殺している。このため、爆発物を仕掛けたのは、両者に連なる軍幹部ではないかとみられている。年末から年始にかけて、軍幹部が集中的に事情を聞かれているという。 習氏の容態だが、過度の緊張状態になり、その影響で胃痛が出たものとされ、深刻な影響はない模様だ。 しかし、習氏は大事をとって、301病院で、念のために精密検査を受けたほか、疲労をとるために特別病棟に一泊し、翌日の朝食後、退院したという。 習氏を狙った暗殺未遂事件はこれまでに、少なくとも8回発生していると伝えられており、今回が9回目になるという。 習氏は政敵や反対派の幹部追い落としのために、反腐敗運動を推進。汚職容疑などで多くの幹部を失脚に追い込んでいる。そのため習氏を狙う者も多く、習氏は一時も気が休まるときもないようだ。このため、精神的には常に緊張状態に置かれており、今回のような突発事件で、体調に異常をきたすことも珍しくないことが想像される。 |
ラグナロードの水星とコンジャンクトする3、8室支配の火星とは、明らかに習近平に反発する軍人を表していると考えられる。
火星の表示体としては、それ以外、考えにくい状況である。
一昨日(2018/6/26)付けのニュースでは、中国で退役軍人が大規模デモを行ない、警察当局と衝突したことが伝えられている。
|
中国で退役軍人が大規模デモ、警察当局と衝突 2018年06月26日 08時04分 読売オンライン 【上海=吉永亜希子】香港の英字紙サウスチャイナ・モーニングポスト(電子版)などは25日、中国江蘇省鎮江市で、待遇改善を求めて集まった退役軍人のデモ隊と警察当局が衝突し、負傷者や拘束者が出たと報じた。 報道によると、今月19日、鎮江市政府庁舎前に退役軍人が集まり抗議を始めた。参加者は数千人規模に膨れあがり、地元当局は25日未明に数百人の武装警察を投入したという。 中国本土のメディアは報道していない。中国版ツイッター「微博ウェイボー」に投稿された画像はすぐに削除されており、騒動が広がらないよう、当局が情報統制を敷いているとみられる。 香港経済日報によると、退役軍人の抗議活動は、軍トップの習近平シージンピン中央軍事委員会主席(国家主席)が2015年に軍改革の一環として30万人の削減を表明して以降、増えているという。16年10月と17年2月にも首都・北京で同様のデモがあった。 |
中国は歴史的に見ても黄巾の乱、太平天国の乱など大規模な武装闘争が民衆の側から立ち上がる歴史がある。
易姓革命理論によって、徳を失った王朝に天が見切りをつけたとき、革命が起きるとされている。
中国史において、易性革命が起きる場合、中国は内戦状態に陥り、国民のかなりの数がその中で命を失ったり、社会の富や文化的財産が破壊されて、歴史が一度リセットされるようなことになり、かなりダイナミックな動きが生じるのである。
習近平の独裁体制に関しては、共産党内にも国民の中にもかなりの不満が蓄積されており、習近平が軍の全てを掌握して独裁体制を強化する為に軍制改革を行なったことも軍幹部にとって不満が溜まっているようである。
また今回のように職を奪われた退役軍人が不満をかかえてデモを起こしている。
このような一部の軍人から始まったデモが中国の一般市民にも飛び火して大規模なデモに発展する可能性を秘めているのである。
私が最近、参考にしている政治経済本として、『米国が仕掛けるドルの終わり 2019年、日中同時破綻の大波乱』吉田繁治著 ビジネス社がある。

吉田繁治氏によれば、中国の不動産価格の下落と崩壊が2019年~2021年に起こると指摘している。
おそらく不動産バブルが崩壊して、経済が冷え込み、人民の不満が爆発すれば、それは不満を持った軍人たちと一般民衆が合流して、大規模なデモに発展する可能性がある。
習近平のマハダシャー火星期というのは、7年間あるが、おそらく習近平が、そうした激しい政治闘争に巻き込まれていくことを表しているのではないかと考えられる。
暗殺未遂などの暴力にさらされ、一方で、自らも武装警官や軍を投入して、その反乱の鎮圧を行なうといった激しい象意になるのではないかと思うのである。
現在は、マハダシャーの月で、月は11室支配で11室の蟹座自室に在住して、高い肩書きや地位に留まっているが、火星は3、8室支配の機能的凶星である。
乙女座ラグナの場合、3、8室支配の火星は、凶暴で暴力的で、ストーカー体質の激しい人物によって支配されたり、悩まされたりすることを表している。
3、8室支配の火星が10室に在住することによって、自らの政治活動や公務が中断されたり、停滞、行き詰まりといった状況に陥るのである。
中国はこれから習近平の火星期が象徴するように国内の軍人たちや民衆の激しいデモ活動、内乱に近い形の激しい政治闘争に移行していく可能性がある。
その過程で、習近平は、これまでそうだったようにやはり暗殺未遂を何度も受けると考えられる。
3、8室支配の火星は、ラグナロードとコンジャンクションし、ラグナにアスペクトしているため、マハダシャー月期の間は、難を免れた習近平も、火星期には、致命的打撃を受ける可能性がある。
そして、それが失脚につながっていく可能性が高いのである。
月をラグナとした場合でも、火星は、6、11室支配で12室で、3、12室支配の水星とコンジャンクトし、2室支配の太陽と接合し、7、8室支配の土星からアスペクトされている。
6室や12室といったドゥシュタナハウス同士が絡み、更にマラカである7、8室支配の土星がアスペクトしている。
中国の建国図を見ると、2019年9月24日からマハダシャー水星期に突入する。
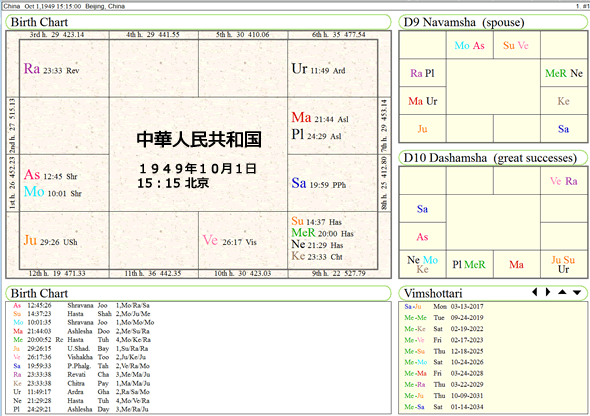
この水星には8室支配の太陽がコンジャンクトし、生来的凶星であるケートゥがコンジャンクトしている。
また6室支配の水星も絡んでいる。
8室支配の太陽は、支配者の暗殺とか失脚を象徴していると考えられ、ケートゥとのコンジャンクトもまさに支配者の没落を表している。
従って、習近平がマハダシャー火星期の間で、中国建国図が、傷ついた8室支配の太陽と絡むマハダシャー水星期になるタイミングは、習近平の失脚を表していると考えられる。
中国の建国図で言えば、これまで続いてきたマハダシャー土星期(19年間)が終わって、マハダシャー水星期(17年間)が始まるタイミングであるため、かなり大きな国家の転換期であると言うことが出来る。
易姓革命で王朝の交代が繰り返された来たダイナミックな中国の歴史からすれば、やはり、このようなマハダシャーの切り替わりなどの大きな区切りに関しては、注目に値するタイミングである。


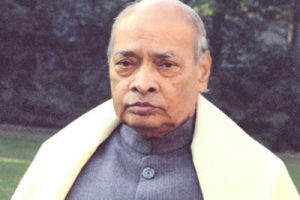



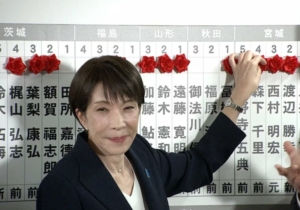



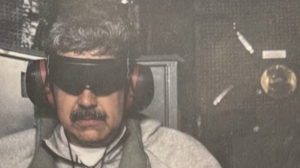
コメント