
日本の平均給与が韓国に抜かれたとか、円安が進行していること、巨額の財政赤字を抱え、国民一人あたりの借金が800万円以上あることなど、日本社会の凋落が目立っている。
野口悠紀雄著『日本が先進国から脱落する日 “円安という麻薬”が日本を貧しくした?』がビッグマック指数というものを紹介しているが、それによれば日本のビッグマックは、アメリカなどと比較してかなり安いという。ビッグマックの価格はその国の経済力を反映する一つの指標として分かりやすいが、今では、日本のビッグマックは、タイよりも安いという。

この本の中で、日本人の給与はなぜ上がらないのかということについて考察しているが、結論として、日本はインターネットによる技術革新が遅れ、電子化が遅れていて、生産性が上がっていないことが挙げられている。
日本人の一人あたりの労働生産性は先進国の中で最も低いと言われているが、労働生産性は、「インプットに対してどれだけのアウトプットが生まれたか」を表す指標で、「労働生産性=アウトプット/インプット」の式で、求められる。
どれだけ少ない労働でどれだけ多くの生産が出来たかを示す指標である。
日本では、一つの仕事により多くの労働者が関与し、より多くの時間をかけている為、労働生産性が低くなっている。
日本の経済的凋落は、労働生産性の問題だけではなく、GAFAのような勝者総取り経済が流行ってしまって、日本経済がこれらの巨大IT企業によって浸食されているとか、第二次世界大戦の敗戦国で、事実上、米国の占領が続いており、米国に何かと理由を付けては金銭を要求され、それを拒むことが出来ないなど、政治的な理由も考えられる。
またアジアで中国や韓国、その他の国が発展途上国が工業国に変化して、日本のライバルとなったことも大きいかもしれない。
これまでは、労働生産性が低くても問題なかったということかもしれない。
色々な理由があると思われるが、労働生産性が低いというのは、重要な観点である。
然し、この労働生産性が低いというのは、日本人の本質、民族としての日本人に深く染みついた考え方、価値観から来ているので、これを変えるというのは、非常に困難である。
例えば、経営の神様と呼ばれた松下幸之助は、「一人も解雇するな、一円も給料を下げるな」という考え方で、経営者の鏡と言われている。
経営をIT技術などで自動化し、合理化したら、従業員は必要なくなるので、解雇しなければならないが、その従業員を解雇しないという美徳やポリシーがある為、どうなるかと言えば、従業員に対して、必要性のない仕事をわざわざあてがって、雇用を維持するということになる。
その結果、AIを駆使し、自動化などによって、業務を効率化するというモチベーションが全く出てこないのである。
合理化したら仕事がなくなってしまうので、そうすると雇用が確保できないので、あえて合理化しないのである。
安い従業員の労働で、その仕事を行なおうと考える。
そして、その方が、労働者に仕事を与えるという観点から良いと見なされるのである。
まず、そもそも人間はお金を得るために労働しなければならないという観点、そして、労働者に雇用を与えることは良いことだという観点、こうした深く染みついた考え方が変わらない限り、どうしようもないのである。
これは表面上、美徳の名の下に装飾しているが、封建時代の領主様が、農奴をいくらでもただ働きさせられるという発想の名残りである。
くだらない仕事をやらされるなら、会社を辞めてしまおうと考える人が増え、インターネットを使って、自営で稼ぐ手段も増えてきており、また少子高齢化ということもあって、若い労働力が不足し始めたので、それで、外国人労働者を連れて来て、労働者をまかなうというのが、現代の奴隷制度と言われる外国人技能実習制度のようである。
より少ない労働者で仕事をまかなうという合理化を進めなかったせいで、経済力が低下して、そのツケが労働者の給与が上がらないという結果に結びついて、生活の安定がないため、少子化がもたらされ、最終的には外国人労働者に頼らざるを得ない状況になったのである。
そう考えると、日本の経営者の鏡で、日本の美徳を体現していた松下幸之助の考え方が時代に合わないということになってしまう。
日本の昔の素晴らしい価値観や美徳が、今の社会には通用しないのである。
イーロンマスクなど、労働者の解雇などは、瞬時にできるそうだ。
日本は、高度経済成長時代から自動車や優秀な家電製品などを世界中に売りまくって、一時期はほんの一瞬だけGNPが米国を抜いて、世界No.1となったこともあった。
「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と称されて、世界2位の経済大国の地位についていたが、それでその先のビジョンがなかったようである。
経済的に豊かになった後、そのあり余る資本で、ゴルフ会員権や美術品を買い漁ったり、不動産を買い漁ったりするだけだった。
それで不動産バブルが弾けて、それ以後、失われた20年、30年という状況になっている。
野口氏によれば、円安にすれば、輸出企業は技術革新などしなくても売り上げが上がるので、長い間、円安に誘導した日本の政策は、麻薬のようなものであり、それに依存した結果、日本はいつのまにか経済的に凋落していたということである。
特に2012年から始まったアベノミクスが国民を貧しくして株価を上げたとして、批判的に捉えている。
上述したが、まず、決定的に問題なのは雇用を確保するという考え方である。
日本がインターネットによる技術革新をしたがらない理由は、合理化をして人員を削減すると、少ない人員で作業がこなせるため、雇用が失われる。
雇用が失われると、生活できない人が増えて社会不安が増す為、あえて技術革新しないで済ませてしまうのである。
技術革新しないで、安い労働者にその仕事をさせて、それで済ませてしまう。
またわざわざ雇用を確保する為に生み出される仕事というものもある。
道路に穴を掘って穴を埋めるような公共工事とか、そうしたものである。
あるいは、公共施設などに行くと、ただ座っているだけで何の為にいるのか分からないような受付の仕事などがある。
日本は元々優秀な一部の研究者が、優れた製品を生み出して、後の人は特にたいした仕事をしなくても給料をもらえるような社会だったのかもしれない。
ただハンコを押すだけのような中間管理職が大勢いたりといったことである。
機械化し、自動化して、人員を削減するといったことが中々モチベーションにならない。
日本が「おもてなしの国」であり、世界一のサービスを誇る国であったということも原因しているかもしれない。
サービスにおいて活躍するのは、人間による献身的なサービスである。
だからそのサービス労働者を削減して、合理化してしまうというモチベーションにもなりにくいのである。
最近は、日本でもスーパーマーケットで、レジ打ちや、レジの袋に商品を詰めるようなことは全て、客にやらせるというように変わって来ている。
究極的にはサービス労働者というものは完全に必要なくなっていく。
日本もしぶしぶ合理化の波に従うようになっているが、それは売上が上がらないので、経費を削減するために強制的にそうせざるを得なくなってきたからである。
合理化自体を良いものとみなして、合理化する思想はないのである。
例えば、第二次世界大戦の末期に日本の軍人が操縦して相手の戦艦に突っ込んでいく「回天」という人間魚雷が開発されたが、安い労働力を使って、技術の無さを補い、人力で魚雷の方向を制御するようにしたのである。
人間のサービスや労働を安く見積もっているので、そういう発想になるのである。
「働かなければ食うべからず」という言葉があるが、昔からのこの考え方からすれば、人は生活費を稼ぐために何らかの仕事をしなければならないのである。
その為、わざわざ経営者はほとんど必要ないような仕事を生み出して、その仕事(ブルシットジョブ)を従業員にあてがうのである。
欧米の経営者は、必要ないとなったら、即座に従業員の首を切ることが出来るが、日本の経営者は松下幸之助のように従業員の首を切らないことを信条とする経営者も多いと思われる。
やはり、日本は、合理化という思想において徹底していないし、徹底できないのである。
合理化しない代わりに合理化しないことで損害が発生したら、従業員に犠牲や献身を求めていくという考え方である。
2014年に刊行された本だが、最近、読んでみて、非常に感銘を受けたものにピーター・ティール著『ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか』がある。

ピーター・ティールは、この本の序文で、ヨーロッパの中世においてルネサンスや近代合理主義への道を開いたフランシス・ベーコンに匹敵するような現代のカリスマとして紹介されている。
この本の中で、企業活動は、競争よりも独占の方が圧倒的に優れていると述べている。
市場を独占して利益を生み出せる企業は、長期的ビジョンを持つことができ、研究開発に資金を投入することができ、技術革新などをもたらすことが出来ると述べている。
一方で、競争は薄利による消耗戦になり、余裕がなくなり、短期的なビジョンしか持てなくなるという。
何故、経済学において、完全競争を良いとするのかは、経済学は物理学をモデルにして誕生した理論だからだと述べている。
|
(略)独占は進歩の原動力となる。なぜなら、何年間、あるいは何十年間にわたる独占を約束されることが、イノベーションへの強力なインセンティブとなるからだ。その上、独占企業はイノベーションを起こし続けることができる。彼らには長期計画を立てる余裕と、競争に追われる企業には想像もできないほど野心的な研究開発を支える資金があるからだ。 では、なぜ経済学者は競争を理想的な状態だと説くのだろう? それには歴史的な経緯がある。経済学の数式は一九世紀の物理学の理論をそのまま模倣したものだ。経済学者は、個人と企業を独自の創造者ではなく、交換可能な原子と見なす。経済理論が完全競争の均衡状態を理想とするのは、モデル化が簡単だからであって、それがビジネスにとって最善だからじゃない。一九世紀の物理学が予測した長期均衡とは、すべてのエネルギーが均等に分布し、あらゆるものが静止した状態──いわゆる宇宙の熱的死だ。熱力学をどう考えるかはさておき、これは強烈な喩えで、ビジネスにおいて均衡は静止状態を意味し、静止状態は死を意味する。競争均衡にある業界では、一企業の死はなんの重要性も持たない。かならず同じようなライバルがその企業に替わるからだ。(略) (『ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか』ピーター・ティール, ブレイク・マスターズ著より引用抜粋) |
これは常識を覆す発想である。
通常は競争があるから、企業は合理化を進め、イノベーションをもたらすという考え方だからである。
ピーター・ティールによれば、競争を良いとするのは事実から出た知見ではなく、イデオロギーであるという。
ここでピーター・ティールは、企業活動について述べているが、人間についてもこれは言えることである。
人間も明日食べられるかどうかという不安の中では、長期的ビジョンをもてないのである。
政治家は次の選挙のことを考え、官僚は自分の保身のことを考える。
そこからは現状維持の考えしか出て来ず、何の合理化もイノベーションも起こらないのである。
各省庁は予算を確保する為に自分の所では、多くの人材が必要であることをアピールしなければならない。
従って、業務を合理化して、より少ない予算と人員で仕事を行なうように改善することは全く動機とはならない。
企業活動でも自分の仕事がAIによって自動化し、合理的に処理できるようになったら、自分の仕事がなくなってしまう。
それで合理化に反対することになる。
自分が支配できる部下が減ってしまうことも面白くないかもしれない。
封建的な価値観の人間にとっては、部下をたくさん抱えて、単に自分が威張ったり、支配出来たり、影響力を振るう立場になること自体が、動機となったりもする。
そこで思うことは、やはり、『ブルシット・ジョブ──クソどうでもいい仕事の理論』のデヴィッド・グレーバーが言うようにさっさとベーシックインカムを導入してしまうということが根本的な解決策になって来ると思われる。

ベーシックインカムというのは、人間は働かなくても生存する権利として、お金を国から支給されるという思想なのである。
それは、憲法で保障する生存権の拡張であり、あるいは、それを実現するための具体的な施策であるとも言える。
これによって何が起こるかと言えば、人々の間で、明日の自分の糧を得るための競争というものがなくなり、自分の保身を考えなくなる為、徹底的な合理化が可能になるのである。
それによって機械化、自動化を推し進め、生産性を極限まで高めることができる。
これは、雇用をつくらなければならないという思想の背後にある「人は働かなければ食うべからず」という考え方とは根本的に異なる思想である。
生活が保障されていなければどうしても人は、自分の明日の糧を得るために保身に走らざるを得ない。
そのため、ブルシットジョブにしがみ付くし、また雇用の確保の為にブルシットジョブでも与えなければならなくなり、合理化へのモチベーションがなくなってしまう。
欧米と日本の違いは、そもそも近代科学は欧米で生まれた為、理性の光によってあらゆるものを照らして、自然を改変していくという思想において欧米の方が徹底している点である。
だから、合理化を進めるという点において妥協がないのである。
経済的に豊かになってもその先のものが見えていたと言える。
日本は、豊かになったら、その金で何をすればいいのか分からなかったようである。
その有り余ったお金で、更に社会を合理化していくという方向に向かわずにゴルフ会員権や美術品を買い漁ったり、不動産を買い漁ったりして、バブルを生み出しただけだった。
人権や民主主義などの社会的な点にしても科学や技術的な視点においても社会が更に発展していくその先の思想やビジョンというものがなかったようである。
だから金だけ持っている動物として、エコノミックアニマルと呼ばれたのである。
欧米社会は合理化によって生産性が上がった分をきちんと従業員の給料に反映しているのである。
日本は合理化によって生産性を上げ、その分を従業員に還元するのではなく、合理化をせずに従業員に雇用を与えて、生産性が上がらない分を従業員の給与を減らすことによって、まかなうという方策に出たのである。
日本人の本性として、上司や部下に献身するが、上司や部下に対して自分に献身させるという性質がある。
これは魚座が強い人と接した時に分かるが、魚座が強い人は、人に良くサービスするが、人にサービスを要求するのである。
つまり、部下にサービスするが、部下のサービスを求めるというのが日本人の本性である。
あるいは、お上にサービスするが、お上のサービスを求めるというのが日本人の本性である。
そうしたサービスの国であり、部下に対するサービス、お上に対するサービスを尊いと考える文化や価値観である為、合理化は日本人には向いていないと言わざるを得ない。
そして、お上は部下に犠牲や奉仕を求めるし、部下もお上に犠牲を求めるのである。
だから日本人は、天皇に対しても犠牲を求めるような国民性である。
天皇は、常日頃から国民の為に祈り、献身する存在でなければならないのである。
天皇が贅沢をして、国民にサービスしていないような場合、国民は天皇に対しても怒り出す。
日本の天皇は、日本国民の顔色を伺わなければならない存在である。
こうした日本人の国民性は、魚座、蟹座、蠍座などの水の星座によってもたらされている。
これは日本のマンデン図で、魚座に金星や水星が在住していることに現れているが、ホロスコープとは直接関係なく、日本は魚座、蟹座、蠍座の象意で満ちている。
合理化を進めていくと最終的に労働者は必要なくなり、労働によって賃金を得るような仕組みがなくなるのであれば、やはり、ベーシックインカムのような仕組みを作らざるを得ない。
然し、それを進んで行う為には、まず、労働が尊いもので、人は労働の見返りにお金を得るという考え方、労働者の為に雇用を確保するといった考え方がなくならなければならず、人は基本的に生存する為のお金をもらう権利があり、創造性の見返りに更なるお金を得るという考え方にならなければならない。
合理化して人間による労働を無くして雇用を無くしていくという考え方が、良いことと見なされなければ合理化が難しいため、生産性も上がらない。
雇用を無くすことがよいとみなされるには、社会的な安定が必要であるため、ベーシックインカムのような制度が必要である。
然し、もしこれを立憲民主党などが求めるような社会保障の充実、大きな政府で行なおうとすれば、その制度の運用に大きなコストがかかり、企業に対して、もっと税金を要求したりすることになり、合理化とは逆の方向に向かってしまう。
行政自体も極限まで合理化しなければならず、社会保障など様々な制度を一本化して、国民に対して一律支給のような単純な仕組みにしなければならない。
そうした行政の合理化を進めるには、ベーシックインカムのような制度が普及して、生存権が保証されないと、自分の仕事が無くなることを恐れる為、合理化に抵抗することになる。
合理化し、人間の労働を減らすということを積極的に求めるようになるかがポイントである。
その為には思想、価値観などの根本的な所からの転換が必要である。
因みに欧米社会では、合理主義が徹底している為、日本人のような献身の美徳はなかったとしても無駄を排除し、利益を最大化するという利益追求の観点から合理化が進んでいる。
日本人の献身の美徳は、逆に合理化の妨げになってしまっており、場合によっては労働者に献身を求め、多大な犠牲を強いるという不徳として現れている。
労働者を貧しくして株価を上げたアベノミクスは、その最大の悲劇である。
日本は、単にAIの導入やITによる電子化、自動化といった技術的な問題だけではなく、考え方、価値観などの根本的な転換を迫られている。
それが得に既得権益を握る日本の老人や高齢の人々に求められている。
立憲民主党は、そもそも経済における合理化の役割についてあまり分かっていないのである。
立憲民主党は、男女平等の推進、LGBTなどのマイノリティーの権利、労働者の権利を守るといったこと、人権や民主主義には関心が高いが、経済に疎く、行政を合理化するという発想がない。
だから行政の無駄を削減し、ベーシックインカムなどを支給することを掲げる、日本維新の党の方が人気が出てしまう。
特に民主主義は効率が悪いので、国家社会主義的であり、トップの指導力によって、改革を断行するような党の方が魅力的に見えてしまう。
現在、世界で進んでいるITによる電子化やAIを駆使して自動化、効率化をもたらすという動きは、日本は自分から進んで取り入れることはなさそうである。
世界が取り入れているから、真似をして、一番、遅れて取り入れているに過ぎない。


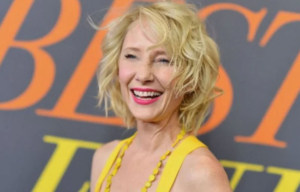


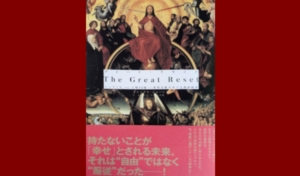




コメント