
先日、映画『ウォール街』を久々に見た。
オリバー・ストーン監督の1987年の作品で、マイケル・ダグラスが、投資家ゴードン・ゲッコーに扮して、インサイダー取引などで、ぼろ儲けしている投資家を演じている。

証券マンに扮するチャーリー・シーンがゴードン・ゲッコーの使い走りで、インサイダー情報などを収集して、ゲッコーに提供し、多額のバックマージンを受け取る。
父親が務める航空会社の買収をゴードン・ゲッコーに提案するが、ゲッコーが、会社を解体して、航空機や設備など、会社の資産を売り、社員のために積み立てられた年金を自分の利益としようとしていることを知り、最後にゴードン・ゲッコーを裏切って、ゲッコーは逮捕される。
この時代は、まだコンピューターでの取引が行われておらず、証券マンに、電話で、株の注文をしている姿が目に付いた。
まだWindowsなどのOSも普及していなかった時代である。
オリバー・ストーンは、「プラトーン」や「JFK」などでアメリカの欺瞞を暴露して来たリベラル派の映画監督で、「ウォール街」で描いたのは、証券マンとなって経済的に成功しようとしたチャーリーシーンが、最後に回心して、父親の航空会社の買収を阻止し、ゴードン・ゲッコーの逮捕に協力するシーンで終わる。
ゴードン・ゲッコーとの会話の録音をFBIに渡して、最後にゴードン・ゲッコーがその後、逮捕されることを匂わせて映画は終了する。
欲望の塊である投資家が、最後にインサイダー取引で逮捕される姿を見せることで、強欲な資本主義に警鐘を鳴らすというのが、オリバー・ストーンの意図だったと分かる。
映画の中で、ゲッコーは、自分が出資する会社の株主総会に姿を表わし、経営陣が、いかに怠慢で、会社の富を失ったかを力説し、会社は株主のもので、欲望は善であると、主張した。

皮肉なことにこの映画を見て、主人公の投資家ゴードン・ゲッコーに憧れて投資銀行に入社する者やゴードンのファッションなどを真似る者などが後を絶たなかったそうである。
作品は、実際のウォール街にも大きな影響を与えたようである。
人々は、ウォール街から足を洗うチャーリー・シーン扮する証券マンよりも、マイケル・ダグラス扮するゴードン・ゲッコーに憧れたようである。

その23年後の2010年に再び、オリバー・ストーンが監督を務めて、続編である『ウォール・ストリート』を撮影した。

ちょうど、2008年、2009年のサブプライムショックで、株式市場が崩壊した直後である。
映画は、インサイダー取引と証券詐欺罪で、8年の懲役の服役を終えて、ゴードン・ゲッコーが刑務所から出所するシーンからスタートする。
ゴードン・ゲッコーが出所した時、既に時代は変わり、インターネットによる株式の取引が活況を呈し、サブプライムローンを担保にしたCDO(債務担保証券)が大量に出回って、株式市場は、バブル状態となっていた。 そこで暗躍していたのが、サブプライムローンで稼ぎまくっていた投資家のブレトンである。

ブレトンは、ゴードン・ゲッコーが、活躍した時とは比べ物にならないぐらい強欲に利益を上げていた。
ゴードン・ゲッコーは、8年間の刑務所生活を送ったためか、今では、人生の時間が最も大事だと考えるようになっていた。
この映画のワンシーンで、前作で、証券マンに扮したチャーリーシーンがちょい役で登場し、ウォール街の成功者ブレトンが主宰するパーティーで、ゴードン・ゲッコーとばったり再会するシーンがある。

チャーリーは前作で、ゲッコーから救った父親の航空会社の経営を立て直し、それを売却して、多額の利益を上げ、今では贅沢な暮らしをしていると述べる。
ゴードン・ゲッコーは、成功した投資家ブレトンと会うと、実質的な価値のないCDO(債務担保証券)を大量に売ることで、バブルを招いていることを批判する。

ゴードン・ゲッコーは、刑務所に収監される前に娘の名義で、スイスの銀行口座に預けていた100億円を引き出すことに成功し、その金をサブプライムローンがはじけて暴落した株式市場で、実物資産に投資して、2000%ぐらいのリターンを弾き出し、完全復活する。
映画では、最後に娘が投資しようと考えていた海水利用の水素発電を開発中のエネルギー企業に100億円を娘の名義で投資して、娘にお金を返すシーンで終了する。
ゴードン・ゲッコーも家族のきずなを大事にしているということを描いて映画は終了するのである。
初回の作品で、オリバー・ストーンは、ゴードン・ゲッコーのように会社を育成し、事業を育てるのではなく、会社を解体し、その資産を切り売りする投資姿勢や、インサイダー取引などの不正な取引を用いてでも利益を上げようとする強欲資本主義を批判した。
次回作では、価値のないサブプライムローンを担保にしたCDO(債務担保証券)を大量に売りさばいて、バブルを生み出した投資家を批判した。
サブプライムショックで、株式市場が暴落して、アメリカ政府は、破綻間際にある投資銀行に公的資金を投入して、救済した。
リベラル派では、ウォール街を囲め運動などが起こって、それで投資家は反省したと思いきや、現在、再び、似たような金融商品を売りまくって、またバブルが起こっている。
このオリバーストーンによる次回作は、サブプライムローンを担保にしたCDO(債務担保証券)でバブルが生み出されたことには批判的だったが、今ひとつ主張するテーマがはっきりとしなかった。強欲資本主義を批判するメッセージ性が、前作よりも弱まっていたように思われる。
前作では、証券マンであるチャーリーシーンの父親(マーティン・シーン)が航空会社の労働組合のリーダー的な存在で、金に無頓着で、清貧な男だった。
強欲資本主義とは対照的な存在として、登場させることで、強欲資本主義を批判する鍵となるキャラクターとなっていた。
次作では、チャーリーシーンが扮する証券マンが、航空会社の経営を立て直して、それを売却して、巨額な利益を得たこと自体に全く批判的ではない。
またゴードン・ゲッコーが、娘の名義で信託した100億を使って、暴落した相場で、再び実物資産を買いまくり、完全復活を遂げることにも全く批判的ではない。
『ウォール街』や『ウォール・ストリート』では、基本的に資本主義によって、人が富を追求すること自体は、批判していないのである。
せいぜい、企業を切り売りしてはいけないし、インサイダー取引をしてはいけないとか、価値のないCDO(債務担保証券)を売りさばいて、バブルを招いてはいけないといったメッセージを発信できただけである。
そして、最後にゴードン・ゲッコーが娘との父子のきずなを大事にしているという家族愛を少し描いて終わりである。
リベラル派で、ベトナム戦争に批判的で、JFKの暗殺にも批判的で、ウォール街の強欲資本主義にも批判的だったオリバーストーンは、それでも、『ウォールストリート』で、アメリカの株式市場自体が悪であるとは描けなかったようである。(描かなかったようである)
株式市場や資本主義自体には批判的ではなかった。
この次回作は、最初の作品からおよそ20年後の2010年に制作されたが、その後、また社会もだいぶ様変わりして来ている。
サブプライムショック後に再び、ウォール街は活況を呈し、株高となっており、またビットコインなどの仮想通貨も登場した。
世界で右傾化が始まって、戦時体制となり、アメリカでは中間層が壊滅し、富裕層と貧困層に二極化しているという。
資産バブルが生じ、インフレも凄まじく、貧困層で、強盗、窃盗などが多発している。
アメリカで2024年に株式市場が崩壊し、世界的な不況に入っていくことが予想されるが、今は、多くのアメリカの若者は、共産主義を望んでいるという。
今は、世界が右傾化して、オリバー・ストーンも全く、陰に引っ込んでいるが、また新たなテーマで作品を創らなければならない状況になりつつある。









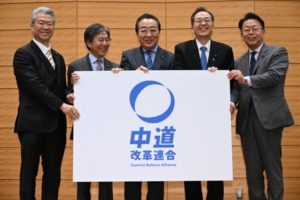


コメント