
中国が経済発展して、他国に対する経済的な影響力を増している中で、オーストラリアは中国への経済依存度を高め、その影響を最も被ってきた国である。
最近、オーストラリアのクライブ・ハミルトン教授が書いた『目に見えぬ侵略 中国のオーストラリア支配計画』という書籍が、書店の平棚に並んでいたが、中国が長年、多額の金をばら撒き、オーストラリアの世論を操作しようとしてきた実態を告発した本である。
オーストラリア経済は、天然資源を外国に買い取ってもらうことで成り立っている為、その最大の購入者である中国がお得意様で、貿易相手国としてその依存度を強めていた。
然し、最近、オーストラリア国民が、中国の影響力が高まるのを警戒し、国民世論は、急速に親中から嫌中に変化しているようである。
その後、オーストラリア政府は、中国系企業による戦略資産の買収を規制すると発表し、州政府や自治体が認可した買収案件に対し連邦政府が拒否権を発動できる法律を策定した。
|
州と外国の協定締結に「拒否権」 中国念頭に、豪で法案可決 2020年12月08日15時00分 JIJI.com 【シドニー時事】オーストラリア議会は8日、同国の州政府や大学などが外国政府と結ぶ協定が国益を損なうと判断すれば、外相が拒否権を発動できるとした法案を可決した。中国を念頭にした措置で、豪中関係の険悪化につながりそうだ。 豪州では南東部ビクトリア州が、中国の巨大経済圏構想「一帯一路」に慎重な連邦政府と十分に相談せずに、同構想に関する覚書を結んだ。この覚書が拒否権発動の第1号になる可能性がある。 |
ニューズウィーク日本版の記事、『中国の傲慢が生んだ「嫌中」オーストラリア』によれば、2019年当時、マイク・ポンペオ元米国務長官の「一山の大豆のために魂を売るか、それとも自国民を守るか、2つに1つだ」といった発言で、オーストラリアの国民に警鐘を鳴らしたようである。
オーストラリアは、元々は、イギリスの植民地であり、現在でもイギリス連邦の加盟国であるが、1901年1月1日のオーストラリア連邦憲法が、シドニーで宣言され、エドモンドバートンが初代首相に就任した時に事実上の独立を果たしたようである。
アストロデータバンクには、その日時が、「1901年1月1日13:35 シドニー、オーストラリア」と記されている。
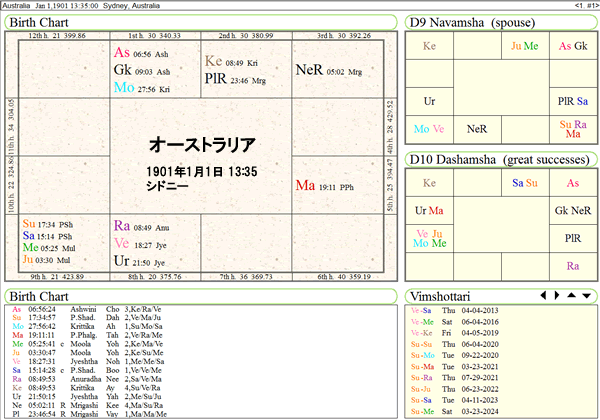
このデータで、チャートを作成すると、ちょうどマイク・ポンペオ氏の発言にも促されて、パンよりも魂を選んだ2020年頃からオーストラリアのマンデン図では、マハダシャー太陽期に移行している。
太陽は5室支配で9室に在住し、9、12室支配の木星や10、11室支配の土星、3、6室支配の水星などとコンジャンクトしている。
9室は、国家の建国図においては、最高裁判所、法廷、国際法、国連、外交、条約、協定、外国との貿易・通商、観光、科学、教育、大学などを表わすハウスで、国際関係における正義、正しい行いなどを表わしている。
その太陽期にちょうど2020年6月から移行していることに注目である。
この頃から、オーストラリアは中国に反発するようになり、また中国は、飼い犬に噛まれたかのように憤慨し、オーストラリアに貿易制限を行なっている。
例えば、オーストラリア産天然ガスの輸入を減らしたり、石炭や鉄鉱石、牛肉、麦など様々な品目の輸入制限を始めている。
オーストラリアは、こうした貿易規制によって、非常に困ることになるが、中国も資源を得られなくなって結果的に困ると思われる。
中国が30年かけて築いてきたオーストラリアへの政治的意思決定への影響力が、こうして崩れ去った。
そして、オーストラリアは、この10年間に20兆円を投じて軍を近代化することに決定したようである。
こうしたこと全ては、マハダシャー太陽期が象徴している。
まさに国家としての魂の覚醒である。
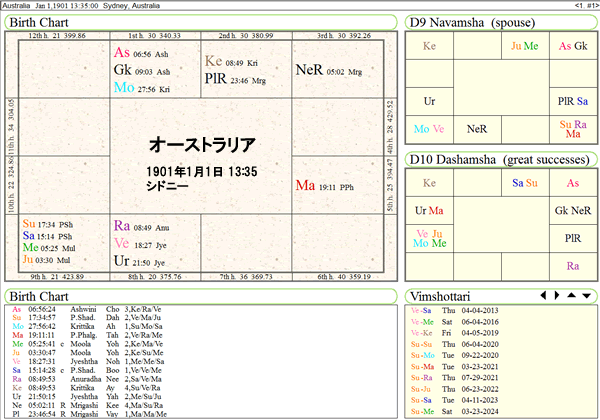
その前は、20年間、マハダシャー金星期が続いていたが、金星は、貿易相手国などを表わす7室の支配星で8室に在住し、ラーフとコンジャンクトしているが、これは貿易相手国や外交上の他国への経済的依存を表わす配置である。
そして、その前が、マハダシャーケートゥ期だが、ケートゥのディスポジターはやはり7室支配で8室に在住する金星である為、やはり同じように貿易相手国や外交上の他国への依存を表わしている。
その前は水星期で、9室に在住しているものの3、6室の支配星である。
従って、トータルすると、ケートゥ期、金星期の27年、そして、その前の水星期17年の計44年ぐらいはあまりぱっとしない国であったということが言える。
特にここ27年ぐらいは、7室の支配星が8室に在住して傷ついている所から見ると、外交的には惨めな国であったということが言える。
他国への天然資源の輸出しか経済的な手段がなければ、他国に依存することになる。
特にこの30年で、オーストラリアは中国への経済的依存を強めたというが、まさにこの7室支配で8室でラーフとコンジャンクトする金星がそれを象徴している。
8室のラーフは、人のチャートであれば、結婚願望が強くなり、常に相手の金銭に期待したり、依存したりする配置である。
然し、ラーフが減衰しているので、思ったほど、相手からは高くは買ってもらえず、経済的に惨めな思いをする。
特に天然資源の輸出国などは、相手先に安く買い叩かれる為、オーストラリアの弱い立場を象徴している。
常に天然資源の輸出国を探し、貿易相手国に期待してすり寄っていくという姿勢を意味している。
そうすると、現在は、マハダシャー太陽期になって、パンよりも魂を選び、容易に他国に買収されない精神的に強い国になっていくが、然し、太陽から見ると、6、11室支配の金星が12室に在住して、減衰するラーフとコンジャンクトしている。
これは国家としては、大きな収入の手段を失って、出費が大きくなり、ラーフが12室で減衰して悶々とする時期である。
つまり、中国から経済的な制限を受けて、苦しむことを象徴している。
日本の場合
然し、こうしたオーストラリアの惑星配置と類推して、参考になるのが、今後の日本の行方である。
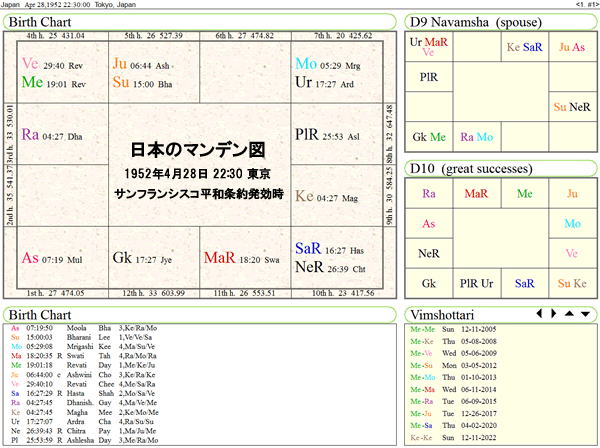
日本は、まもなく、2022年12月からマハダシャーケートゥ期に移行する。
ケートゥは9室に在住しており、ディスポジターの太陽は5室で高揚し、ラグナロードで4室支配の木星とコンジャンクトしている。
このケートゥ期において、やはり、オーストラリアと同じく、日本は経済的に非常に落ち込んでいくと考えられる。
特にナヴァムシャで12室に在住している配置などからそれが言えそうである。
然し、この頃から、日本には、昔の日本の軍国主義のような精神が復活すると考えられる。
天皇を中心とした右翼、民族主義的で、愛国主義の精神が噴出してくると考えられる。
何故なら、太陽は牡羊座で高揚しており、それは愛国主義を表わす蟹座から見た行為の10室に在住しているからである。
オーストラリアの国民が覚醒したようにパンよりも魂を選ぶようになると考えられる。
今現在、中国が覇権国として台頭して来ており、日本は、米国との同盟関係の中でもより責任ある立場を求められていると言われており、安倍晋三が、再び、改憲論者として注目を浴びているという。
例えば、日本も尖閣問題などで強い対応を取っていく必要があり、また中国の諜報機関である孔子学院などは今後、廃止していくべきである。
また中国人による日本国内の土地の購入などにも厳しく制限を課していくべきである。
そうした多少ファシズムのような気概が出て来なければ、国家を守ることは出来ない。











コメント