以前、『金融のしくみは全部ロスチャイルドが作った』安部芳裕著や、youtube上の動画『money as debt』(負債としてのお金)などを見て、銀行の信用創造の仕組みなどを初めて知った。
今日、政府が作るお金はマネー全体の5%程度に過ぎず、残りの95%のお金は誰かのローンによって作られているということを知って非常に驚いた。
誰かが銀行にローンをすると銀行はその人の預金通帳に数字を書き込むだけで、お金が生み出されるのである。
銀行は日本銀行(中央銀行)の当座預金に一定額の預金をしていれば、その何倍もの資金をローンとして貸し出すことができる。
つまり、銀行は自分が実際には持っていないお金を人に貸し付けているのである。
『money as debt』はこの銀行が自分が持っていない金を人に貸し付けて金利を取る行為を銀行家の詐欺であると告発し、いつ頃、この詐欺が始まったのかを考察している。
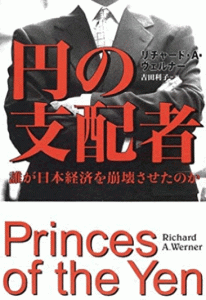










コメント
コメント一覧 (7件)
その時は戦前の取り付け騒ぎ同様の対処でしょうね。
大量に紙幣を刷りまくり、銀行やATMに配布します。
片面印刷になるかもしれません。
この後にインフレになるか否かは、受け取った国民がタンス貯金するか使用するかで決まります。
「このお金を人々が売買や交換などの経済行為を行なって、人々がいす取りゲームのように取りあうのだが、銀行が利子を取るため、流通しているお金は常に不足することになるのである。
つまり、銀行はローンで貸し付けたお金以上のお金を受け取るため市場には全ての人に行き渡るだけのお金がない為、生活していくには新たに銀行から借金をしなければならないのである。」
利子がついてお金が不足するので、現行の法定通貨はインフレするように出来ているのです。
ですから、数十年や百年で見ると、長期的には円やドル等の法定通貨は必ずインフレで価値が下落していますし、そうでないと利子が払えません。
「アベノミクスは、財政ファイナンスに近いことを行なって、財政赤字を国債の発行で賄い、買いオペで、量的緩和を行なおうとしても無駄な日銀当座預金残高を積み上げるだけで成果が上がっていない。」
財政赤字や国債発行はインフレ率・金利の許容範囲内なら無限に出来ますし、これからもずっと出来ます。
明治維新の頃に比べ、国の借金は3500万倍に増えましたから、財政赤字や国債発行は今は無問題です。
アベノミクスが失敗しているのは、日銀当座預金を社会保障や教育等の必要なことに使用してないからです。
リチャード・ヴェルナーの分析は殆ど正しいと思いますね。
現在の銀行制度や法定通貨の問題点は、利子や金利やインフレ等にあると思います。
仮想通貨なら、それらの問題が殆ど収まります。
様々な面を比較すると、法定通貨より仮想通貨の方が全体的に遥かに優れているでしょう。
唯一、仮想通貨が法定通貨に劣る点は富が偏りやすいという点です。
ビットコインは僅かの富裕層に大量の資金が偏っています。
金本位制のビットコインや仮想通貨は、価値上昇期待から富の保有者や量が偏りかねません。
一方の法定通貨は価値がインフレで減少していきますから、価値が減じる前に手放そうとして、保有者や量が仮想通貨よりかはまだ偏ってはいません。
そこで例えばリップルは、発行枚数を1000億枚にして、長期的に売却して保有者や量の偏りを是正しようとしています。
今後の仮想通貨がどうなるかは面白そうです。
> その時は戦前の取り付け騒ぎ同様の対処でしょうね。
> 大量に紙幣を刷りまくり、銀行やATMに配布します。
> 片面印刷になるかもしれません。
> この後にインフレになるか否かは、受け取った国民がタンス貯金するか使用するかで決まります。
それ程、詳しくありませんが、そういうことは戦前にありましたね。
しかし今は国家社会主義的状況であるため、緊急措置を発表したり、銀行を閉店して払い出さないなど、色々やり方はありそうです。要は国の一大事だから一度に銀行からおろさないで我慢して下さい的な対応になるかもしれません。またもし大量に刷ったとしてその紙幣を国民が即座に使おうとすれば、街にその紙幣が溢れる訳ですが、政府のお金に信用がなくなった末期的状況になった時に国民は金を即座に物に変えようとすると思います。ロシアで起こったようにルーブルよりもタバコの方が信用されるというような状況になるかもしれません。その前に国が貧しくなれば物が不足してくるため、物が不足してきたら紙幣を直ぐに物に変えようとする動きになるかと思います。
> 「このお金を人々が売買や交換などの経済行為を行なって、人々がいす取りゲームのように取りあうのだが、銀行が利子を取るため、流通しているお金は常に不足することになるのである。
>
> つまり、銀行はローンで貸し付けたお金以上のお金を受け取るため市場には全ての人に行き渡るだけのお金がない為、生活していくには新たに銀行から借金をしなければならないのである。」
> 利子がついてお金が不足するので、現行の法定通貨はインフレするように出来ているのです。
> ですから、数十年や百年で見ると、長期的には円やドル等の法定通貨は必ずインフレで価値が下落していますし、そうでないと利子が払えません。
>
> 「アベノミクスは、財政ファイナンスに近いことを行なって、財政赤字を国債の発行で賄い、買いオペで、量的緩和を行なおうとしても無駄な日銀当座預金残高を積み上げるだけで成果が上がっていない。」
> 財政赤字や国債発行はインフレ率・金利の許容範囲内なら無限に出来ますし、これからもずっと出来ます。
> 明治維新の頃に比べ、国の借金は3500万倍に増えましたから、財政赤字や国債発行は今は無問題です。
財政赤字と国債発行が無問題に見えるのは日本の場合、日本の国債を買っているのが国内の銀行や生保で、外国人が保有していないからですね。日本の老人がまだ貯金が沢山あるからです。また財政ファイナンスにおいては無限に国債を発行して未来の若者の借金として背負わせることが出来る訳ですが、ある程度の所で、政治運動や政権交代が起こったり、また未来に絶望した人々の犯罪なども増えたり、日本の国債が国債市場において値下がりすれば長期金利が上がるとか色々問題が出るのではないですか。日本の国債の価値が円のレートに影響して日本円で海外から食料や物資が輸入出来なくなります。物資が不足してくれば日本の紙幣を直ぐに物に変えようとする動きになり、銀行に人が殺到するかもしれません。
> アベノミクスが失敗しているのは、日銀当座預金を社会保障や教育等の必要なことに使用してないからです。
銀行の日銀当座預金は一応、銀行の資産なので、どう使うかは銀行の勝手ですが、国家社会主義的な独裁的な力があれば、それらを社会保障や教育を担う機関に融資させることは出来るかもしれません。しかしそれは政府に国家社会主義的な力がある時です。戦争中は重工業などに政府や軍部の指導で融資させましたが、そういう時代ではなく、市場原理に移行したため、銀行は儲かるビジネスにしかお金は融資しません。安倍政権が国家社会主義的な性質があるとしてもこの市場原理には手をつけられない、つけたくないのかもしれません。また安倍政権は福祉や教育、慈善などが嫌いです。彼が蟹座ラグナでD9が魚座ラグナであることもあると思いますが、人は競争を勝ち抜くべきだというリバタリアンの発想が、あります。成長の家や日本会議の思想もそうであり、戦争は文明の発展のために必要だと考える傾向さえあります。
だから市中銀行の日銀当座預金残高を福祉や教育に使おうという発想は出てこないと思います。
現状の枠組みでは日銀が融資を促進させるためにマイナス金利にするぐらいの発想しかありません。銀行側は当座預金に置くと手数料がかかるならセキュリティ付きの倉庫に現金を保管するかを考えるといった発想しかありません。
日銀当座預金残高を普通の一般市民に届ける方法がない訳です。
そもそも中央銀行と市中銀行を使って信用創造する仕組みは、拡大する資本主義とセットのもので、帝国主義時代のモデルです。
そのパラダイム自体が機能していないということです。
ベーシックインカムを導入することもありますが、マネーシステム自体が銀行からの負債によってマネーサプライを作るものから変わる必要がある訳です。
その変化を作り出しているのが仮想通貨だと思います。
やがて政府が仮想通貨を発行するようになると思いますが、そうするとそれは銀行に対する負債としてのお金ではなく、政府のICOによる資産のようになり、政府紙幣に限りなく近いものとなり、通貨発行権を国際銀行家から取り戻した形になるかと思います。利子という発想はなくなります。
国民に国家の成員であることの権利として、一定額の政府紙幣としての仮想通貨を支給してもいい訳です。それをほとんどコストがない形で実施出来ます。
仮想通貨はそうした可能性を秘めています。政府がもはや仮想通貨を自ら発行せざるを得ないほど盛り上がっていく必要があります。
仮想通貨の本質とは銀行家からマネーシステムを取り戻し、市民の手で、インターネットを利用して、それを運営するということです。
今後は一般の起業家が立ち上げた仮想通貨と政府による仮想通貨が共存する形になっていくと思います。
> リチャード・ヴェルナーの分析は殆ど正しいと思いますね。
> 現在の銀行制度や法定通貨の問題点は、利子や金利やインフレ等にあると思います。
> 仮想通貨なら、それらの問題が殆ど収まります。
> 様々な面を比較すると、法定通貨より仮想通貨の方が全体的に遥かに優れているでしょう。
>
> 唯一、仮想通貨が法定通貨に劣る点は富が偏りやすいという点です。
> ビットコインは僅かの富裕層に大量の資金が偏っています。
> 金本位制のビットコインや仮想通貨は、価値上昇期待から富の保有者や量が偏りかねません。
> 一方の法定通貨は価値がインフレで減少していきますから、価値が減じる前に手放そうとして、保有者や量が仮想通貨よりかはまだ偏ってはいません。
そうした問題があるので結局、政府が仮想通貨を政府紙幣として発行する流れとなるのではと思います。
そして既に価値を持ったビットコインなどの仮想通貨と共存する形になるかもしれません。そうした場合でも銀行や銀行システムとはまた別のシステムであり、政府がインターネットを利用したマネーシステムに移行するということを意味します。
その場合は市民と政府は通貨を発行する立場上、全く対等の立場になる訳です。
インフレに関しては、昔、インフレしていく紙幣をわざわざ作ろうとしたことがあったようですね。
その時の考えは、紙幣に経過した期限に応じて印を付けるという、ほとんど実現が難しいものでした。
だからインフレすることはむしろ良いぐらいのもので、それ程、問題ないという考えもあるのかもしれません。
またインフレになっても資産家は外国為替市場で、他の通貨に変えてしまうため、痛くもないかもしれません。
問題は利子であって、利子が大きいため、貯蔵されます。
> そこで例えばリップルは、発行枚数を1000億枚にして、長期的に売却して保有者や量の偏りを是正しようとしています。
> 今後の仮想通貨がどうなるかは面白そうです。
リップルは国際決済における銀行に変わるマネーシステムになろうとしていますね。但し、リップルはプライベートブロックチェーンを使うので、インターネットで誰でも参加できるという思想と異なっているのではと思います。
政府が発行する場合もプライベートブロックチェーンかもしれないですが、その場合でも銀行ネットワークとは決別して自分で運用できるようになると思います。
こうしたことを記事として書いていたら保存に失敗して一日がかりで書いたものを全て消失しました。ショックです。
ただここで刺激になったので、また新たに考えをまとめてみたいと思います。
その際のリスクは金利・インフレ率による高インフレやハイパーインフレのみです。
無論、高インフレやハイパーインフレを財政破綻の一種と定義するなら、財政破綻リスクはあります。
日本でハイパーインフレになる可能性は、生産能力・供給能力の高さから非常に低いはずですが、南海トラフ地震や首都直下地震、食糧・エネルギー危機等が原因で起きる可能性はゼロではありません。
前回の冥王星が山羊座をトランジットしていた時期はフランス革命が起きましたが、その原因の一つに寒冷化による世界的な食糧不足がありました。
同時期の日本では、天明の大飢饉という近世日本最大の飢饉が起きました。
ですから、今度の冥王星山羊座時代も同様なことがあるかもしれません。
既に2030年以降に地球は寒冷化すると一部の科学者は言ってます。
なので、2030年以降は世界中は無論、世界一ハイパーインフレリスクから遠い日本ですら危ないかもしれません。
その際には日本円も米ドルも法定通貨は紙屑で、仮想通貨の時代になるでしょう。
なるほど、政府が仮想通貨を発行する可能性もありますね。
私は政府が大富豪から財産税を取ったり、仮想通貨から財産税を取ったりすると思っていました。
仮想通貨は法定通貨にかかるインフレ税がかからない資産ですから、そのような可能性を考えたのです。
ただ、仮想通貨による世の中の大きな変化の波に乗れる人とそうでない人との経済格差が著しいものとなるでしょうから、格差是正機能を持つ税金によって、いずれは経済格差是正の動きが見られると思われます。
政府発行の仮想通貨なら、税金集めにも良いでしょうし。
法定通貨の利子と仮想通貨の金本位制的性質は通貨の滞留を招きますから、何かしらの工夫が施されると思います。
すみません、全然この内容と関係ないのですが、今ちょっと話題ニナッテイル佐藤浩市さんの鑑定を載せていただけませんでしょうか?
あんなにシブくて人気だった実力派俳優さんに何があってあのような変な発言をしてしまったのか?
はたまた本当は元々そういう素地がある方なのか?
などとても興味があります。
お忙しいかとは思いますが、お時間できらた鑑定していただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
月から見た5室に自室の木星と7、8室支配の土星が在住しています。
現在、この8室支配で5室に在住する土星に対して、土星がトランジットしている為に
判断能力に混乱が生じたと思います。
佐藤浩市がああいった発言をするからには、リベラル左翼の価値観を持っており、安倍政権が嫌いであることが推測されますが、
通常、常識的にしないような発言をしてしまうのは、判断能力に異常が生じたためだと思います。
8室支配の土星が思考、判断能力の5室に在住している為、悪意が生じたと考えられます。
知性の表示体である水星から見た5室支配の木星にも3、4室支配の土星がコンジャンクトしており、同じ象意を繰り返しています。
また月から見た2、11室支配の水星が4、9室支配の火星と星座交換しており、トランジットの木星と土星は逆行して蠍座にダブルトランジットの効果を発揮しています。
つまり2室支配で火星と星座交換する2、11室支配の水星にダブルトランジットが生じている為に攻撃的な発言として現れたと思います。
火星が逆行して月から2室にアスペクトしているような配置もあり、また2室支配の水星に木星がトランジットし、2室に土星がアスペクトしている為、2室にダブルトランジットが生じています。
2室の支配星である水星が太陽とコンジャンクトしていたり、火星と星座交換していることが発言をコントロールできないことを示しており、また5室の支配星に8室支配の土星がコンジャンクトし、そこに土星がリターンしているため、常識的に振る舞う判断能力を失う時期にいることを物語っています。
佐藤浩市
https://star7.org/?p=9513
早速ありがとうございます。
>8室支配の土星が思考、判断能力の5室に在住している為、悪意が生じたと考えられます。
そうなんですね。今まで見えていた佐藤浩市さんのイメージからは想像もつかない発言でした。
アンチ安倍さんは構わないですが、病気のことを揶揄するのはやはりどうかと思います。やはり悪意があったんですね。
8室は悪名高いらしいですが、もし8室支配の土星が、その8室にいたらどうなるんですか?
もし気が向いたらで結構です。
ありがとうございました。
8室の支配星が8室に在住している場合は8室を傷つけません。
この場合は8室が強くなり、例えば、不労所得、相続、贈与といった8室のプラス面や恩恵も受けることになります。