今日、読んでいた記事の中にマザーテレサの活動を批判する記事が載っていた。
確かにマザーテレサにも色々と欠点はあっただろうと思われるが、人物の長所や業績については過小評価して、欠点や過失をあら探ししてほじくり返し、高い評価を受けている人を落としめるこの言論は、明らかにグルチャンダラヨーガの発現ではないかと思われる。
然し、別の見方によっては、今まで聖人と考えられてきた人物にやや辛辣で合理的な観点から批判を下しているとも考えられる。
但し、その批判する観点が、ややラーフの特徴となる妄想や幻想に彩られている。
何か人間の偉大さに対する感受性が欠如した曲解、誤解があるように感じられる。
確かにマザーテレサが、頑固な人物で、晩年には自分が設立した『神の愛の宣教者会』を自ら脱退する程、我が強く、人に合わせることの出来ない個人主義的な人物であったことは知られている。
また特定のキリスト教的な信念に凝り固まっていて柔軟性に欠けていたことも事実としてあると考えられる。
然し、インドの貧しい地域に入っていって、慈善活動を行なうというのは、普通の人には出来ないことであって、そうした人間の偉大さに対する好意や想像力が欠如した安直な批判なのである。
インドで極貧の中で死にゆく人々を看取ることによって、単に食料や物資を贅沢に提供する以上の救いがあるのだろうと考えられる。
そうしたことをキリスト教のカトリックの枠組みの中で行い、多少、イエスへの献身や信仰から狂信的になることがあったとしても、それを補って有り余る程の貢献もあったはずだ。
ラーフは、今まで評価されてきた木星の価値を全く、正反対のものに貶めてしまったようである。
ラーフは5室に絡む場合、ロケットや航空機を開発するような技術的で科学的なマインドなのである。
そうしたマインドには、木星の美徳や深みについては決して理解できないと考えられる。
然し、ロケットを月に飛ばすほどの物質的な合理性であり、ある種、木星とは全く違った点で秀でている。性質が全く違うのである。
マザーテレサの施設が、衛生が行き届いておらず、イエスの受難の理想から、痛みに耐えることは尊いことだといった間違った信念に陥り、“痛みに耐える”ことを患者や貧しい人に強いたということはあったかもしれない。それは事実である。
そうした迷信じみた狂信性は確かにあったと考えられる。
このようにラーフが介在することで、木星の欠点が時には浮き彫りになってくる。
これは不思議である。
ラーフが木星に絡むと明らかにグルチャンダラヨーガである。
ラーフの手にかかると、今まで神聖視され尊敬されて来たマザーテレサが、180度、正反対のカルト的な狂信者だったということになってしまうようである。
確かにこの下の記事に書かれているマザーテレサの事実関係は本当のことだろうと思われる。マザーテレサに対する批判は理に適っている。
然し、ラーフには、マザーテレサの深さというものは全く分からないようだ。
但し、ラーフの力で、木星の狂信性やカルト性といった木星の欠点があぶりだされることもまた事実である。
先日、NHKで放映されたUFOの番組(BSプレミアム夜22:00~23:00『幻解!超常ファイル ダークサイド・ミステリー』)もそうだったが、
木星にラーフがコンジャンクションしている今現在、宗教的、道徳的なものが、否定され、貶めらえるそうした出来事が様々な分野で生じている。
これらの興味深い現象について注意深く観察するべきである。

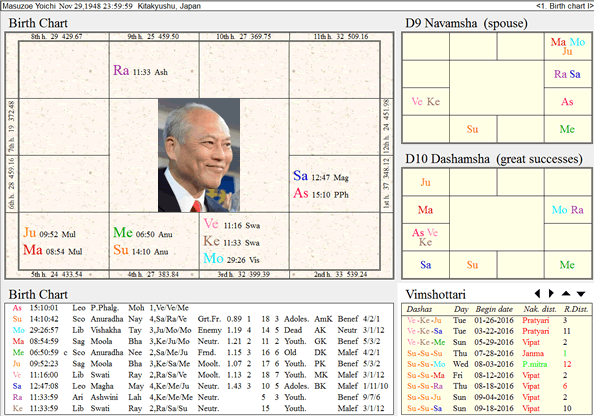

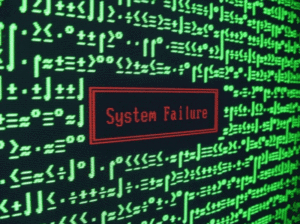






コメント
コメント一覧 (3件)
ryuchell自死の速報入ってきました。
今年は本当に凶悪事件、驚くべき事件が続きますね。
これもラーフ木星のコンビネーションによるものでしょうか?
お手空きの時に分析お願い致します。
宗教的な考え方からすると、自殺をすることは非常に良くない事で、
神から授かった自分の命は勝手に終わらせてはならず、神の計画の為に用いなければならないのです。
信仰心のある人は、通常、神への冒涜となる自殺はしません。
自殺が流行ってしまうのは、木星が世俗的なラーフによって害されて、理想が失われているからとも考えられます。
理想や希望を失った時、人は死ぬしかないと考えるのかもしれません。
木星とラーフはファナティックな(狂信的な)信仰や思想を意味しており、市川猿之助の自殺幇助罪での逮捕も、偏った思想によるものだと思います。
市川猿之助の場合、向精神薬を粉末状にして、両親に与えた上で、「袋をかぶせた」ということから、殺人を行ったことを意味しています。
自殺幇助と言えば、自殺を手伝っているようなニュアンスがありますが、実際の所は、殺している訳です。
木星とラーフのコンビネーションは、グルチャンダラヨーガで、お世話になった人々(両親)への裏切りや不敬を意味し、まさに市川猿之助の自殺幇助は、この効果だと思います。
その歪んだ思想は、ラーフ、火星、土星によって傷つけられた不安定な月がもたらしたものです。
木星の問題解決能力、木星の知恵が失われていると思います。
また最近、蟹座に火星がトランジットしていましたが、母親を殺して、その遺体の一部を食べたという恐ろしい事件が発生しました。
この事件でもフィットネスのインストラクターをやっており、会員からの人柄の評判はよい感じでした。
それが、突然、黒魔術のようなものに取り憑かれてしまったのは何故なのか、非常に疑問が沸きます。
「犯人は霊媒師になるために殺す必要があった」などと供述しています。
蟹座への火星のトランジットが、母親殺しという象意をもたらした可能性もあります。
市川猿之助の事件では、火星が蟹座をトランジットしており、母親の自殺幇助で逮捕されました。
ラーフと木星のコンビネーションは、狂信性をもたらし、精神分裂した状態や、妄想や幻覚、悪霊から憑依されたような状態まで生み出しかねない、間違った信念や理想に取り憑かれた状態を表わします。
市川猿之助は、自分の分と両親の為に近所でうなぎを3つ買うような姿も何度も目撃されており、決して、常に不敬であった訳ではないと思います。
つまり、異常で狂信的なイデオロギーや信念に取り憑かれていたと思います。
勉強になりました。
木星とラーフのコンビネーションは狂信的思想を生み出すというのは実感として分かります。
海外の動画では、前回のグルチャンダラヨーガで起きた混乱を、収束させる効果もある、と言っているのも有りますが、先生はそこはどう思われますか?
というのは、私に関するデマが粘着婆さんから流され始めたのが前回のグルチャンダラヨーガの時で、今その誤解が全て解けている段階なのですよね…
だから、私の予想だと、ラーフが牡羊座を去る11月頭までかけて、全ての人の誤解が解けるのだろうな…と、身の回りの出来事に関して感じたりしています。
(一方で、最後の墓穴を掘っていた人たちを最近まで見かけました。つまり、虚言癖のデマ婆さんに惑わされ操作されて、手下のように間違った情報を広めた人たちですね。その人たちは、その影響、風説の流布に加担した恥やマイナスの露出を、多分、次回のグルチャンダラヨーガの時まで引きずるのではないか… 等と思って周りを見ているのですが…)