
円安が進んでいるが、輸入に頼っている日本は燃料や食料(小麦など)の資源価格の高騰により、じわじわとインフレになって来ている。
専門家によれば、日本は戦後、最大の危機と考えられているが、日本ばかりでなく、世界的に考えても危機的状況にある。
先日のスリランカの財政破たんもそうだが、コロナの影響で観光収入が減り、インフラ整備の為に中国に巨額の借金をしていたスリランカは返済が出来なくなり、債務不履行(デフォルト)を宣言した。
また中国などでもコロナ封じ込めの為、上海などでは長期に渡って都市を封鎖したため、経済が悪化している。
銀行から8000億円の預金が引き出せずに人々が集まって抗議活動したり、不動産を購入した人々が不動産の建設工事が進まない為、支払いを拒否するような動きが出ている。
アメリカは金融緩和をし過ぎて、インフレが激しいため、政策金利を引き上げて、2022年6月の時点で、3.4%に引き上げている。
アメリカが急激なインフレとなったのは、コロナ下で、米連邦準備銀行(FRB)が、金融緩和をし、4兆5千億ドル(マネーの総量の40%)のお金を短期間で市場に投入した為であるという。
一方で、日銀は、政策金利を0.25%を上限としており、日米で大きな金利差が生まれて、円を売ってドルを買う動きが加速し、急激な円安となって、本日7月25日の時点で、1ドル136.39 円である。
通常は日銀は、円安を抑えるため、金利を引き上げ、日米の金利差を無くしたいが、日本は住宅ローンを変動金利で組んでいる一般市民が多いため、金利を上げると返済が出来なくなって、破産者が続出し、社会不安が増大してしまう。従って、金利を上げることが出来ない。
また日本政府は1200兆円の負債を抱えているため、金利が2%に上がるだけで、利息だけで24兆円支払わなければならなくなる。
利息を支払う為、また国債を発行すると、更に財政赤字が膨らむため、金利を上げることが出来ない。(金利を2%にすると政府は財政破たんするという)
それで、日銀は政策金利の上限を0.25%としているようだ。
海外のヘッジファンドや機関投資家は、それを知っていて、日銀がこれ以上、政策金利を上げられないことを分かっている為、日銀の打つ手はもうないと見て、円売りを仕掛けて来ている。
1992年8月にイギリス政府がポンドの価値を維持できないと考えたジョージ・ソロスは、ポンド売りを仕掛け、イングランド銀行は、ポンドを支えきれなくなって、ポンドが暴落し、ソロスは、210億ドルを稼いだが、それと同じことが今、起こっている。
現在、日銀は、海外の投機筋の円売りに対して、同額の国債を買い入れて、円安を防いでいるが、それがいつまで続くかである。
日銀はもはや海外の日本売りに対して、全て買いで対抗するしかない状況になっているという。それ以外、選択肢がないようだ。
日銀は2012年頃からアベノミクスが始まると、毎年、巨額の国債を買い入れるようになり、2014年~2018年の5年間で、毎年、50兆円買い入れたという。
また国債だけでなく、上場投資信託(ETF)なども毎年、6兆円購入し、コロナ下で、更に12兆円に増額し、現在、50兆円分の株式を保有しているという。(日銀が保有するETFは、日本国内にあるETF市場全体の8割を占めるそうである)
それで2022年6月時点で、日銀の国債保有率は、50.4%になっている。これは日本政府が発行した国債の半分を日銀が引き受けていることになる。
これは財政ファイナンスと言って、中央銀行が政府から直接、国債を引き受けると無制限に国家の借金が膨らんで、財政が悪化する為、財政法で禁止されている。
この法律を回避する為、一度、市中銀行に国債を引き受けさせるが、最終的に日銀が引き受けて、実質的に国債を日銀が直接引き受けていたに等しいという。
財政ファイナンスの禁止は、第2次世界大戦前後の日銀による国債の直接引き受けが、貨幣供給量を増やし、急激なインフレーションを引き起こした為に規定されたという。
日銀がこのまま国債を買い続けると、買いが続かなくなって、日銀が破綻するか、市中に貨幣が大量に供給されて、円が暴落して、急激なインフレ(ハイパーインフレ)になるかのいずれかになると見込まれている。
日銀が破綻すると、海外への送金が禁止されたり、預金封鎖となって、銀行からの引き出しが制限されたり、また預金に対して、税金をかけられる可能性も出てくる。
似たような話は、youtubeでもどこにでも挙げられているが、私は、2022年6月17日刊行の『オレが香港ドルを暴落させる ドル/円は150円経由200円へ!』カイル・バス著、浅井隆著を参考にした。

この本によれば、円安は更に進み、150円~200円になるというシナリオもあるという。
1ドル200円になれば、銀行預金は、実質、価値が半額になってしまう。
日本人は海外旅行も出来なければ、海外から物を輸入で仕入れられなくなってしまう。
また燃料や食料など、資源価格が高騰し、輸入で成り立っている業界は、物価高となって、国民生活への負担が増大する。
日本が戦争中に行った財政ファイナンスは、戦後にインフレで国債が紙くずになるという形で、国民が負担することになった。
然し、1929年に起きた世界恐慌に対して、高橋是清蔵相は、1932年から1935年の間、日銀に国債の直接引き受けを行わせ、積極的な財政支出政策(いわゆるケインズ政策)を実施し、昭和恐慌を乗り切ったようだ。
この時は、物価は2%の上昇に留まっており、特に問題は起こらず、歴史的には、有効な政策だったと評価されているようである。
国債が暴落もデフォルトも起こさなかったのは、日銀が直接引き受けを行ない、国債のほとんどが国内で保有されていたことで影響が限定的であり、政府と日銀が一体化していたためであったという。
従って、日銀が国債の保有高を増やしていっても問題はないとする考えもある。
結局、安倍政権が、アベノミクスで目指したのは、確信犯的に高橋是清の政策を真似して、財政ファイナンスで、経済不況を乗り切ろうとしたということかもしれない。
それが安倍元首相の「日銀は政府の子会社」という発言に現れていたかもしれない。
日銀が政府の発行した国債の50%を保有し、主要な株主が日銀である会社が多い状況は、日本は、国家社会主義に移行しているということである。
アベノミクスの2012年からの歩みは、国家社会主義の台頭という評価が出来る。
MMT理論(現代貨幣理論)では、自国通貨を発行できる政府が、自国通貨建てで国債を発行している限り、債務不履行(デフォルト)に陥ることはないとされている。
上述したように高橋是清の時は、このMMT理論がよい形で、働いたと言える。
然し、日本の軍部が戦時国債を乱発して、戦後、インフレとなって、国債が紙くずとなるといった前例もあり、また第一次世界大戦中にドイツが、戦勝国から莫大な賠償金を課せられた為、その返済に充てようとして、紙幣を大量に発行して、それでハイパーインフレとなった事例もある。
但し、それは日本の生産設備が破壊されて、生産力などが全くゼロになったからだとも言えるし、またドイツの場合は、巨額の対外債務があったからだとも言える。
日本は対外債務を抱えておらず、国債は外国人投資家が保有しておらず、日本国内で、政府の子会社である日銀自身が保有している。
つまりは、日本国民が、日本国債を支えている。
日本は財政破たんはしないかもしれないが、税金、預金封鎖などで国民に負担を求め、海外から購入する資源が割高となり、物価高(インフレ)となり、また外国通貨に対して円安になるため、海外での購買力が低下する。
日本国民は、国内だけで貧しく暮らしていくことしかできない、国内に閉じ込められた囚人のようになっていくと考えられる。
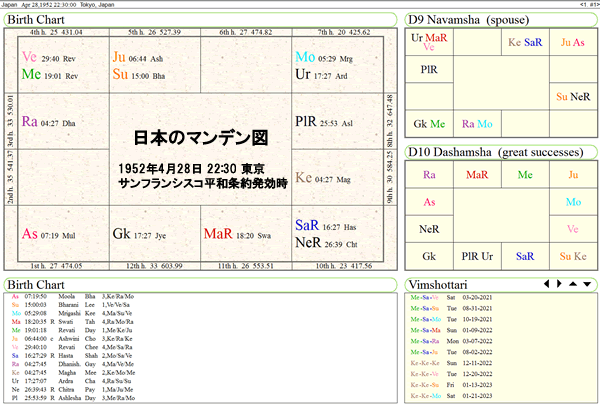
日本のマンデン図を見ると、2022年12月からケートゥ期に移行するが、ケートゥは9室に在住し、ディスポジターの太陽が5室の牡羊座バラニーで高揚して、1、4室支配の木星とコンジャンクトし、5、12室支配の火星と相互アスペクトしている。
5室でラージャヨーガを形成している。
この配置から見ると、更に国家社会主義が推し進められていくと考えられる。
自民党、日本維新の会、参政党などが票を伸ばしていくかもしれない。
ナヴァムシャを見ると、ケートゥは、8室支配の土星と共に12室に在住し、2室支配で6室で減衰する月からアスペクトを受けている。
この配置は、日本は破綻に近い状態になっていると考えられる。
然し、D1の配置を見ると、日本は国民が団結して、愛国民族主義で乗り越えて行こうといった形になるのではないかと考えられる。
経済など物質的な活動がダメになった時は、精神主義に偏らざるを得ない。
その為、武士道とか、愛国精神で、国難を乗り越えて行こうといった動きになっていくと考えられる。
然し、国家社会主義は、国民の命や権利を何とも思っていない為、国民に過大な負担を求める。
従って、国民の未来の借金である国債を無制限に発行したり、国民の預金に税金をかけて、赤字を補てんしたりできるのである。
専門家によれば、2024年とか2026年が日本の財政破たんの時期だと予測しているが、これは日本のマンデン図のマハダシャーケートゥ期への移行と完全にタイミングが一致している。
然し、ダシャーの流れを見ると、ケートゥ期は、もっと早く2022年12月から始まるのである。
その為、土星が山羊座に逆行した2022年7月13日から2022年の年末にかけて、株式市場が崩壊し、世界恐慌に突入していく動きが生じるはずである。
その時は、おそらく間違いなくやって来るのだが、それがどんな形でやって来るかはまだ見ていないだけに信じがたいが、今年中に何かが起こることは確かである。
世界的な表現では、その混乱の中で、グレートリセットが模索されることになる。
人類の歴史の中でも非常に稀有なポイントである。







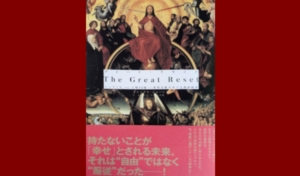


コメント
コメント一覧 (2件)
良くない象意下でも、それゆえにか結果的には現在逆の事象が起こっている株式市場の奥深さ(ひねくれ具合?)に驚いております。
果たして今後はどのような経緯をたどるのか興味深いです。
日本の投資家自身も日本株に投資しているからかもしれません。
おそらく、アメリカが2023/11/20から、ラーフ/土星期に入り、不況に入っていくことによって、その資金は一気に引き上げるのではないかと予想します。
しかし、本当に長期投資の計画を持つ投資家は、それでも引き上げないかもしれません。
他の記事でも書きましたが、日本は新興国のように安くて旨味のある国になってしまっています。