
プーチンが2月24日、ウクライナに軍事侵攻した。
侵略が目的ではなく、非軍事化が目的だと言っているが、明らかにロシア軍がウクライナ領内に侵攻している。
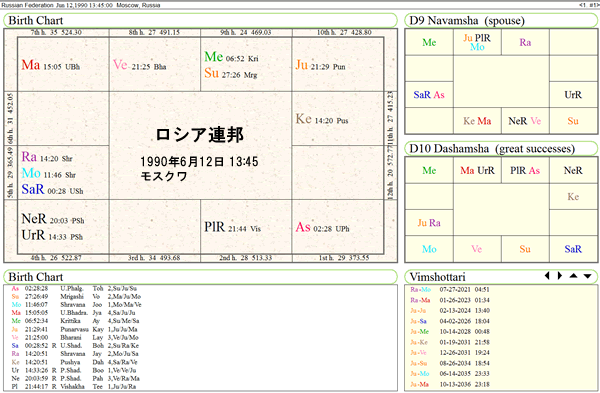
ロシアの建国図からウクライナ国境付近に軍を展開して、プーチンは何をするのかを考察してきたが、ロシアの建国図から見ると、現在、ラーフ/月期(2021/7/27~2023/1/26)で、ラーフのディスポジターである土星は6室の支配星で、11室支配の月とコンジャンクトして、6-11の絡みを生じている。
これは近隣諸国(11室)との軍事的衝突(6室)と解釈できる。
ナヴァムシャを見ると、月は戦争を意味する7室の支配星で4室(国土)に在住しているが、戦争で領土を獲得することを表している可能性がある。
3、12室支配の木星も4室に在住しており、12室の支配で4室に在住する木星は外国の土地といった象意になると考えられる。
ラーフ/月期の次は、ラーフ/火星期(2023/1/26~2024/2/13)で、火星は3、8室支配で、やはり戦争の7室に在住している。
然し、この8室支配の火星は、6室支配の土星からのアスペクトを受け、6-8の絡みを7室で生じている。
プーチンが起こしたこの戦争状態は暫く続きそうである。
次の2024年2月13日の木星期は、木星は4、7室支配で10室に在住し、4室にアスペクトバックして4室(国土)が強くなっている。
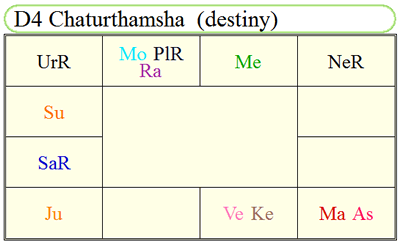
チャトゥルシャムシャ(D4)では、木星は4、7室支配で4室(国土)で定座に在住しており、ハンサヨーガを形成している。
木星は拡大傾向を表している。
ナヴァムシャでも木星は4室に在住している。
こうしたことを考えると、プーチンは外国に領土を広げる見込みが高いと思われる。
プーチンの目標は、旧ワルシャワ条約機構の復活である。
これまでのロシアの動きを考えると、2008年に南オセチア紛争(ロシア・グルジア戦争)を行なっている。
2008年8月に始まり、陸戦、航空戦、海戦の全てが行われ、グルジア領内を爆撃し、グルジア領内に侵攻して、ポティーやゴリといった都市を占領している。
停戦受け入れ後、ロシア軍はグルジア領内からの撤退を開始したが、アブハジアや南オセチアに接するグルジア領内のポティ、セナキ 、ペレヴィに「軍事中立地帯」と称して軍を残し、2008年8月26日、ロシアは国際的にはグルジア領とされている南オセチアとアブハジアの独立を承認している。
この直ぐ後の2008年10月26日からラーフ/木星期に移行していることから、これはアンタルダシャーの木星の結果、生じた効果だと推測できる。
ロシア建国図の木星期において、プーチンは、占領した地域の独立を承認して、占領ではなく、実質的に自分たちの領土の延長のようにすることに成功してきた実績がある。
その後、プーチンが行っているウクライナ東端の親ロシア派居住区域であるドネツクやクリミア半島なども全く同じ手法で、独立を承認するという形で、侵略戦争であるとの国際社会の非難をかわして、結局、その後、既成事実として認めさせている。
このことから考えると、プーチンは、木星期において、軍事侵攻によってウクライナ首脳部を排除し、その後、目的は果たしたとして、兵を撤退させると共に新ロシア派政権を樹立して、ウクライナから撤退する考えなのだと思われる。
そうした手法によって、実質的にウクライナをロシア領として、併合し、旧ワルシャワ条約機構を復活させるつもりなのである。
プーチンがラーフ/木星期にこうした作戦に成功していることを考えると、ウクライナに対する軍事侵攻も成功を収めそうに思える。
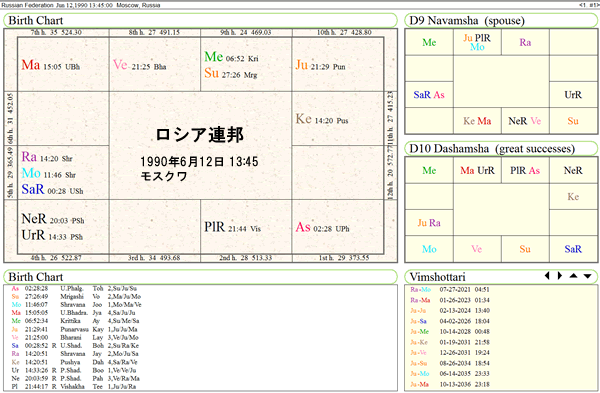
そして、以前のロシア・グルジア戦争の時に南オセチアとアブハジアの独立を勝ち取ったのと同じようにウクライナの親ロシア派政権樹立という成果を成し遂げるのかもしれない。
アメリカは弱腰で、ロシアを非難するバイデンも支持率が低く、米軍に犠牲者が出るような戦闘行為に参戦するリスクを非常に懸念しており、ウクライナの首脳部は見殺しにされる可能性が出て来たと思える。
プーチンは、ウクライナを親ロシア政権にした後、軍を撤退して、西側諸国の非難をかわし、ほとぼりが収まった頃、ドイツとの間に結んでいるロシアからの天然ガスパイプライン「ノルドストリーム2」計画を再稼働させ、安定した経済発展の道を辿り始めるとも考えられる。
プーチンは、NATOを拡大しないとの協定に応じないアメリカに非があるとして責任をかわしていく戦略である。
因みにプーチンは、エリツィン政権下で、首相に就任し、1999年夏からイスラム急進派の排除という名目の下で、チェチェン独立派勢力(チェチェン・イチケリア共和国等)に対して、ロシア軍の全面的な戦闘を行なっている。
この時は、マハダシャー火星期にちょうど入ったタイミングである。
ロシア連邦はまだ成立が新しくプーチンが政治の表舞台に登場したタイミングと建国のタイミングが一致している為、戦争の象意にはプーチンが関与している。
ロシアは、これまでにもロシア領内の分離独立派との間で、内戦を行なって来ている。
このウクライナ問題も旧ワルシャワ条約機構の同盟国であったウクライナが、NATOに加盟するという形で、分離独立運動を起こした為、ロシア側に引きとどめようとする作戦である。
これをロシアの侵略戦争と見なすか、ロシアの国内問題と見なすかは微妙な所でである。
ウクライナは立派な独立国と見なす考えもあるが、ソビエト連邦を構成した一つの国であり、ロシアにとっては旧ワルシャワ条約機構内の同盟国の一つという認識である。
これまでの何度かの内戦において、占領しては、その地域を独立させるという手法にプーチンを非難する声が上がっても、それはいつの間にか消えてなくなり、既成事実として受け入れられていく傾向にある。
然し、私が先日、プーチンのチャートを改めて検討した所、チャラダシャーのロジックなどによれば、プーチンは、2024年で失脚、あるいは引退するはずである。
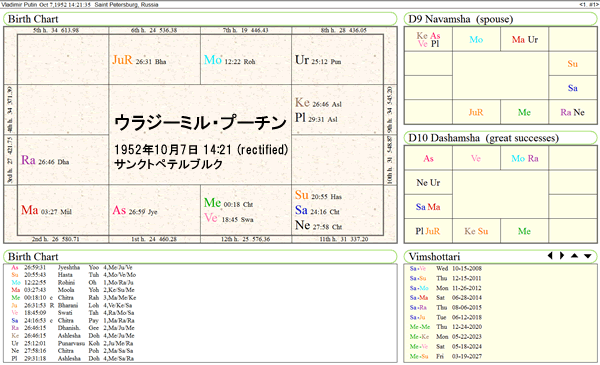
プーチン個人のチャートによれば、現在、マハダシャー水星期に移行している。
時刻修正が正しければ、水星は、ナヴァムシャやダシャムシャで8室に在住しており、物事の中断、行き詰まりを表している。
水星は、出生図や他の8つの分割図で、同じ天秤座に在住して、ヴァルゴッタマの強い水星である。
天秤座は、駆け引きが得意な為、今回の軍事作戦のように侵略ではなく、新ロシア派住民の保護や非武装化という名目など、国際社会がギリギリ許容できるラインを狙って、微妙な駆け引きを行なっている。
出生図では、水星は8、11室支配で、11室の支配星が12室に在住している為、プーチンは自分の国際社会での評価や利得を失うかもしれない。
但し、8室の支配星が12室に在住して、ヴィーパリータラージャヨーガを形成している為、自分を悩ませる相手や支配する相手には悩まされずに済むかもしれない。
プーチンの8、11室支配の水星は、ヴィーパリータラージャヨーガを形成し、2、5室支配の木星、7室支配の金星と形成する5-7のラージャヨーガに含まれ、また木星との間で、2-11、5-11のダナヨーガを形成している。
従って、引退した後も特に何事もなく、背後で暗躍し続けると考えられる。
私はこれまでロシアの建国図において、木星期が何を表わすのか分からないでいたが、上記のように考えて見ると、やはり、ロシアが広大に国土を広げるようにしか思えない。
然し、そうしたプーチンもやがて引退し、その後は、ドイツとの天然ガスパイプライン「ノルドストリーム2」なども稼働し初め、ヨーロッパ経済圏の一部となっていくのである。
プーチンの戦争行為は、愛国民族主義者の最後のあがきであると言える。
西側諸国がダボス会議を通じて進めるグレートリセット、あるいは、新世界秩序に組み込まれていくことを回避して、プーチンは、ロシアが、優しい全体主義の国家として、自主独立し、生存し続けられるかどうかの最後の抵抗を行なっているのである。











コメント
コメント一覧 (6件)
プーチンは目上に恵まれても、後継者には恵まれないという宿命を背負っているようで(午未空亡)実際メドヴェージェフ大統領のあと、再び自分が大統領に戻ったり
末代運というか、それまでの流れを最後にまとめる役割があり、次代からは異質な流れとなるようです
プーチンの西側諸国に対する奮闘もプーチン一代で終わり、
西側の自由主義諸国の秩序に組み込まれていくイメージしかありません。
武官のような晩年、死に方という出方ですが、三島由紀夫はそこまで強くはなかったので、自らの切腹という範囲にとどまった
プーチンも愛国主義が晩年になるほど高くなる
秀吉さんが何度か言及されているグレートリセットと重ねて考えると、
プーチンの晩年の最後の役割は、グレートリセットにスムーズに移行するために、世界に印象づける愛国主義の独裁者なのかと思えてきます
そうなると、中国も同じ役割なのかと感じ、習近平の方も確認したところ、やはりプーチンと同じでした(北の偏官)
よく似ていると思います。
確かにプーチンの今回のウクライナ侵攻が反面教師となって、主権国家の問題点が明らかになり、世界政府、グレートリセットといったものに移行していく一つの流れを作り出す可能性はあります。
私はプーチンのナヴァムシャが魚座ラグナであるなら、それこそが、プーチンの本質だと思います。
やはり、古い魚座-蠍座-蟹座の水の星座の封建的、伝統的な価値の保存や存続を望む古い人物だということです。
プーチンには、巨大で強かったソビエト連邦の時代への郷愁があり、それが旧ワルシャワ条約機構の復活という形で現れたのかもしれません。
プーチンは西側の新自由主義の流れに飲み込まれるのをオルガリヒの排除など独裁者としての英断で防ぎ、ロシアの愛国民族主義者で、英雄でしたが、時代は移り変わり、インターネットが普及し、Netflixやfacebook、twitterなど、米国のシリコンバレーで生み出されるような新しい文化によって、世界がどんどん変化していく流れに逆行することは出来ず、世界政府、グレートリセットへの流れを食い止めて、時間稼ぎをすることは出来ても根本的にはその流れを変えることは出来なかったということではないかと思います。
ウクライナも結局、西側諸国のそうした文化的魅力になびいて、ロシアから離れてゆき、それは民衆が選んだことで、防ぎようがないことでした。
そして、徐々にNATO加盟国が増えて、西側が拡大し、劣勢になっている面はあったかもしれません。
然し、ロシアがSWIFTを使って、資源を外国に売って、国民が外貨を稼いでいたことから考えると、既に負けていたといっていいかもしれません。
ソ連崩壊後に西側のシステムに完全に組み込まれるのを食い止めて来たとしても、あくまでもそれは抵抗に過ぎず、根本的にはその流れには逆らうことは出来なかったと思います。
プーチンの人生の物語とは、そうした抵抗の物語だったかもしれません。
つまり、長い目でみれば、勝てない戦いをしているということです。
プーチンがナヴァムシャで、魚座ラグナであれば、6室支配の太陽が5室で蟹座に在住し、かなり偏見の強い愛国右翼思想を表しており、非常に納得できます。
キューバ危機と同じですね。
もう少しで核戦争だったらしい。
今回は火星の位置が怖いです。
ラーフ/ケートゥ軸が、3月17日から牡羊座/天秤座軸に移動しますが、そうすると、ケンドラサンバンダ(ケンドラ関係)で、ラーフやケートゥの影響が土星や火星の影響に加わります。
4月4日-5日辺りは、火星は、28°付近の土星にピンポイントで、コンジャンクトします。
その後、4月29日辺りから土星は、水瓶座に移動し、水瓶座は国連など各国の連帯を表わし、集団の力を表わす為、戦争を止める為の国際的な連帯の力が強くなると思います。
この頃までには戦闘が終結し、国連の名の下で、停戦監視団などが派遣されるかもしれません。
キューバ危機の時は、土星が山羊座をトランジットし、ケートゥも山羊座をトランジットし、火星は水瓶座でした。
キューバ危機の時には、新月図に土星と火星のコンジャンクとは見られなかった為か、核戦争の緊張は高まりましたが、実際の重火器による戦闘は行なわれませんでした。
結局、交渉で、アメリカがトルコにあるミサイル基地を撤去することを条件にキューバからミサイルを引き上げることで、話がまとまりました。
今回は、これだけ激しい戦争となったのは、土星の影響に火星の影響が加わっているからだと思います。
更に土星は山羊座を抜けてゆく、最後の方の度数(現在、25°付近)を通過しており、これが2020年との違いです。
土星は星座を抜けてゆくタイミングで、力を発揮します。
従って、土星が山羊座を抜けてゆくタイミングで、しかも火星の影響が加わったタイミングで、侵略戦争が起こりました。
火星は、これから土星の度数に徐々に近づいていく為、戦闘はまだこれから激しくなっていくと予想されます。