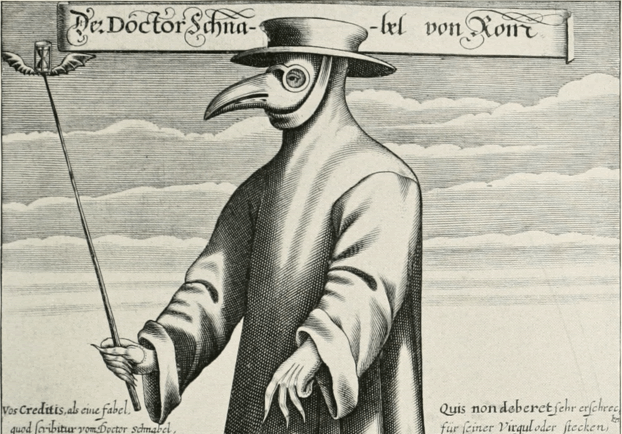
現在の新型コロナウィルスの感染拡大は、中世のペスト(黒死病)の流行に比較されるが、実際、ペストはどんな惑星配置下で起こったのか、調べると色々、興味深い結果が得られた。
調べたきっかけは、一般財団法人 海外邦人医療基金のニュースレターの中に『感染症ノスタルジア(4)「文明を進化させてしまう魔力...ペスト」』という記事を見つけたからである。そこから非常に重要な情報が得られた。
以下にその一部を引用抜粋する。
|
感染症ノスタルジア(4)「文明を進化させてしまう魔力...ペスト」 NL03020102 感染症、ペスト 海外勤務健康管理センター 濱田 篤郎 1.「ハーメルンの笛吹き男」の恐ろしさ 13世紀末、ドイツ北部の町ハーメルンの住民達はネズミの大量発生に悩まされていた。そこに、ある男が現れ「ネズミを駆除しょう」と申し出る。住民達は喜んでその男にネズミ駆除を依頼した。男が持っていた笛を吹くと、不思議なことに町中のネズミが路上に現れ、行進を始めたのである。やがてネズミ達は近くの小川に次々と飛び込んでいった。これがグリム童話で有名な「ハーメルンの笛吹き男」である。 実は、この童話には恐ろしい続編がある。ネズミを駆除してから、笛吹き男は町の住民に約束の報酬を要求した。ところが、住民達はその約束を反故にしてしまった。男は怒りに震えながら再び笛を吹き始める。すると今度は、町中の子供達が隊列を作り、行進をはじめたのである。そして子供達はどこか遠いところに消えていった。 グリム童話はドイツの古い民話が土台になっているが、実際にハーメルンの町で、1284年に130名の子供が消えたとする記録が残っている。そこで、この民話は何らかの史実が語り継がれたものと推測されている。 それでは、なぜ子供達は集団で失踪したのだろうか。 その理由の一つに、ペストにより子供達が集団死したとの見方がある。ペストはネズミと密接に関連する病気である。ネズミを駆除したという最初のストーリーは、ペストを暗示させるものだ。 また、この事件がおこってから60年後の1340年代に、ヨーロッパ全域は中世の黒死病流行と呼ばれる、空前のペスト大流行に見舞われている。その少し前からペストが燻っていても不思議はないのである。 いずれにしても、ペストは人間社会が形成されてから大流行を繰り返してきた。その恐怖は人々の記憶に深く刻まれ、各地の民話や風俗にはペストの流行に関連するものが数多く残されている。 2.繰り返す悲劇 有史以来、ペストの世界的な大流行は4回記録されている。 最初の大流行は6世紀のことで、東ローマ帝国のユスチアヌス帝が大ローマ復活をかけて、侵略戦争を繰り広げている最中の出来事だった。流行の極期に首都のコンスタンチノーブル(現イスタンブール)では、日に1万人近い人々が死亡したと記録されている。 そして2回目の大流行が、1340年代に始まる中世の黒死病の流行である。この時は全世界で7000万人の命が失われる大惨事となった。 3回目はロンドン大疫病とよばれる17世紀の流行で、この模様はダニエル・デフォーの「ペスト年代記」の中で詳細に述べられている。 (略) |
グリム童話で有名な「ハーメルンの笛吹男」という話があるが、13世紀末にドイツ北部の町ハーメルンでネズミの大量発生に悩まされていた時にある男が現れて「ネズミを駆除しよう」と申し出て、男が笛を吹くと、ネズミが行進を始めて、近くの小川に次々と飛び込んでいったという話である。
町の住民たちが、男に報酬を支払わなかったので、男が怒って、笛を吹くと、町中の子供たちが行進をはじめて、遠いところに消えて行ったという恐ろしい結末である。

最近、グリム童話の本当の怖さについて語る書籍などが出ているが、そうした中で論じられているかもしれない話である。
実際にハーメルンの町で、1284年に130名の子供が消えたとする記録が残っているそうだ。
それで、このハーメルンの笛吹男の民話は、何らかの史実が語り継がれたものと推測され、その一つの見方として、子供たちが集団でペストに感染したのではないかというのである。
この130名の子供たちが消えたとする1284年のトランジットを調べると以下のような惑星配置である。
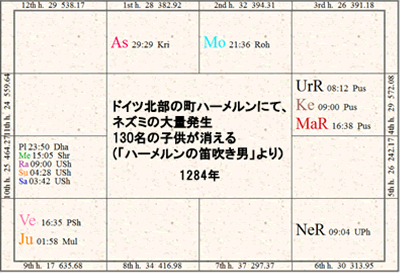
土星が山羊座をトランジットし、ラーフ/ケートゥ軸も蟹座と山羊座の軸にあり、木星がまもなく山羊座に入室していくタイミングである。
山羊座への土星と木星、ラーフ/ケートゥ軸などのトランジットは、『信用収縮・食糧危機の占星学 - トレンド転換のクリティカルポイント -』の中で、徹底的に調べたが、やはり、ねずみが大量発生したとされるこの時期に土星や木星、ラーフ/ケートゥ軸などが山羊座にトランジットしていたのである。
現在、アフリカでバッタが大量発生して、それが中国に迫り、食糧危機が引き起こされようとしているが、そうした天変地異の一つとして、当時、ねずみが大量発生し、ペストも大流行したのではないかと思うのである。
そのため、子供たちがペストに感染して集団死したのではないかとする説は、確かに可能性としてあり得る話である。
但し、この「ハーメルンの笛吹男」は、それ以上の興味をそそられる話である。
13世紀の中世といえば、まだルネッサンスが始まる前の暗黒時代で、魔術的な世界観で、人々が生きていた時代であり、また実際に魔術も存在したと考えられる。
例えば、聖書の中でも「ガダラの豚」という逸話がある。
悪霊がイエスに豚の群れに活かせてもらう許可を願い、イエスが許可を与えると、豚の群れが湖に飛び込んで溺れ死んだという話である。
|
ゲルゲサ ゲルゲサ(Gergesa, Country of the Gergesenes)とは新約聖書に登場する地名で、ガリラヤ湖南東に広がる広大な地域を指していると考えられている。中澤啓介はケルサと呼ばれている場所であると推定している。この地方にはガダラやゲラサなど、ギリシャ人の住む植民都市が散在していた。たとえばガダラはマタイの福音書とマルコの福音書に登場するデカポリスの町の一つであり、ガリラヤ湖東岸の切り立った断崖の湖に突き出ている場所であった。 ゲルゲサは、「ガダラの豚」の逸話で有名である(ルカの福音書ではゲラサ人となっているなど、舞台についてはガダラ、ゲラサ、ゲルゲサの三つが併存している)。マタイの福音書によると、主イエスがガリラヤ湖の向こう岸に行くことを提案し、舟でガリラヤ湖を横断し、ガダラ人の地についた。その地の墓場に、レギオンという悪霊に憑かれて凶暴になった人がすんでいた。悪霊はイエス・キリストを神の子として認めて、底知れぬところに行くように命じないように懇願した。そこで、悪霊が豚の群に行かせてもらう許可を願った。イエスが許可したので、悪霊は豚の群れに移り、豚の群れはがけを下って、ガリラヤ湖で溺れ死んだ。この事件がガダラ人の地に広まりイエスは、ガダラ人の地から追い出された。 (wikipedia ゲルゲサより引用抜粋) |
こうした話を読むと、自然界の諸力(ディーバ・エレメンタル)を操作できる人は、豚やネズミを川に突進させたりできるのではないかと思うのである。
以前、日本の江戸時代の田沼意次の時代を調べたが、冥王星や木星が山羊座をトランジットして、土星が逆行して、蟹座から山羊座にアスペクトする配置であった。
この田沼時代に飢饉が起こり、食糧難や疫病が生じたのであるが、明和の大火・浅間山の大噴火などの災害の勃発など、自然災害も頻発している。
地震、火山の噴火、火災、ネズミやバッタの大量発生などの天変地異とは、やはり、自然界の諸力(ディーバ・エレメンタル)の乱れから起こっていると考えられ、その深い原因は、現代科学では解明できないのである。
神智学や秘教では、こうした自然界の諸力の乱れは、人間の考え方や生き方が間違っている為に起こると考えられている。
つまり、思考、感情、行為のレベルで、否定的なものが蓄積されると、自然界の諸力が、それらを浄化する天変地異が起こるというのである。
「ハーメルンの笛吹男」の話は、中世の暗黒時代において、オカルト的な力を駆使して、自然界の諸力を扱える魔術師たちがいたのではないかと思うのである。
そして、惑星が山羊座を通過するような危機の時に暗躍したと考えることも出来る。
1340年代の欧州でのペスト大流行
そして、ハーメルンの町から子供たちが消えた1284年の60年後にヨーロッパ全域でペストの大流行が起こっている。
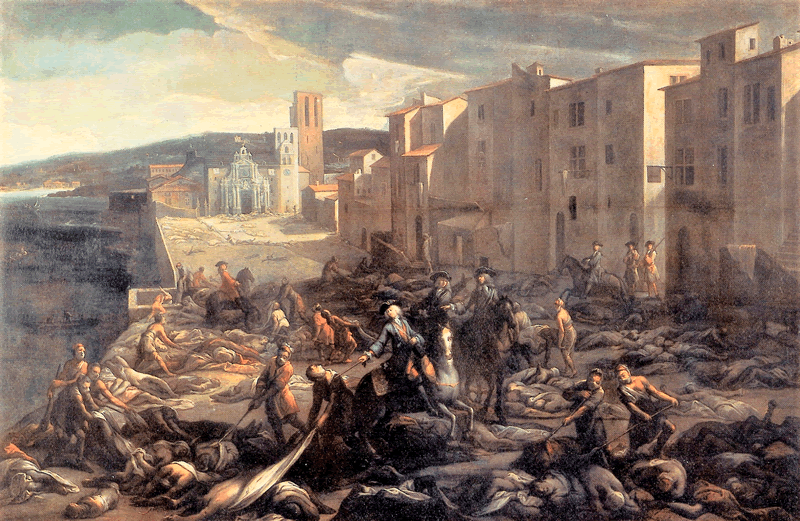
wikipediaによれば、当時の世界人口4億5000万人の22%にあたる1億人が死亡したと推計されており、イングランドやイタリアでは人口の8割が死亡し、全滅した街や村もあったという。
1284年の60年後のチャートを作成してみると、やはり、土星が山羊座をトランジットしており、木星も山羊座に入室する直前である。
そして、海王星も山羊座を通過している。

このペストの流行後に人びとの考えや社会制度に変化が生じ、欧州の労働者の生活は一変したのだという。
それは非常に納得できるのであるが、参考記事として、東洋経済ONLINEの記事『「黒死病」流行後に欧州の労働者が経験したこと 食事、賃金、宗教、慈善活動はどう変わったか」』(文末に参考文献として引用)が興味深い。
それによれば、「多数の人が亡くなったあとの西欧では、実質賃金が2~3倍に跳ね上がり、労働者が肉とビールの夕食をとるようになる一方で、地主は体面を保つのに必死だった」そうである。
山羊座を通過した後、土星は、水瓶座に入室していく為、大規模な福祉政策が行なわれたり、色々社会の状況が変わってくるということである。
つまり、ペストというのは社会がよく変化していくための一つのきっかけであったことがよく分かる。
17世紀のロンドン大疫病
その後、17世紀にロンドン大疫病とよばれるペストの流行があったようである。
ロンドン大疫病は、1665年~1666年に起こっている。
wikipediaによれば、18か月で推定100,000人(ロンドンの人口のほぼ4分の1)を死亡させたという。
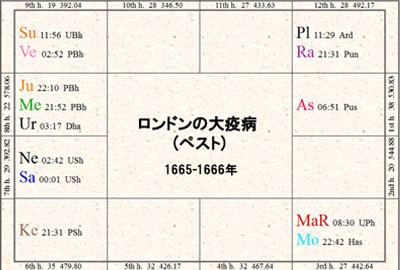
この時もやはり土星が山羊座を通過して、海王星も山羊座を通過している。
1666年3月から土星が山羊座に入室していくのだが、木星が水瓶座を通過しているので、その前年度には山羊座を通過していたということである。
ラーフ/ケートゥ軸も射手座/双子座軸の半ばである為、その前年度には、ラーフ/ケートゥ軸も山羊座/蟹座軸をトランジットしていた。
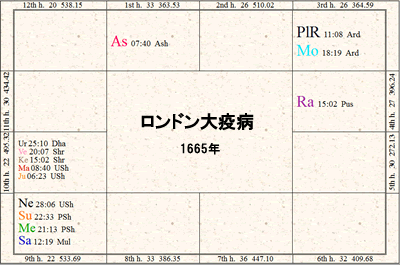
1665年1月の時点で、木星とラーフ/ケートゥ軸が山羊座をトランジットしていることが確認できる。
ローマ帝国を崩壊させたアントニヌスの疫病
今度は時代を遡ると、西暦165年に「アントニヌスの疫病」と言われるものが発生している。
天然痘ともペストとも言われており、少なくとも350万人が死亡したという。
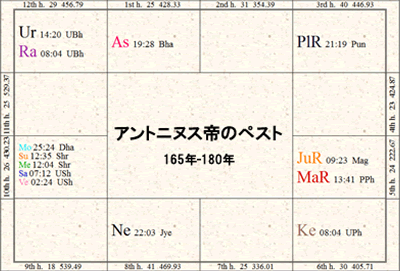
やはり、この時、土星が山羊座をトランジットしている。
因みにローマ帝国は、キリスト教徒の迫害で知られているが、その迫害は、皇帝ネロ(在位54-68)の時代に始まり、161年に即位したマルクス・アウレリウス・アントニヌスの時代に迫害は更に強化されたようである。
その中で発生したのが、「アントニヌスの疫病」である。
キリスト教徒は野獣の餌にされ、拷問を受け、監禁され、凄まじい暴力を受けたという。
因みに法輪功の人々は、新型コロナウィルスが、中国の武漢で発生したのは、中国政府の法輪功への迫害が原因だと考えているようである。
そうした見解が、法輪功の広告媒体である大紀元というサイトで述べられている。
確かに新型コロナウィルスは、最も暴力的で、他国に害を行なっている中国と米国で起こっていることは注目に値する。
イタリアでも流行が激しく死亡率も高かったが、このローマ時代の負債をいまだに支払っていると考えられなくもない。
日本でそれ程、流行が少なく、死亡率が圧倒的に低いことが世界から不思議がられているが、何もたいして効果的な対策をする訳でもなく、運がいいだけだと評価されてもいる。
これは日本は、第二次世界大戦で、大東亜共栄圏といった思想を打ち出して、そのつけは支払ったものの、基本的に民族の本性として、それ程、暴力的ではなく、カルマ的な負債を背負っていないからだとも考えられなくもない。
間違った思考、感情、行為が、自然界の諸力(ディーバ・エレメンタル)の乱れを招き、浄化作用を被ると考えれば、これも理解できる。
民族のカルマというものが、国家の建設を行なう特定のタイミングにおいて、国家のマンデン図の中に織り込まれるのかもしれない。
だから、中国や米国のマンデン図において、水星とラーフ/ケートゥ軸の絡みが強調されるダシャーの時期にウィルスの流行が起こったのである。
国家のマンデン図の中に織り込み済みの民族(国民)のカルマが、噴出したと考えることが出来る。
そのように考えると、木星が減衰する山羊座とは、カルマが噴出する星座であるとも考えることが出来る。
過去のカルマ的負債を清算するタイミングとして、天変地異、食糧危機、疫病などが起こり、そのことが最悪の状況を作り出すと共に未来に向けて社会を改革する大きなチャンスともなる。
そういうことではないかと思われる。例えば、戦争であっても、それは一つの浄化作用である。
アリスベイリーの著作によれば、第二次世界大戦の原因は、世界で貧富の格差、階級の固定化が生じた為、それを破壊する為にシャンバラから破壊のフォースが解き放たれたという解説なのである。ヒトラーとか、ムッソリーニとか、それを迎え撃つ、ルーズベルトやチャーチルも、その媒体となるプレーヤーに過ぎないのである。
ユスティニアヌスのペスト
アントニヌスの疫病の後、6世紀のユスティニアヌス帝の時代に「ユスティニアヌスのペスト」と呼ばれるペストの流行が起こっている。
これは、wikipediaによれば、541年~542年もしくは542年~543年にかけて起こったとされており、ローマ帝国の全人口の40%が死亡し、コンスタンチノープル市内では、毎日1万人が死んだという。
「流行の最盛期には毎日5,000人から10,000人もの死亡者が出て、製粉所とパン屋が農業生産の不振により操業停止に陥った」というが、コロナが流行する現在の状況と非常に似通っている。
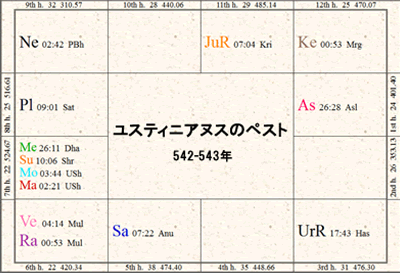
但し、この時のトランジットを見ると、土星や木星は山羊座にはトランジットしていないが、木星と土星のアスペクトがあるため、山羊座にはダブルトランジットが形成されている。
また540年ぐらいには、ラーフ/ケートゥ軸が山羊座と蟹座の軸にあったと思われる。
過去に3回起こったペストの大流行
「wikipedia ペスト」によれば、ペストは過去3回に渡って世界的流行が生じており、第1次が6世紀の「ユスティニアヌスのペスト」で、第2次が14世紀(1340年代)のヨーロッパでのペスト大流行で、第3次は、19世紀末に中国で起こったものだという。
然し、上述したようにそれ以外にもペストは様々な時期に流行している。
19世紀末のペストの流行
この19世紀末の中国で起こったものが分かりにくいが、1855年に雲南省で腺ペストが流行っている。
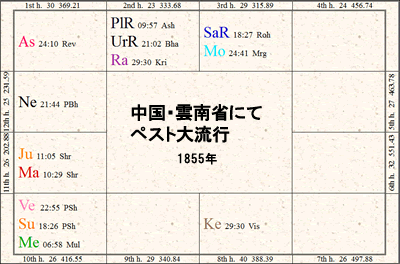
この時、木星が山羊座をトランジットして、牡牛座で逆行しているので、山羊座にダブルトランジットが生じている。
1894年にも香港で大流行が起こっているが、この時は、土星は天秤座、木星は牡羊座をトランジットして、特に山羊座にはダブルトランジットは生じていない。
その他のペストの流行
また他にも小規模に起こっているペストの流行の時期を調べてみたが、必ずしも山羊座に木星と土星がトランジットしていない場合も多い。
従って、必ずしもペストが起こった時は、山羊座が関係しているとは言えないが、少なくとも過去の大きなペストの流行時は、山羊座に木星、土星、ラーフ/ケートゥ軸などが絡んだタイミングで起こっていることが確認できる。
ロンドン大疫病(1665~1666年)の後、1720年にフランスのマルセイユで、ペストが大流行しているが、この時は、土星は山羊座で、木星は乙女座をトランジットし、山羊座にダブルトランジットが生じている。
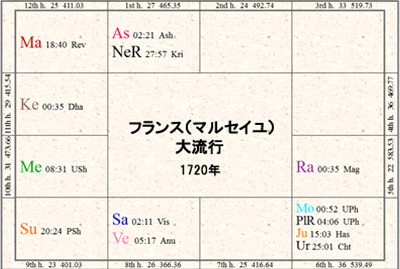
また1994年にインドでペストが発生した時のチャートも出してみたが、トランジットの土星は水瓶座を通過していた。
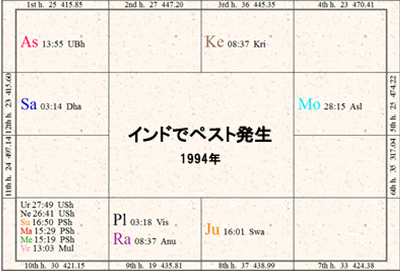
その前年の1993年のトランジットでは、山羊座を土星が通過し、木星が乙女座から山羊座にアスペクトして、山羊座にダブルトランジットが生じている。
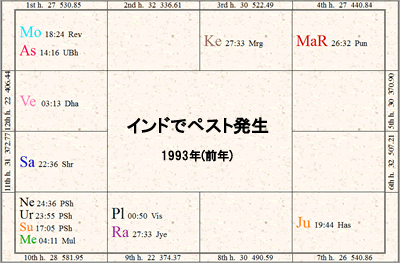
1994年として記録されているが、おそらくその前年の1993年から感染が拡大していたと考えられる。
14世紀に欧州でペストが流行した時、人々のモラルが低下した
冒頭で紹介した一般財団法人 海外邦人医療基金のニュースレターの記事『感染症ノスタルジア(4)「文明を進化させてしまう魔力...ペスト」』を再び引用すると、1348年頃、ペストが流行した欧州の当時の様子がよく分かる。
|
5.早すぎた埋葬 イタリアの諸都市に悪魔が到達したのは1348年のことである。 当時のナポリには、ルネッサンスの幕引き役となる作家のボッカチオが滞在していた。彼は周囲の人々が次々と死んでゆく事態に恐怖し、故郷のフィレンツエに帰着する。しかし、そこも地獄の様相を呈していた。当時、12万人程の人口があったこの町で、1348年7月までに生存できたのは僅かに2万人だったのである。 この死臭が充満する町で、ボッカチオは代表作の「デカメロン」を執筆する。それは、ペストに脅えて郊外に逃避した男女10人が語る好色艶笑譚であった。この男女のように、極限の恐怖状態のため、快楽と官能的な喜びに溺れる者も少なくなかった。 ボッカチオはこの物語の冒頭で、人々が動揺し道徳が崩壊していく様をルポタージュ式に述べている。 「姉妹は兄弟をすて、またしばしば妻は夫をすてるにいたり、また父や母は子供たちを、まるで自分のものではないように、訪問したり面倒をみたりすることをさけました」 患者に近づくと感染するという経験から、家族は看病をやめて患者を放置するようになったのである。放置された患者は孤独の中で悶え苦しみ、そして息をひきとる。死体は門前に棄てられ、それを死体運搬人が回収するのであった。葬式が行われても、それは笑い声に満ちた馬鹿騒ぎの場と化していた。 さらに恐ろしいことには、瀕死の患者も死体として処理されたのである。死者が膨大な数になると従来の墓場では足りなくなり、町の郊外に大きな穴を堀り、そこに死体を投げ込んでいた。この穴の中に、まだ息をしている瀕死の患者も数多く埋められていたのである。患者に近づきたくないために、死を判断することすら躊躇われたのだろう。墓場に生き埋めにされた患者は、多くの死体に囲まれながら昇天するのだった。 ポーの怪奇小説「早すぎた埋葬」を彷彿とさせる情景である。 |
この記事で「デカメロン」を読んでみたいと思ったが、あまりにも死が日常になると、人々の感受性がおかしくなっていくようである。
ペストと山羊座の関係
このように見て来て、明らかにペストと山羊座は関係があることが分かる。
『信用収縮・食糧危機の占星学 - トレンド転換のクリティカルポイント -』の中でも書いたが、山羊座に木星や土星、ラーフ/ケートゥ軸がトランジットすると、大規模な信用収縮、食糧危機、疫病、天変地異(自然災害等)が生じる。
そして、それは人間社会に積み重なったカルマ的負債を清算するようなタイミングであるかもしれないということである。
9室はダルマハウスであるが、10室はカルマのハウスである。
従って、山羊座はカルマの星座であり、カルマの意味とは、自分で播いた種を刈り取るということである。
自分で作ってしまった原因を取り除く為に猛烈な働き(仕事)を為さなければならない。
それによって、社会は新たに前進するため、ピンチとチャンスが同時にやってくるような機会である。
危機を経験しつつ、その危機を解消し、乗り越えていく活動によって、社会が進化、発展、改善していく重要なタイミングであるということである。
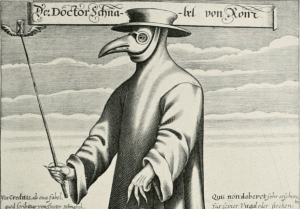
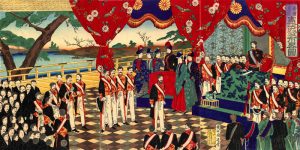







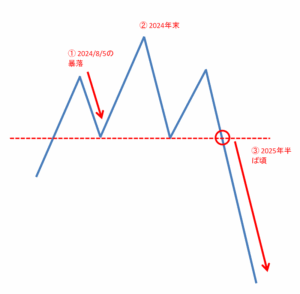

コメント