
先日、『信用収縮・食糧危機の占星学 - トレンド転換のクリティカルポイント -』の中で、過去の株式市場大暴落や食糧危機と、山羊座への木星や土星、ラーフ/ケートゥ軸などのトランジットの関連性について調べたが、1991年3月のバブル崩壊、そして、2008年12月のリーマンショックなどが山羊座に関係していることを見た。
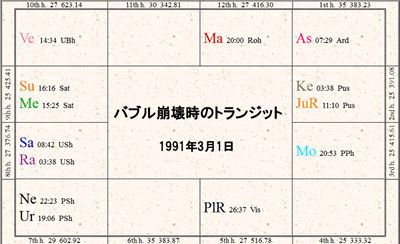
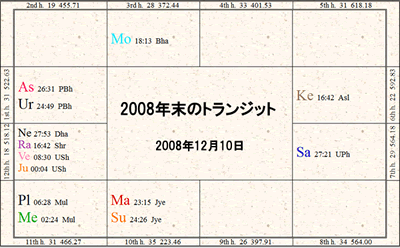
そして、一点、確認するのを忘れていたのが、1997年7月のアジア通貨危機である。
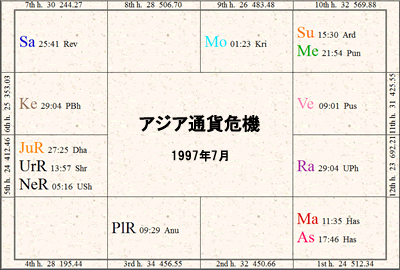
この時も調べて見ると、やはり、山羊座に木星がトランジットしていた。
また天王星や海王星も山羊座を通過していた。
山羊座では何かしらの経済危機が起こるのはもはや間違いなく明らかなことである。
射手座では、人々は楽観主義に支配され、経済活動、株式市場は過熱し、株価は天井に達するのだが、惑星が山羊座に入室した途端に株式市場は暴落し、危機が訪れる。
その危機の解決の為に山羊座は猛烈に奔走しなければならない。
そして、惑星は水瓶座に移動して、改革が行われて、幅広い公的な救済が行なわれる。
この射手座⇒山羊座⇒水瓶座の流れは、人間界のお決まりの学習コースと言えるかもしれない。
このアジア通貨危機は、ヘッジファンドが空売りを仕掛けて始まったというが、タイ、インドネシア、韓国は経済に大打撃を受け、IMFの管理下に入った。
IMF・世界銀行体制という言葉があるが、IMFとは国際連合の専門機関であるが、本部はワシントンD.C.にある戦勝国であるアメリカの出先機関であり、IMFからお金を借りるとは、アメリカのウォール街の金融資本家の支配下に入ることを意味している。
一旦、IMFの融資を受けると、当該国の政府は、緊縮政策を命じられる。
そして、IMFの勧告の元、増税や政府支出削減、民営化、経済自由化、通貨切り下げなど構造調整プログラムといったものが課される。
旧約聖書の「借りる者は、貸す者の奴隷となるー」の警句の通りである。
このアジア通貨危機の時、中国は、国内全体の預金がほとんど国内口座にあり厳しい規制が敷かれていた為、ほとんど影響を受けなかったようである。
中国は、海外からの資本と国内資本の自由な移動が規制されており、また中国の株式市場は、暴落が起こるや否や直ぐに取引停止にすることが出来る。
そのような民主主義のない、独裁国家である。
従って、アメリカが主導する資本主義の仕組みに完全に依存しないでいた為にIMFの支配下に入ることはなかった。
アメリカは民主主義の国で、自由の国と呼ばれ、ヘッジファンドも米国政府も、独立してそれぞれが自分たちの利益を目指して、独自に行動しているように見えて、国家戦略的に連携して、自国民の国益を推進している。
ヘッジファンドが、アジア各国の通貨を暴落させて、その後、IMFがそれらの国を借金漬けにして、支配するという見事な連携プレーなのである。
そのアメリカの仕組みに組み入れられず、アメリカの見事な連携プレーに影響されずに来た中国のやり方は正しいのである。
中国は、インターネットも遮断し、googleもfacebookも締め出し、アメリカのインターネット網から完全に閉鎖されたプライベートネットワークを作り出し、アメリカのPRISMという監視網からも逃れることが出来る。
従って、facebookが、リブラという仮想通貨を出す計画があるが、その影響も受けないのである。
中国は、独自にデジタル人民元をリリースすることで、facebookのリブラに対向することが出来る。
アメリカは、連邦準備制度と、世界の中央銀行の連携によるドル基軸通貨体制によって、現在、世界のマネーシステムを支配している。
facebookのマークザッカーバーグは、米国の政治家、高官たちにリブラは、アメリカの国益にかなうとして、その認可を求めている。
リブラが発行されると、リブラはたちまち世界に流通して、ビットコインなどとも連携して、米ドル基軸通貨体制が崩壊してしまう。
然し、リブラを認可しなければ、先にデジタル人民元をリリースした中国が、世界のマネーシステムの覇権を握ってしまう。
今、米国と中国は、そのようなマネーシステムの覇権争いの瀬戸際にもあるようである。
先日、テレビ東京の「ネット興亡記」という番組で、インターネットイニシャティブ会長の鈴木幸一氏の創業時の苦労がドラマ化されて報じられていた。
鈴木幸一氏は、日本で、1992年にインターネットのサービスを提供する会社を作ったが、当時、管轄だった郵政省が認可しなかったそうだ。
そして、1年半の間、サービスを開始できないで、遂に郵政省の幹部を前にもし認可してもらえないなら、提訴すると伝えて、やっと認可が下りたといったエピソードが、ドラマの中で報じられていた。
日本では、何かを認可一つもらうだけでも提訴までしなければならない。
孫正義もNTTがインターネットサービスを提供する為のNTTの局舎内の工事を妨害することに対して、総務省に通いつめ、何とかしてくれないなら、ここでガソリンをかぶって火をつけると言ったそうだ。総務省の職員はそれだけはやめて下さいと言ったそうだ。
他にも日本の役人から認可をもらうための苦労話は、沢山ある。
日本の役所が課す規制は、日本の経済活動などを全く停滞させる害悪そのものである。
他国のグローバル企業に対する規制は、国内企業を守るために役立つが、国内企業に対する規制は、全く日本の国益の為にもならない。
然し、日本の官僚は米国の圧力には屈して、市場開放、規制緩和し、日本の企業には規制を課すといったことをやって来たようである。
日本の官僚とは、日本に対する忠誠心も愛国心も日本の国民に対するサービス精神も何もないようである。
鈴木幸一氏によれば、アメリカがインターネットを官民挙げて推進してきたのは、世界の覇権を取るためという明確な目的をもって推進しているという。
そのような中で、日本の政府(官僚)は、日本の企業の活動をバックアップして連携して企業活動を推進できないことをもどかしく思っている。
日本はバブル崩壊までは、護送船団方式で、官民挙げて、日本の製造業を推進して来たのだが、1990年以降、米国が市場原理主義に舵を切り、構造調整プログラムによって、日本に金融市場の開放などを迫ると共に国家戦略として、インターネットビジネスを推進するようになってから、全く骨抜きになったようである。
この頃、大蔵省も解体され、財務省に名前を変えているが、日本の護送船団方式を推進してきた大蔵省の名前が変えられたことは、日本が骨抜きにされたことを象徴している。
バブル崩壊は、『円の支配者』のリチャード A ヴェルナーによれば、日銀のプリンスたちが、米国の金融資本家たちに忖度したか、彼らの要求を実行するかによって、銀行に割り当てている信用創造の枠を縮小して、マネーの供給を止めたからだと言われている。ここで大蔵省と日銀の争いがあったようである。
このように見てくると、全てが符合して非常によく分かるのである。
当時、何故、日本のバブルが崩壊し、米国が市場開放を盛んに迫って来て、それと同時期にインターネットビジネスを盛んに伸ばして来たかがよく分かるのである。
ちょうど日本のバブルが崩壊した頃に米国は、それまで公的機関が管理していたインターネットを民営化したのである。
アメリカの官民挙げて、他国に市場開放させて、インターネットビジネスも推進して、世界市場を制覇したと言うことが出来る。
今、日本のIT業界は、システム構築の仕事は、アマゾンウェブサービス(AWS)で運用されているサーバー上に構築するような仕事ばかりになって来ているのである。
インターネットの仕組みは、アメリカが生み出したものであり、インターネットビジネスは、アメリカが胴元の舞台である。
世界の見方というものは様々あるが、世界は、国家同士が覇権を奪い合う舞台であるという冷酷な見方は、政治においては重要なようである。
中国は、このアメリカが官民挙げて構築したインターネット網から自国民を遮断し、現在、アメリカに挑戦し得る唯一の国である。
中国が、アメリカに行なってきたことは、全く正しいと言わざるを得ない。
何故なら、アジア通貨危機の時にアメリカの強欲なヘッジファンドの売り攻勢も受けずに済み、IMFの支配を受けなかったのも中国では、自国民に規制を掛けて、アメリカの経済網に組み込まれないようにして来たからである。
アメリカは中国からは安価な物を買うことが出来るだけで、後は中国は、人民元の切り上げも拒否して、ひたすら米国に物を売り続け、ドルを蓄積し、実力を蓄えてきた。
その間、軍事的には、第一列島線や第二列島線といった対米防衛線を設定し、尖閣諸島、西沙諸島、南沙諸島を中国の領土であると規定し、制海権の確保を目的として、進んで来ている。
その結果、現在、南沙諸島を埋め立て、人工島に基地を建設し、着実にその計画を進めている。
中国はアフリカに資金を融資して、返済できない場合に港などの使用権を得るなど、アメリカが第二の植民地政策として、世界で行なってきたことと全く同じことをしている。
アメリカの覇権を揺るがす存在となり、通貨発行権も奪取する所まで迫っている。
そして、識者の話では、既にヨーロッパは、中国側についたという情報も伝わって来ている。
このように中国は、唯一、アメリカに挑戦できる国家であるが、国内に民主主義がなく、監視がひどい独裁的全体主義国家である為、他国から嫌われてもいる。
この両者のどちらが覇権を取るのかを各国は注視している。
中国でデジタル人民元がリリースされ、アメリカでもリブラがリリースされ、ビットコインとも共存している社会、そうした中で、アメリカの建国図から見た限りでは、アメリカ国内は、ますますひどい状況になっていくことが予想される。
また中国の建国図でも国内でデモなどが活発化していくことが示されている。
大国の覇権争い、民主化運動、新型コロナウィルスが流行する中で、現在、時代の転換期が進行中である。
先日、ジム・ロジャースの最新刊を読んでいたら、投資をする人は、何もしないで待つことが大事で、人生で20回ぐらいしか投資をするチャンスはないと思った方がいいということだった。
山羊座で株式市場が暴落する時、それが絶好の投資のチャンスだとすると、木星は12年、土星は30年で、12星座を一周し、ラーフ/ケートゥ軸は9年で、半周するので、これらの惑星、感受点が山羊座に入室する機会は、それ程、多くはない。
20回も無いかもしれない。
ジム・ロジャースが言っていることは正しいことが分かる。
ジム・ロジャーズは「日本は20年後、必ず没落する」と言っている。
その根拠として、少子高齢化、人口の減少を挙げている。
日本は巨額の負債を抱えていても外国人投資家によって円が買われ続けたのは、日本には長時間労働に耐える勤勉な国民が豊富に存在したからである。
日本の富とは、この勤勉な国民の労働が生み出してきたのであり、この日本の労働者たちの未来の労働を担保にして、いくらでも国債を発行でき、円を刷ることが出来た。
然し、人口のうち、働き盛りの若い労働者の数が少なくなれば、これ以上、借金をすることが出来なくなる。
MMT理論では、日本の国債を引き受けているのは、外国人ではなく、日本の国内の人々であるから、インフレ率の範囲内で、日本の円を発行できるというが、インフレ率の範囲内というのがポイントである。
MMT理論では、国債を発行して、円を市中に供給し続けたとした場合、インフレが起こらないといっている訳ではないのである。
日本の労働者が持つ生産能力を超える額の円を刷ったら、インフレになることは確かであり、インフレ率が直ぐにMMT理論が許容する範囲内を越えてしまう可能性もあり得る。
人口が増え続けている国の経済が成長するというのは、投資家の基本的な考え方のようである。
ジム・ロジャースは過去の作品でもそのように書いている。
インフレにならなくて済むのは、日本の経済の生産性が日本の労働者の頭数とは直接関係がない経済に移行している場合だけである。
然し、日本は本当にそういう段階に達しているのかどうかである。
実際は、労働者の数だのみで、マンパワーで乗り切るような経営が行なわれているような場合が多く、やはり労働者の数に依存しているのではないかと思うのである。
また労働者の数は、消費者の数も表わす為、労働者の数が減れば、消費者の数も減り、国内需要が減って、国内で回っていく経済規模も小さくなってしまう。
もし外国から外貨を稼ぐことが出来ないとすれば、日本はその国内の小さな生産と消費でやっていかなければならないということである。

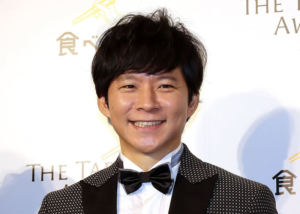







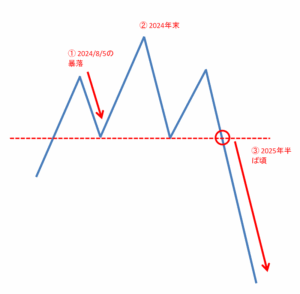

コメント