
安倍元首相が昨日、奈良県での演説中に後ろから銃撃され、心肺停止で救急搬送されたが、病院に到着した時点で既に心肺停止しており、蘇生措置を行なったものの、午後5時3分に死亡が確認された。
安倍元首相が、これ程、劇的な暴力的な死を迎えるとは全く予想していなかった。
むしろ、現在、金星/ラーフ期である為、この後も残りのマハダシャー金星期を派閥の長として、息の長い政治生活を送るものと思っていた。
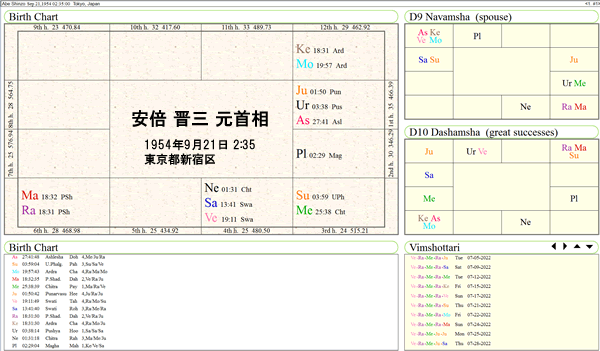
然し、安倍晋三元首相のチャートは、ラグナが激しく傷ついていることは分っていた。
それは潰瘍性大腸炎といった若い頃からの持病に現れていると考えることができるが、それだけに収まるには多過ぎるほどの傷を抱えていた。
ラグナには6室支配の木星が在住し、7、8室支配のマラカの土星と火星がアスペクトし、ラグナロードの月は、ラーフ/ケートゥ軸に絡み、火星からのアスペクトを受けている。
チャンドララグナから見てもラグナには、ラーフ/ケートゥ軸が絡み、6、11室支配の火星がアスペクトしている。
安倍元首相は、金星/ラーフ期に暗殺されたが、金星は7、8室支配のマラカの土星とコンジャンクションし、ラーフにもアスペクトして、マハダシャーロードの金星にもアンタルダシャーロードのラーフにもこの7、8室支配のマラカの土星が絡んでいることが分かる。
そして、土星は更にラグナにもアスペクトしている。
通常、暗殺は8室が表わす為、この土星が大きな役割を果たしたと考えることができる。
土星は月から見ても8室の支配星である。
土星はスヴァーティー(ラーフ)に在住しているが、金星と共にラーフを支配星とするナクシャトラに在住している。
そのことで、マハダシャー金星期には、この7、8室支配のマラカの土星が活性化されたのである。
そして、アンタルダシャーのラーフも7、8室支配の土星からアスペクトされて、直接、影響を受けていることもあるが、ラーフはプールヴァアシャダー(金星)に在住していることで、支配星の金星が活性化し、その金星と同じナクシャトラ・スヴァーティーに在住する土星をも活性化したと考えられる。
そのようにして、金星/ラーフ期には、7、8室支配のマラカの土星が大きな役割を果たしたのである。
因みにこの土星は、スティラダシャーでは、ルドラに該当し、ルドラとはインド神話に登場する暴風神で、全ての人を泣かせる折檻者を意味し、苦痛、もしくは苦痛の原因を取り去る人を意味するというが、既に述べたように火星は、マヘシュワラとなり、ヒンドゥー教のシヴァ神(破壊/再生を司る神)に該当する。
こうした神話的解釈も意味を為すかもしれない。
安倍元首相のチャートでは、金星と土星がスヴァーティー(ラーフ)に在住し、ラーフと関係し、ラーフはプールヴァアシャダー(金星)に在住して、更に同じくプールヴァアシャダーに在住する火星にも深く関係している。
金星、土星、ラーフ、火星といった惑星が、単なるアスペクトやコンジャンクションだけに留まらず、金星とラーフのナクシャトラ交換も交えて、緊密に連携して働いていたのである。
どんなチャートでもそうだが、惑星が在住するナクシャトラの支配星の連携を考えて行かなければ、緻密で微細な解釈をするのは不可能である。
私が気づいたのは、この安倍元首相の暗殺に貢献した7、8室支配のマラカの土星が、天秤座で高揚し、またナヴァムシャでは水瓶座でムーラトリコーナの座にあることである。
従って、防衛費2%への目標の修正を現政権に要求し、米との「核共有」議論を推し進めていた安倍元首相は、リベラル派にとっては影響力が大きいだけに厄介であった。
安倍元首相の政治活動を阻止したのは、出生図で天秤座、ナヴァムシャで水瓶座の土星であると考えると、論理的にリベラル派であるということになる。
然し、現在、リベラル派は、理性的であり、デモ活動など言論による平和的な手段によって、政治的主張を行っているので、リベラル派が実行犯にはなりようがないのである。
リベラル派は、安倍元首相の政策に反対であっても、言論という手段を通してそれを行なう。
然し、奇妙なことに海上自衛隊の元自衛官が、本来、国の安全保障を現場で実施するその自衛官が、報道によれば、政治的信条以外の安倍元総理の態度に不満を持っていて、暗殺を実行したのだという。
暗殺を決行した山上徹也容疑者は、「安倍元首相の政治信条への恨みではない」という趣旨の供述もしており、不可解である。
然し、この実行犯である山上徹也容疑者が、模倣犯であろうが、心神喪失や心神耗弱の状態にあろうが、カルマが実現される為の駒として役割を果たしたということかもしれない。
日本では銃規制が厳しく、また安倍元首相は、日本の神道右翼連合である日本会議に支えられて来ていた為、銃を容易に手に入れることが出来る右翼的な暴力団に狙われるということも考えられなかった。
従って、銃へのアクセスが可能な海上自衛隊の元自衛官に狙われるというのが、可能性のある唯一の細い線であったと考えられる。
そのようなほとんどあり得ないような細い線が実現してしまったということでもある。
私は、この安倍元首相の暗殺劇を見て、以前、ブログにも書いた米映画『アメリカン・スナイパー』のモデルにもなったクリス・カイルの最期を思い出した。
クリス・カイルは、イラク戦争の戦場で多くの敵を暗殺した「ラマーディーの悪魔」と名付けられた伝説の狙撃手である。
このクリス・カイルが除隊後の2013年2月2日にPTSDを患う元海兵隊員エディー・レイ・ルースの母親からの依頼で、同じく退役軍人のチャド・リトルフィールドと共にテキサス州の射撃場で、ルースに射撃訓練を行わせていたところ、ルースに突然、撃たれて死亡したのである。
それは全く因果関係がよく分からない不可解な死であり、何故、このPTSDを患う元海兵隊員エディー・レイ・ルースから撃たれなければならなかったのか全く理解できないが、カルマの法則とはおそらく、表面上だけでは、全く不可解で理解できないものなのである。
伝説の狙撃手クリス・カイルが、イラク戦争の敵国であったイスラムの兵士など軍事関係者から撃たれるのであれば因果応報として分かりやすいが、全くそうではないのである。
然し、カルマは、決して消えることはなく、しつこく追いかけてくるというのはこういうことであり、表面上、全く繋がりが分からない出来事によって、それが実現される場合もあるということである。
安倍元首相も日本の独裁者であり、トップダウンで、政治を推し進めた指導者であるが、独裁者はしばしば強引に自らの政策を押し通すため、暗殺の対象になることも事実である。
従って、安倍元首相が何故、暗殺されなければならなかったかは、これまで安倍元首相が行ってきた仕事の内容を総括して考えなければならない。
安倍首相は、森友学園問題、加計学園問題、所謂モリカケ問題で、激しく追及されたが、蟹座ラグナである為、政治権力を私物化する傾向はあったと思うが、それが国民にとって決定的に問題であったとは思えない。
そうではなく、アベノミクスなどの経済政策が問題であったと考えている。
アベノミクス=MMT理論の壮大な実験場
経団連の特定企業の株式をGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の資金で、買い支えたり(GPIFの国内株の運用比率引き上げ)、日銀に上場投資信託(ETF)を大量に買い入れさせたりといった行為である。
日銀が市中銀行から国債を引き受けて、通貨供給量を増やし、物価を上げて、インフレに導くことを買いオペと呼び、反対に市中銀行に国債を売って、通貨供給量を少なくすることを売りオペと呼ぶが、これが日銀の金融政策である。
金利を設定したり、買いオペ、売りオペなどによって、通貨供給量を調整するのである。
参議院議員で、トレーダー、経済評論家の藤巻健史氏が、日銀が、アベノミクスの下で、異次元金融緩和を行っていることを論理的根拠が乏しい「ブードゥー(呪術)経済学だ」と批判していた。
アベノミクスの下で、日銀が、市中銀行を経由してはいるが、政府が発行した国債を無制限に引き受けて、通貨を発行し、貨幣供給量を増やしていることを批判し、そのうち、ハイパーインフレが起こると警鐘を鳴らしていた。
日銀が国債を引き受けることは財政ファイナンスとして禁止されている。
国債は、政府によって市中銀行に割り当てられて、市中銀行が買わされるが、その後、最終的にお決まりのように日銀が買うことになっていたようである。
そのため、実質的に日銀が無制限に政府が発行した国債を引き受けて、輪転機を回し続け、通貨を大量に市中に供給する財政ファイナンスが行われていたと言われている。
因みにMMT理論(現代貨幣理論)では、自国通貨を発行できる政府は財政赤字を拡大しても債務不履行になることはないという。
銀行は信用創造によって、誰かが借金することによって、市場にマネーを供給している。
借金がなければ市場にお金がないのである。
これまでは企業がお金を借りて、利益を出して、銀行に金利を支払うなどして、企業が借金をすることで市中にマネーを供給していたが、今は、経済の成長センターがないため、企業は銀行からお金を借り入れることが出来ず、その為、政府が財政赤字を増やして、お金を借り続けることによって、市中にマネーを供給している状況である。
だから政府の財政赤字がこれだけ膨らんだのだという話である。政府が借金しなければ市場にお金がなくなってしまう。
政府の借金は、民間の預金ということになり、それでバランスシートが釣りあっているというのが、MMT理論である。
この理論を根拠として、れいわ新撰組の山本太郎は、インフレ率2%以内なら政府はどんどん国債を発行して、それで積極的な財政政策を行なうべきだと主張していた。
然し、アベノミクスというのは、実は、MMT理論の壮大な実験であったと言われている。
日銀が無制限に国債を引き受けて、異次元の金融緩和を行い、市場にマネーを供給し続けたのである。
然し、そのようにして増加したマネタリーベースは国民の所得に反映されず、ETF(上場投資信託)や長期国債等の買い入れなどに使われている。
国債を発行して、意義深い財政政策を行なうならまだ分かるが、アベノミクスの場合、株式市場にその増加したマネーが流れ込んでいる。
だから国民の給与には反映されず、株高によって支えられた企業は、国民に給与を支給せずに巨額の内部留保を抱えている。
労働者には少ない賃金で、過剰にサービス労働させるという考え方である。
通常は、労働者に適正な給与を支払うことで、労働者が購買者として、消費することにより、内需が発生し、経済が回っていくが、そうではなく、日本に指導層の考え方は、あくまでも労働者はただ働きさせる存在である。
現在、海外ではインフレが激しいが、インフレになる代わりに労働者にもそれなりに高い給与を支払うようになっている。
アベノミクスの結果、日銀の国債保有比率は、政権発足時には11.5%だったが、2020年3月末には47.2%にまで膨れ上がり、532兆円の国債を積み上げ、株式も33兆円を積み上げたようである。
MMT理論では、自国通貨を発行できる政府は財政赤字を拡大しても債務不履行になることはないという理論通り、特に日本は財政破たんしてはいないが、じわじわと円安に振れ始めた。
日銀がマネーを市中に過剰に供給した為、貨幣の価値が下がり、外貨との比較において、価値を失い始めたのである。
これは完全にアベノミクスの残した遺産である。
日本の国民は勤勉で、よく働く為、これまで日本の円は高く評価されてきて、決して円安にはならなかったが、ここまで財政赤字(将来の国民の借金)を膨らませたことと、例えば米国では、GPIFのような企業が台頭して、新しい産業が生まれたのに対して、日本は全く新しい産業が生まれずにこれまでの産業を八百長的な株高で支えた為、イノベーションなども起こらず、日本はこれといった産業もなく、財政赤字ばかりを増やした状態で、衰退し始めた。
こうした状態になって、日本の円の価値は、遂に外国の通貨に対して、価値を下げ始めたということである。
MMT理論通り、財政破たんはしないが、日本は原材料などを輸入している為、円安で輸入のコストも増え、じわじわと悪質なインフレになって来ている。
悪質なインフレとは、物が売れないのに原材料の価格の上昇で、物の価格を上げざるを得ないような状況で、経済的に活況してインフレになるのと全く違っている。
結局、アベノミクスは、国民の未来の借金である国債を発行して、それを日銀に買い取らせて、マネーの供給量を増やしたが、そのマネーは株式市場に流れ込み、富裕層の人々を潤わせた。
外国人投資家も潤わせたが、一般の労働者にはそのマネーは届いていない。
アベノミクスが始まる前は、ハローワークには失業者が溢れていたが、デフレ経済で、仕事はなかったが、国民が過酷な労働を強いられるという感覚もなかった。
アベノミクスが始まると、ハローワークから失業者が消えて、一見、皆、職を得て、ハッピーになったように見えるが、実際は、低賃金で過酷な労働を強いられるケースが多くなり、国民の貧困化が進んだと言える。
富裕層と貧困層の2分化が進んだと言える。
そして、国民は借金を増やし、特に経済においてイノベーションや新しい産業分野の開拓もなく、円の価値は下がって、円安となり、インフレになりつつある。
アベノミクスの結果、MMT理論は正しいことが証明されたように思われる。
日本はこれだけ巨額の財政赤字を抱えても決して破綻しないことがそうである。
もし日本が資源が豊富で、食糧自給率も100%であったら、完全に日本という閉じた系の中で、経済を回していけるため、財政赤字で、国債を発行して、一定のインフレ率の範囲内で、いくらでもマネーを供給しても大丈夫である。
然し、日本は資源がなく、食糧自給率も低く、外国に依存しなければならない為、外国から資源を輸入する際に日本が巨額の財政赤字を抱えていて、国民一人当たりの借金が膨大で、それでいて国民一人あたりの生産性が低かったら、外国の通貨に対する円の価値が下がってくる。
アベノミクスの結果、やたらと海外からの買い物客が増え、インバウンドの観光産業などが盛んになったが、日本は安い国となり、日本の労働者は、安くこき使われるようになって、良い結果につながらなかったという印象である。
MMT理論は正しいが、国債を大量に発行して、国民の未来の借金を増やすのは健全ではないということはよく分かる。
アベノミクスの結果、今、日本では円安の苦しみが始まった。
国民の貯金などは、外国通貨に対して目減りして、日本人は、外国に出て行けず、国内に留まっているしかない囚人のような状況になって来た。
昔、アジアなどに遊びにいったら、日本人が贅沢が出来た時代とはまるで違ってしまっている。
アベノミクスというのは、結局、日本は変わりたくない、今までのままでいたいということの現れである。
異次元金融緩和などを行い、株式市場にマネーを投入して、株高を演出し、旧態依然とした経団連の主要な日本の企業群を支えたのである。
新しい産業がイノベーションをもたらしたり、巨大産業にとって代わったりすることを許したくないのである。
古い構造を維持し続けたいというのが、アベノミクスの行ったことである。
但し、アベノミクスをしなかったらどうなったかと考えると、日本の主要な企業群は経営がままならなくなり、やはり外国の革新的な企業群にとって代わられたかもしれない。
日本を統治していた人々によって日本を統治し続けたいというのがアベノミクスである。
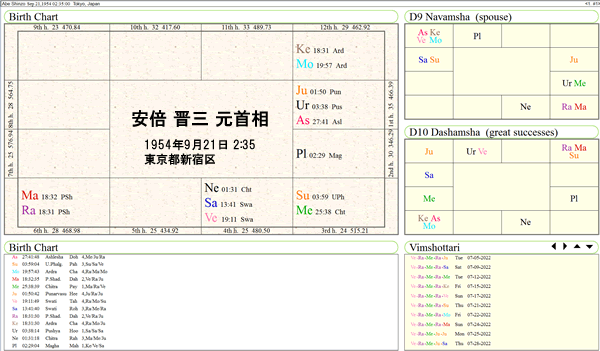
安倍元首相は、愛国民族主義者であるが、知らず知らずのうちに無意識的に外国人投資家に貢いでしまうような所もあった。
ラグナロードが、12室双子座(株式市場)に在住している為、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の資金を株式市場に投入したりして、外国人投資家に利益をもたらしたり、日銀の金融政策で、ETF(上場投資信託)を買うといったこともそうである。
外国にお金をばら撒いてしまうような所があった。
安倍晋三元首相のチャートを見ると、6室に火星とラーフが在住している。
これは官僚を動かして、自分の好きなような政治を行う権力を表わしている。
だからアベノミクスのようなことが実行できたのである。
然し、やはり、インディラガンディーのように自分の行ったことのつけが跳ね返ってきた結果、暗殺されたのだとしか考えられない。
安倍晋三元首相は、愛すべき人物で、批判もされたが、支持もされていて、人気もあった。
然し、エネルギーの世界で生じた反発が、元自衛官の暗殺者を通じて、具現化したのだとしか思えない。
但し、全ては、カルマであり、予め決まっていたことだったのだ。




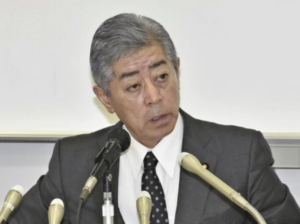






コメント