2008/9/21 奥菜恵について−8室火星と魔性の女の関係-
以前、彼女は天秤座ラグナだとしたが、ラグナロードが8室に在住している意味が明らかになってくると、彼女が蠍座ラグナで正しいことが分かってきた。
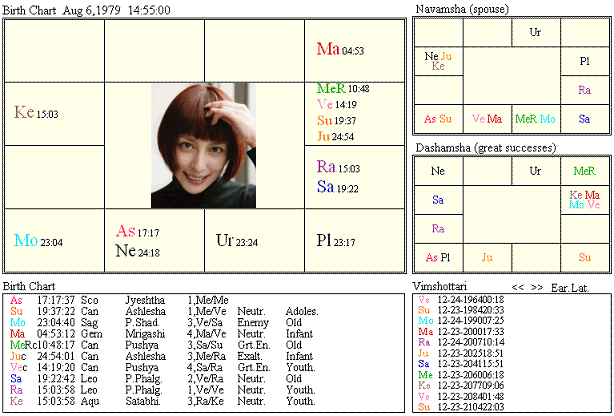
8室火星とは血の気の多い男性から、あるいは支配者としての男性から、ずる賢く支配されるということを意味している。
つまり、火星は男性器、筋肉、血の気の多い乱暴な若い男の象徴であり、そうした男性が彼女に君臨して、彼女を愛人、ペット、奴隷として支配下に置くことを意味している。
彼女の男性遍歴を調べると、明らかに男性から愛人のように囲われてしまう関係が多いようである。
それともう一つ蠍座ラグナでよいと思われるのは、9月6日(土)に公開された映画「シャッター」のプレミア試写会などに出席して、注目を浴びているからである。既に太陽は乙女座に入室してしまったが、映画が公開された9月6日の時点で、太陽が獅子座をトランジットしていたため、彼女が蠍座ラグナで獅子座10室に太陽がトランジットしていたと考えると納得できるのである。10室とは注目される大舞台である。
 彼女は最近では、魔性の女と呼ばれるようになり、2008年4月8日に自叙伝フォト&エッセー「紅い棘」(双葉社)を発売して妖艶な姿を写真で晒している。 彼女は最近では、魔性の女と呼ばれるようになり、2008年4月8日に自叙伝フォト&エッセー「紅い棘」(双葉社)を発売して妖艶な姿を写真で晒している。
それで思うのは、魔性の女とは何か?ということである。
魔性の女とは、次々と男性を誘惑する悪女というのが、ドラマや小説での描かれ方である。
実際、魔性の女とは、男性にとっては魅惑される相手で、危険な毒をもった落とし穴という印象であるが、 女性にとっては、何か男を誘惑する同じ女としては許せない相手のようであり、女性から嫌われるのが魔性の女である。
それでドラマや小説の架空の話でなくても、現実の私生活の話として魔性の女と世間から評価されている女優は何人かいるようである。
例えば、ドラマ「北の国から'92巣立ち」で人気のあった裕木奈江は、『ポケベルが鳴らなくて』の略奪愛的な役柄により、週刊誌で「男性に媚びる、同性に嫌われる女性」として取り上げられ、多くの女性から嫌われていたようである。
男性としては、彼女を嫌うということはないのであり、むしろ、何かほっとけない、守りたくなる存在なのであり、そうした意味で男性からは人気があるのである。
然し、女性たちにとっては、何かほっとけない、守りたくなるような、かよわいオーラを発して、男性をひきつける彼女に対して猛烈な怒りと憎しみを感じるようである。
私の経験からすると、魔性の女の行動パターンとしては、妻子ある男性を誘惑して、家庭を壊し、男性の子供を身ごもって、それで、男性との結婚を迫るというようなイメージが浮かぶのであるが、これはまさに典型的な魔性の女像ではないかと思うのである。
それで、魔性の女の本質とは何かというと、一言で言うと、それは、男たちに次々と支配したい、囲いたい、愛人にしたいと思わせる女性のことである。
それを占星術的な観点から言えば8室に惑星が在住する女性、その中でも特に火星が8室に在住する女性は、魔性の女としての素質がある女性だと言える。
それが、奥菜恵のラグナロードの火星が8室に在住している配置の意味である。
だから、彼女は魔性の女と評価されたのだと思われる。
彼女は、そのようなカルマを持っているから、支配欲旺盛で、女を囲いたがる、あるいは結婚ということは考えずに、ただ女性と性的関係を結びたいという、女性をペットや愛人として扱う、性欲旺盛な男性をひきつけるのである。その結果、彼女自身が男性経験において、場数を踏んでいる結果としての性的に開発された妖艶な魅力を醸し出すのである。
私は以前から8室は性的魅力を表すハウスであるという説明は聞いていたが、それが何故かを説明してくれる人は今までいなかったのである。然し、8室を”支配者”として解釈すると、何故、8室に惑星が在住している女性が性的魅力があるのかが非常にクリアに理解できるのである。
8室に惑星が在住している女性はそもそも男性から支配されるというカルマを持っているため、男性に支配者としての自分、(性的に)強い自分を意識させるのである。そのような女性は、本能的な潜在意識のレベルで男性に性的な自信を与えるのである。だから、魔性の女とは、男性に自然に性的欲求を感じさせる女性なのである。
つまり、性的魅力とは、セックスアピールとして異性に対して働きかける力であるが、それは、男性に支配者としての自分を意識させる力である。
例えば、近親相姦で、幼い頃に父親から性的に犯された被害経験を持つ少女を精神科医(男性)が診察した時に、精神科医が内心、恐れを抱くほどの性的な誘惑をその少女が発したという話を聞いたことがある。つまり、何故、精神科医が恐れを抱いたかというと、精神科医自身の前意識、無意識に潜む支配欲を幼いながら強く刺激したからである。
(その話自体は、後に成人になって過去を回想した女性が著した本から引用されていると思われるが、その本の題名、著者名等は不明)
まさに男性から性的に支配された経験のある女性は、早期に性的に開発されて妖艶な恐るべき性的誘惑を示すようである。
その被害にあった少女はおそらく8室に火星やその他の惑星が在住していたり、1室と8室が星座交換していたり、8室の影響が必ずあるはずである。そうでなければ、無理やり自分の意思に反して、自分の身体を拘束されて、性的行為を強要されるような経験をするはずがないのである。そうした体験は支配者(8室)との支配/被支配の関係を表しているのである。
因みに8室の火星というと、マリリンモンローもそうである。
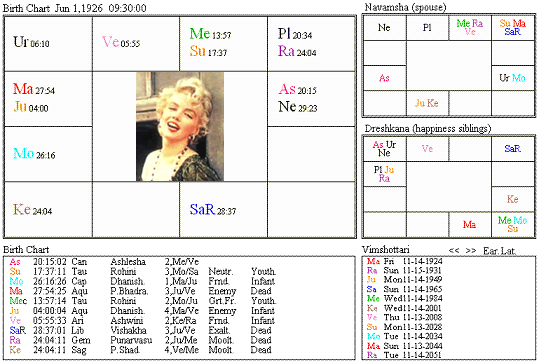
彼女の男性遍歴を見ても、複数の男性から愛人として囲われていた印象である。
彼女はセックスシンボルと言われたが、つまりは、男性が遊びたい、囲いたい女性ということで、魔性の女と同じような意味合いである。
日本の場合は、家父長的な伝統があるからか、魔性の女という言葉は、少し陰湿な響きを伴い、米国文化のセックスシンボルという言葉からは、陽気な印象を受けるが、どちらも、遊び相手のペット的な愛人のことを表している。
魔性の女 ≒ セックスシンボル
彼女は9室支配の木星が8室(9室から12室目)に在住しており、生まれた時、既に父親はいなかったようである。(死んでいたわけではなく、母親を捨てて女性と一緒に出て行った)
8歳の時に「預けられた先で性的虐待を受けた」と経歴にあるが、性的虐待というのは、抽象的な言い方をしているが、直接的に言えば、”男性から犯された”ということである。
つまり、これは8室火星の象意であり、血の気の多い暴力的な男性から力づくで犯された支配されたことを表している。つまり、外傷経験を伴いつつ、早期に性的に目覚めてしまい、娼婦のような性的魅惑を発揮し出したということである。
それで「中学生になると、マリリンモンローは自分が男の子達の熱狂的な関心の的となっているのを知る」と経歴に書かれているが、早熟な当時のマリリンモンローを見て、男子学生たちが仲間内で彼女と交際できないかどうか、噂し合っている光景が目に浮かぶのである。
先に述べた幼少期に性的な被害を受けた女性(つまり、8室に火星が在住する女性と言い換えてもいいが)は成人してから、結婚が何度も破綻したり、男女関係も続かないで、幸せな異性関係を築くのが困難であったようである。
つまり、6/8の関係によって支配され、愛人とか、ペット並みの性的対象としての扱いしか受けないため、愛情にも飢える結果となり、次から次へと相手を変えてみても、やはり、同じような関係性に陥って、愛情面で空虚なのである。それで幸せな異性関係を築くのが困難なのである。
これはマリリンモンローにも言えることであり、奥菜恵にも言えることである。
マリリン・モンローはジム・ドハティー、陸軍カメラマン、デヴィッドコノーヴァー、ジョニーハイド、アーサーミラー、ジョーディマジオと男性遍歴を続けるが、皆、おそらくモンローの性的魅力に魅かれた人々ではないかと思われるが、これは彼女の男性遍歴の一部であり、実際、彼女と性的関係を持った男性はこれ以外にも大勢いると思われる。
10室支配の火星が8室に在住しているため、彼女の仕事というのは、男性に支配され、男性と性的関係を持つことを避けられなかったのではないかと思うのである。
それは、彼女にモデル業への道を開いた陸軍カメラマンのデヴィッドコノーヴァーとか、脚本家のアーサーミラーとか、彼女は男性と寝ることで仕事が得られるようである。
石油会社のヌードカレンダーに出たことも石油会社という火星の強そうな経営者の管理下にいるということであり、その会社からお金をもらってヌードになったのであるから、逆に言うと、お金をもらって裸にされたようなものであり、8室火星の支配を感じさせる象意である。
20世紀FOXとの有利な契約を結ぶ尽力をしたジョニーハイドにしても、彼女は性的関係を結んでいると思われ、彼女は自分に仕事をもたらしてくれた男性とは肉体関係を結ばざるを得ないのかもしれない。
つまり、彼女から感じることはホステスのように自分の肉体を武器にして体を張って生きている印象である。 これは魔性の女の進化した形であり、複数の支配者を持ったり、支配者を渡り歩いていくことでたくましく生きているという印象もあるのである。このタイプの女性の開き直った形かもしれない。
彼女の場合、8室に9室支配の木星も在住しているため、支配を受けた男性からは必ず、仕事のチャンスなど、何らかの利益が得られるようである。木星は数が多いことを示しているので、支配者がたくさんいるのである。
 一方、奥菜恵の場合は、押尾学、藤田晋、山内圭哉など、異性関係を結んでも、幸福な関係が続かないようである。 一方、奥菜恵の場合は、押尾学、藤田晋、山内圭哉など、異性関係を結んでも、幸福な関係が続かないようである。
藤田晋との結婚後の生活について、以前、何かの雑誌(不明)で読んだ感じでは、彼女がIT社長の社交生活に全く馴染めず、仕事熱心な藤田晋が奥菜恵を構わないので、ある種、”放置プレイ”のような状態になっていたようである。
”放置プレイ”というと、江川達也の漫画「東京大学物語」で有名になった用語であるが、支配して完全に管理下には置くが、放置して全く関わらないという行為を指すのであり、これは一つの支配の形であり、暴力の一形態である。
また彼女が以前、何かの雑誌(筆者の記憶で詳細は不明)で、自分が変な趣味があるということを告白していたのだが、その内容については秘密であると語っていたのを覚えている。
その秘密ですというところから、何か彼女にとっては恥ずかしいことなのではないかと当時、漠然と思ったのだが、今思えば、それは何かM(マゾ)的な趣味であり、例えば、縛られたり、拘束されたりするようなことを楽しむような趣味ではないかと今になってみると思うのである。
これは全くの私の推測であるが、案外当たっているかもしれないのである。
このように、最近、6/8の関係に関する理解がすすんで来たところで、もう一度、奥菜恵のチャートを見た所、8室の火星は、まさに男性からの(性的なニュアンスも含めた)支配を表しているようである。
彼女はチャンドララグナから見ると、1室と8室で星座交換しており、8室に水星、金星、太陽、木星と惑星集中しているため、まさに8室が強調されている女性の男女関係のパターンを示すよい事例の一つではないかと思われる。
(資料)に示した『紅い棘』から引用した彼女の男性遍歴によれば、初恋の相手に嘘をつかれて逃げられたり、暴力を振るう年上の男性と同棲していたり、結婚した相手から所有されたような状況で、構ってもらえず、放置プレイのような境遇に置かれたり、交際した年下の男性に何度も浮気をされ、三角関係に悩むなど、まさに彼女の恋愛、パートナー関係というものは、その様々な形態は異なるが、男性から”支配”されている関係と言えるのではないかと思われる。
そして、魔性の女のもう一つの条件かもしれないのは、蟹座の強調である。それも出来れば蟹座アーシュレーシャに在住していれば申し分ないのかもしれない。
奥菜恵は蟹座に水星、金星、太陽、木星が惑星集中しており、 そのうち、太陽と木星がアーシュレーシャに在住している。
マリリン・モンローはラグナが蟹座アーシュレーシャである。
そして、文中で触れた、裕木奈江は、月が蟹座に在住している。(出生時間が分からないため、プシュヤか、アーシュレーシャかのどちらか不明)
蟹座は守りたいという欲求と、守られたいという欲求があり、これも男性に対して守って欲しいというメッセージを発信する一つの要素かもしれない。
従って、蟹座への惑星の在住と、8室在住の火星の条件を満たすと、ほぼ、魔性の女としての素質を示していると思うのである。
(資料)
wikipedia 奥菜恵
wikipedia マリリン・モンロー
奥菜恵 腹をくくった“魔性の女”
日刊ゲンダイ 最終更新:4月5日10時1分
●自叙伝を発売 奥菜恵(28)の電撃復帰が話題になっている。 奥菜は昨年5月にそれまでの所属事務所を辞めて女優業を休業。自宅を引き払い、日本とニューヨークを行き来する気ままな生活を送っていた。
かねて興味を持っていたスピリチュアルについて勉強しているという情報もあった。そんな奥菜が今月8日に自叙伝フォト&エッセー「紅い棘」(双葉社)を発売する。
同書では05年7月に離婚したサイバーエージェントの藤田晋社長との結婚から破局までの“真相”や、過去の恋愛遍歴について赤裸々に語っている。
これまで、ヤンキー系俳優、無名ギタリスト、年上の劇団俳優、ハワイ帰りのサーファー、イケメン僧侶、年下の舞台俳優、IT経営者といった相手との熱愛がウワサされてきただけに、注目が集まるのは間違いない。
●フリーで再出発 告白本の発売をきっかけに、奥菜は芸能活動を本格的に再開させる。 今後は女優業だけでなく、写真、詩、デザイン、演出などさまざまな分野に挑戦するという。今回の告白本では、自ら撮影したセルフセクシーショットが100点も掲載されている。
「奥菜が所属事務所を辞めたとき、“このまま引退するんじゃないか”なんて声もありましたが、本人はヤル気まんまんでした。辞める直前に“舞台のプロデュースをやりたい”と漏らしていたし、関係者には“事務所を辞めるけど、これからもよろしくお願いします”とあいさつしていましたからね。今後は芸能プロに所属することなく、フリーで活動していくつもりのようです」(マスコミ関係者)
●険しい道のり? 奥菜の再スタートは順風満帆なのか。 「休業前に出演したドラマや映画が散々な結果に終わり、“女優生命の危機”といわれていましたからね。それに、彼女は奔放で気ままなタイプだから、いつまたスキャンダルを報じられるかわからない。芸能プロや広告関係者もそれは分かっています。テレビやCMではなかなか使いづらいでしょう。海外でスピリチュアルや占いについて勉強していたといいますが、その手のジャンルは“逆風”が吹いているだけに、売り物にはなりません」(テレビ関係者)
昨年12月、奥菜サイドが前夫の藤田社長に10億円の財産分与を請求したと報じられたが、実際には過去に話し合いが行われ、すでに解決済みの事柄だったようだ。
告白本の中では「信頼できる人がいる。子供が欲しい」と漏らしているが、それまでにできるだけ稼ぐ必要がある。 仕事に本腰を入れる奥菜から目が離せない。
|
※以下は、奥菜恵の自伝「紅い棘」からの引用であるが、彼女のパートナー関係のパターンについて伺い知ることが出来る内容となっている。相手から嘘をつかれたり、浮気されて三角関係となったり、物のように所有されて、相手に放置されたり、関心をもってもらえなかったりといった男女関係のパターンが浮かび上がる内容となっている。これらは一言で言うと、パートナーからの支配ということができる。(秀吉)
|
「紅い棘」双葉社 奥菜恵著より
初恋 (P.90〜P.93)
あれは、小学校6年生のときだった。
その頃私は、学校が終わると毎日のように女の子の友達と近所の公園で遊んでいた
。おしゃべりしたり、鬼ごっこをしたり・・・・。特別何をするというわけではない。子供特有の無邪気な遊びに興じていただけなのだが、それが私には楽しみだった。
「キャー、やめてよ〜っ」
あるとき、公園の水場でいきなり男の子から水をかけられた。いたずらの主は、いつも公園で見かける顔だった。公園には、私たちとは別の男子グループもちょくちょく遊びにきていたのだが、水をかけたのは、そのグループで子分を引き連れていちばん威張っていたリーダーらしき男の子だったのだ。
「お前ら何年生?」
「え?6年だけど、あなたたちは?」
「俺らも6年。○○小学校」
このことがきっかけで、初めて男子グループと話をした。
「じゃあ、また明日ね。バイバイ」
意気投合した、というのだろうか。私たち女子のグループと、別の小学校に通う男子グループは、いつの間にかその公園で放課後に落ち合うのが日課になっていた。
「好きってことなのかなぁ・・・・」
私は、男子グループのリーダー格の男の子に恋をした。初恋だった。
「お父さんの仕事の都合でポルトガルに行くから、もう会えないんだ」
ある日、その男の子はそれだけ言うと、私に手紙らしき封筒を渡して、自転車でその場を去った。
「もう会えなくなるけれど、2、3ヶ月したら戻るので、8月X日にこの公園で待ち合わせしよう」と書かれていた。
私は、初夏の香りのする風と戯れながら、その手紙を読んだ。
家路につくまでの道で、泣きじゃくりながら何度も何度もその手紙を読み返した。
約束の日がやってきた。私は緊張しながら公園で彼を待った。しかし、彼は姿を現さなかった・・・・。
もしかしたらポルトガルから帰れなかったんだ・・・・。
それからも私は毎日、学校が終わるとすぐに公園に向かった。
今日は来るかもしれない。もしかしたら、もしかしたら、もしかしたら・・・・。
月日が流れた。思い出だけが公園の水場に葬られてしまいそうなそんな頃。追い打ちをかけるような出来事が私を襲った。
その日、いつものように公園を歩いていると、向こうから見覚えのある顔が近づいてくるではないか。自転車に乗った男の子たちの集団。子分を走らせ、引き連れるように先頭で自転車をこいでいたのは、彼だった。
「!」
目が合った。
思い切り声を出して名前を呼んだ。
「ヤバッ・・・・」
バツの悪そうな表情を浮かべ、彼は大急ぎでその場からいなくなった。
「え?なんで逃げるの?ちょっと待って!待ってよ!!!!」
彼は逃げてしまったが、子分を捕まえて私は問い質した。
「なんで日本にいるの?ポルトガルじゃなかったの!?」
「何?ポルトガルって!?」
すべて嘘だった。名前も、父親の仕事の都合でポルトガルに行くということも、年齢も実はひとつ年下で、通っている小学校も嘘だった。
「何なの、それ・・・・」
私が大きなショックを受けたことは言うまでもない。
悲惨な形で終わった初恋。その傷を私はちょっぴり引きずった。
愛の原型 (P.93 〜 P.94)
10代後半から約4年の歳月を共に過ごした人がいる。
車の好きな人だった。彼は、年上の男性らしく私をリードしてくれる一方で、自分の怒りをコントロールできないところもあった。何かの拍子にスイッチがオンになると、怒りの矛先を暴れるという形で私や物に向けた。
私は完全に周りが見えなくなっていたし、その彼の言動を愛情表現だと勘違いしていたのかもしれない。誰の忠告も聞き入れる耳はなかった。どんなに辛くても一緒にいることが、私にとっての幸せで、相手にとっての幸せだと思っていたのだ。
マインドコントロールが解けたというのだろうか・・・・。
結局、その人とは、私のほうから切り出す形でお別れをしたけれど、私は一緒に過ごしたことを後悔はしていない。私も相手も、互いを想う気持ちに嘘はなかったと思う。感謝もしている。
人と真っすぐに向き合い、そして愛情を注ぐ”捧げる愛”。それを痛いほど深く教わったような気がする。
これが私の愛の原型を作ったのかもしれない。
結婚 (P.95 〜 P.101)
愛する人から必要とされ、そして自分が相手に愛情を注ぐことに、喜びを感じる。
「結婚しよう」
そう言われたとき、この人にとって私は必要な存在なんだとしみじみ感じ入った。
彼からはたくさんの幸せや喜びをもらった。
でも、何よりも嬉しかったのは、このプロポーズの言葉だったかもしれない。
最初、私は彼が何をしている人なのかまったく知らなかった。
会社を経営していると聞かされても、まったくピンとこなかったし、仕事の内容を聞いてもよく分からなかった。今までも心を大切に恋愛してきたように、ただただ彼の素朴な人間性と穏やかな”心”に惹かれたのだった。
当時は、とてもいい意味で社長っぽくないというか、ギスギスした鋭さもなくて、その柔らかい自然体な人柄から、私がそれまでイメージしていた青年実業家の概念が一気に引っくり返されたのをよく覚えている。
自分とは一生接点を持つことはないだろうと思っていた業界の人だっただけに、初めは自分でもびっくりしたけれど、そんなことよりも、何より彼の醸し出す空気感やその内に秘められた強さが好きだった。
相手がどんな仕事をしているとか、どんな立場の人間であるのかをきちんと実感として把握したのは、ワイドショーや新聞、雑誌に書かれているものを目にしたときだったのかもしれない。
私たちが結婚したとき、世間は”セレブ婚”などと騒ぎ立てたが、私は自分のことを言われている実感がなかった。
「そうなんだ・・・・」
まるで他人事のように受け止めていた。
私にしてみれば、何かの縁で知り合って結婚することになった人が、たまたまそういう仕事の人だったというだけだった。
はっきり言って私にはそんなことよく分からなかったし、どうでもよかった。
ただ何を言われても、目に見えるものだけではなくて、心で感じる幸せが保てれば、それだけでよかった。自分たちの心が守られればよかった。
二人のことは二人にしかわからない。どう見られようが、何を言われようが、その二人の心は二人で守るしかない。それだけで幸せだった。
「私たちは、周りによって心が壊されないよう二人でちゃんと守っていこうね」
当時、私はよくこう言っていた。
なぜなら、表に出て、マスコミに取り上げられ、それらによって心が惑わされることで、二人の居場所を見失ってしまうこともあるということを、私は少なからず自分の経験を通して感じていたからだった。それだけは絶対に避けたかった。
2004年2月、私は妻になった。24歳のときだった。
東京のゲストハウスで挙式と披露宴を行った。お互いの友人たちの前でブーケトスをした、あのときの私は喜びに満ちあふれていた。
早い結婚という見方もあるかもしれない。でも、私自身、結婚願望がなかったというのも大きかったと思うけれど、結婚への迷いはあまりなかった。新婚旅行にも出かけ、楽しい新婚生活がスタートした。
結婚して1年ほど、私は仕事をセーブした。
彼は、私に仕事を辞めて家庭に入ってほしかったようだった。
「お金はあるんだから、もう働かなくていいんだよ」
嬉しかったけど、私はお金のために働いてきたわけでも、働きたいわけでもなかった。ただ純粋に演じることが好きだった。その場所が私にとって唯一生きてると感じられる場所だった。
芸能界に対する釈然としない気持ちは抱き続けていたものの、私は辞めるつもりはなかった。
だから、とりあえず、期間は決めず、1年くらいをめどに仕事を休みにして家にいることに決めたのだった。
妻になったという気負いのようなものはなかったけれど、私ははりきっていた。
そして、どんなに忙しくても心のすれ違いや、心のつながりだけは失わないようにしよう、そう心に強く思っていた。
彼は毎日忙しかった。彼の仕事のことはまったくわからない。私が口出すべきところでもない。ならば、せめてくつろげる場をつくることにしよう、帰ったときにホッとできる空間にしよう、そう努めることにした。
たまに家で食事ができるときには、土鍋で玄米を炊いたり、バランスを考えて新鮮な野菜を使った料理に切り替えたりした。毎日のスーツや普段着を選んだりすることも楽しかった。喜ぶ顔を見れば見るほど、全てが嬉しくて幸せだった。
食事も掃除も洗濯も私にできることがあれば、私はなんでもしたかった。できることといえばそれしかなかったからだ。
「私は家のことは自分でできるし、何でも自分でやりたい。掃除だって掃除のおばちゃんたちがくると思ったら気を使ってゆっくりできないし、自分たちの家は自分の手できれいにしたい。これからは私にやらせて」
「そういうのはプロに任せておけばいい。掃除だってハウスキーパーがやったほうがキレイだし。何もしなくていいよ」
普通に考えたら楽だし、ありがたい幸せなことなのかもしれない。私が仕事をしながらだったら余裕もなかっただろうし、違ったと思う。贅沢な悩みだ。
でも私は基本的に家のことをやるのが好きだし、精神的にも物理的にも、とにかく彼の支えになりたかった。もしかしたら、自分の存在理由を見いだしたかったのかもしれない。
考えてみたら、そんなに長い間ゆっくりしたのは初めてのことだった。仕事を休んだことで、ぽっかりと心に穴があいてしまったようで、何もない自分でも必要としてくれてる人がいることを、ちゃんと感じたかったのかもしれない。
何でもいいから支えでいたい。
単なる自分のエゴかもしれない。でもエゴだとしても、そんな自分で存在していることを感じていたかった。必要とされたかった。そのために何でもしたかったし、力になりたかった。
結婚して間もない頃、親友がわが家に遊びにきた。あとから聞いたことだけど、そのとき私が発したひと言が印象的だったと彼女は言った。
「地に足が着かない・・・・」
自分では覚えていないけど、結婚生活の感想として、私はこう漏らしたらしい。
「変かもしれないけど、あのときの言葉を聞いて、やっぱりどこにいてもあなたは変わらないんだって安心したんだ」
彼女はそう言った。
何気なく発した私の言葉は、その後を暗示していたのかもしれない。
存在価値の喪失 (P.101 〜 P.108)
”悲しみは半分に、喜びは2倍に”
結婚するとき、父が一枚の絵を贈ってくれた。その絵に書かれていた言葉である。
彼と暮らしはじめてからどれくらい月日が過ぎた頃からだろうか。私は、この絵を眺めながら、自分たち夫婦のことを考える時間が多くなっていった。
楽しみながらはりきって生活していたというのに、私の心にはぽっかりと穴が空いていた。
”空の巣症候群”というものがあるらしいけど、そんな状態だったのかもしれない。
一種のうつ状態と言うのだろうか。
子育てを生きがいにしていた主婦が、子供が巣立ったことで空虚な現実に直面して、その生きがいを家事や夫を支えることに見出してはみたものの、夫の無反応、無関心なその態度から、自分の存在価値を見いだせなくなって生きる気力を喪失したりするらしい。
私の空虚感とはちょっと違うのかもしれないけど、子育てを仕事に置き換えて考えたら、私は正にそんな心境だった。
よく愛情の反対を”憎しみ”とか言うけれど、”無関心”ということほどつらいものはないのではないかと思う。私は自分の存在理由について悩んでいた。
「夫婦って何だろう。人と一緒にいるってなんだろう」
心の会話や、つながりを感じることよりも、ただ彼の今までの生活の延長線上に、私がちょこんと加わっただけのような感覚で、相手の視界に入らない自分自身が、まるで空気のように思えることも多かった。
仕事の忙しさが原因なのか。
そうとは思えなかった。もっと根本的なことだった。生活の全てがそうではないにしても、話をしても、何かをしても、私の存在が見えてない。声も届いてない。
幸せだったはずなのに、私に無関心、無反応というその素っ気なさに次第に不安を覚えるようになっていった。
私という人間に、本当は興味がないのではないだろうか。私は必要とされているのだろうか。本当にこの人は私を見てくれているのだろうか。愛してくれているのだろうか。
私はそんな寂しさを確かに感じていた。
怖くて不安で仕方なかった。
何がこの人の幸せで、何を望んでいるのだろう。
笑顔を見たいから優しくいたいし、いろんな気持ちを共有したい。喜びも分かち合いたいし、悲しみや苦しみだって支えたい。それが本当の意味で人と一緒にいることだと思っていた。
でも何かがつながっていない。そう、心だった。
初めからそうだったのだろうか。そうじゃなかったはずだ。でも一緒にいられることの楽しさや喜びに私が舞い上がっていただけで、見えていなかったのだろうか。
それとも彼の中の何かが変わってしまったのだろうか。不安が募った。
表面的な幸せや喜びなんて私は求めていない。 私は知りたかった。感じたかった。私にとっては、心と心のつながりさえあれば他に何もいらなかった。
休みのときに食事に行ったり、買い物に行ったり、旅行に出かけたり、確かに楽しかった。でも深い部分ではどうだったのだろうか。確かに楽しい。でも楽しいだけで、本当の意味での幸せとは何かが違う。
彼にとっては、どこに行って、何をする、というその事実があればよかったのかもしれない。
どこにいても何をしていても一緒にいられる喜びをともにわかちあうことや、その気持ちを大切にすることが私にとっての幸せだった。ただ幸せを感じながら一緒にいられるなら場所なんてどこでも良かった。
何かをすることが重要ではなかった。
そこが私たちの最大の価値観の違いだったのかもしれない。
幸せなはずなのに、それは”はず”でしかなく、どこか寂しくて虚しくて、心が泣いているのを感じていた。
一緒にいるのが私である必要はないんじゃないだろうか。私はこの人にとってどんな存在なのだろうか。
その頃、彼は本を書いていた。
その本の中に私を登場させたいと言われたことがあった。
「私は”奥菜恵”じゃなくて、一人の人間としてあなたの妻になっただけだから、あまりそういう形では出たくない」
「本を売るために仕方ないじゃん」
「・・・・・」
彼は、私を見ているのではないかもしれない。やっぱり私が感じている寂しさは嘘じゃない。そう思った。
今の私ならもう少し余裕を持って立っていられたかもしれないけれど、当時の自分にはそんな器も心の余裕もなかった。
私が神経質になりすぎていただけなのかもしれない。
”セレブ婚”と騒がれ、”ヒルズ族”と呼ばれてもそれは仕方のないことだったのかもしれない。
でも私は悲しかった。嫌だった。今まで私はお金で人を見てきたことなんか一度もない。人に対してお金で判断したりすることを、最も軽蔑してきた自分があっただけに、そんな眼差しが自分に向けられ、異常なまでの嫌悪感を抱いていた。神経質にならざるをえなかった。
たとえ大前提として敏感になりすぎてた自分がいたとしても、心で会話ができないことは私にとってはとても悲しいことだった。
私は自分の存在価値を確かめたいと思ってしまう。愛すれば愛するほど相手に必要とされたいと願うし、そんな自分であるための努力もする。
そんなつながりきらない心に耐え切れず、気持ちをぶつけることが増えていった。
「これだけ幸せを与えているのに、何が不満なの!?」
ある日、彼にそう言われた。
「私の幸せは目に見えるものが全てじゃない。心の会話ができないことが悲しい。何をしても、何を言っても無関心で、私じゃなくても成り立つって思えてしまうことがもう耐えられない」
「これだけ買い与えて、不自由ない生活をさせてるじゃないか」
感情のスイッチが入って、私は言ってはいけないことを思わず口にしてしまった。
「買い与えて!? あなたの幸せってお金? 肩書き? 世間体? 高級レストランに行くこと? 外車を乗り回すこと? 私はそんなの求めてない! 私はお金と結婚したんじゃない!」
涙が止まらなかった―――。
全ての人がそうなのかは分からないけれど、愛でつながれる喜びが私の幸せで、表面的な幸せや物質的な幸せがいちばん大事だなんて思ってこれまでを生きてきてないし、私は求めていない。
幸せの基準や向かっている方向が違うのかもしれない、二人の間には決して埋められない溝があるのかもしれないということを、私は感じていた。
離婚 (P.108 〜 P.115)
そんな想いを抱えながらも、それもひっくるめて彼を愛する気持ちがそこにはちゃんとあったし、私は前向きに歩み寄ることを考えていた。
彼のご両親のことも大好きだった。とても温かくて平和な空気の漂うお父さんとお母さんだった。遠く離れた場所に住んでいたため、会うことは滅多になかったけれど、お母さんは時々私に手紙を書いてくれていた。
”あの子は、あなたに寂しい想いをさせていませんか?”
あるとき、その手紙のその一文を読んで、思わず溜まっていた感情が爆発して、一人で号泣してしまったことがあった。
寂しい想い・・・・。私は確かに寂しい想いをしていた。
お母さんは彼の性格をよくわかった上で、私の気持ちを心配してくれていたのかもしれない。
でも、大丈夫。彼には素敵なところもたくさんある。温かいところもたくさんある。ここで泣いてちゃいけない。初めの頃を思い出そう。彼を精いっぱい支えよう。そう思わせてくれたありがたい手紙だった。
夫婦にはきっといろいろな時期がある。
どんなことも乗り越えよう。乗り越えたい。
私の両親や、彼のご両親のように、年老いても一緒にいられるように頑張ろう。
雑念を取り払うようにして、新たな気持ちで彼と向き合おう、そう心に決めて楽しく生活していたある時期、私の中でさらなる亀裂を生む出来事があった。
結婚前から私が大切にしていたジュエリーボックスがある。
そのジュエリーボックスは父が私の誕生日に贈ってくれた、とても思い入れのあるもので、結婚してからも愛用していた。
「見てこれ!パパが買ってくれたんだよ」
「ふーん。どうせお前のお金で買ったんでしょ?」
何気なく言っただけの言葉で悪気もなかったのかもしれない。
でもショックだった。
その瞬間、怒りなのか、悲しみなのかよく分からない感情に、頭が真っ白になって震えが止まらなくなった。
理解ができなかった。その彼の感覚に戸惑い、恐怖さえも感じた。
目を背けたくても、このときばかりはどうしても目を背けられなかった。なぜなら、その瞬間に私の記憶の回路があるところにフラッシュバックしたのだ。
結婚してから初めての彼の誕生日に、私は贈り物をした。
「どうせ俺の金で買ったんでしょ?」
そのプレゼントは気持ちを込めて自分の貯金で贈ったものだった。
彼からしてみれば、冗談で言ったのだろうと思って、多少のショックは受けつつも、そのときは私は笑って流していた。
しかし、今回ばかりはそうもいかなかった。
自分のことなら今までのように笑って流せたのかもしれないけれど、親からもらった大切な贈り物に対して、そんなことを言われたということが大きかった。
その感覚が私にはどうしてもわからなかった。
私は人と心でつながっていたい。優しい気持ちで繋がっていたい。それだけだ。
このとき、結婚した事実にはっきりと疑問を抱いたのだった。
これくらいのことでショックを受ける私がおかしいのかもしれない。そう思って逆の立場でも考えてみた。でもいくら考えても、私にはそれが例え愛する相手じゃなくても到底言える言葉ではないと思った。
人としての価値観の違い、考え方や捉え方の違いに、私には歩み寄りたくても歩み寄れない次元の出来事だった。根本的なものが完全に違う、そう感じた。
本当はこの本の出版にあたって、このことを書くかどうかもすごく悩んだ。いや、書いている今でも葛藤がある。
でも私は、はっきりと伝えたいと思った。
私はお金のために結婚したわけでも、、セレブに憧れて結婚したわけでもない。本当の意味での心のつながりを求めて結婚をしただけだった。
でも、幸せの基準、価値観には埋めることのできない溝があった。
その感覚の違いにうすうす気がつきながらも、疑問を抱きながらも、そうじゃない部分での幸せももちろんたくさんあった。
いろんな場所へ連れていってもらった。おいしい食事にも連れていってもらった。贈り物もしてもらった。結婚生活は幸せだったと思う。でもどこか埋まりきらない心を抱えながら、私は生きていた。夫婦って何だろう。一緒になるって何だろう。物質的なものに惑わされていて、核の部分でのつながりや喜びがない・・・・。
その頃から私の酒量は増えはじめたのかもしれない。
ちょうどその時期、1年ちょっとの休業期間を終え、仕事に復帰していた。私は自分の中から湧き出るエネルギーに満ちあふれていた。久々の仕事やその環境が楽しくて幸せだった。やっぱり私はお芝居が大好きで、私の居場所はここなんだと再確認した。何よりも、どこよりも、生きている実感があった。と同時に、このことがきっかけとなって、今まで溜まりに溜まった彼との価値観の相違に対する疑念を抑え込んでいたたががはずれてしまった。
心のつながりが一方通行の状態で、それでも歩み寄ろうとする気力も、日に日に失せていった。なぜこの人と一緒にいるのか、その理由が見いだせなくなっていった。
最後まで自分なりに努力はしてみたものの、自分の気持ちがスーッと引いていくのがわかった。
心が離れていくのを感じた。
2005年7月、私たちは1年半という結婚生活に終止符を打った。
彼は私たちの離婚について自身のブログで次のように綴っている。
【離婚は唐突に聞こえるかもしれませんが、つい先日、解決し難い問題が生じました。ふたりで話し合った結果、しこりを残すよりも別々の人生を歩むことに決めました】
どちらがいい、悪いということを、私は言いたいわけではない。
お互いの問題だったと思う。
彼には彼の価値観や気持ちがあるように、私には私の理由がある。それは最後の最後まで決して交わり合うことはなかった。ひずみが生まれた時点で、もっと早急に解決するべきだったと思う。疑念が生まれた時点で、その溝をさらに深めてしまわないよう、お互いの心の在りかを確認するべきだったと思う。
私自身、人として、妻として、至らない部分も多かったと思うし、まだまだ未熟だった。存在価値を見いだせないという理由で、途中で歩み寄ること、信じることを諦めてしまい、忍耐も足りなかった。価値観の相違を笑って流せるだけの器も余裕もなければ、心の強さを持って支えられるだけの愛も足りなかった。
もちろん楽しい幸せなこともたくさんあった。
いや、楽しい幸せなことの方が多かったと思う。
ただ、お互いの求める幸せの形に温度差があっただけなのかもしれない。少なくとも私はその瞬間、瞬間、一緒にいられることの喜びを感じていたし、短い間だったけれど、そばにいさせてもらえて本当に幸せだった。
私たちは夫婦としては、生涯一緒にいることはできなかったけれど、今でも、人として尊敬しているし、素晴らしい人だと思っている。彼に出逢えたこと、与えてもらった幸せすべてに感謝している。
対人恐怖症とお酒 (P.115 〜 P.118)
「もう疲れた・・・・」
離婚したときの、私の正直な気持ちである。
食事も喉を通らない、外にも出られない、人に会うのも怖くてできない・・・・。
あの頃の私は、ある種、対人恐怖症のようだった。今まで精神的にはタフだと思っていただけにこの経験で、私も生身の普通の人間なんだと認識させられた。
暗闇の中に一条の光を見るような気持ちで、私は、押しつぶされそうになりながら、息もできないような時間を過ごしていた。
あのときの私の慰めのひとつはお酒だった。
離婚前、自分の存在理由について悩みだした頃から、酒量が増えたように思う。
お酒を口にし、そして感覚を麻痺させようとしていたのだ。
しかし、お酒を飲んで浮遊感の中を漂い、いっとき嫌な思いから開放されたとしても、しらふに戻れば、また再び陰鬱な感情が私を襲う。その繰り返しで何の前進もないことは、自分でもよくわかっていた。
それでも、あのときは、一時的で短い期間ではあったが、そうするしかなかったのだと思う。
(以下省略)
三角関係 (P.118 〜 P.121)
「ほら、一夫多妻の国だってあるわけだし、そもそも男には子孫を残すっていう血が本能的にあるからねぇ。もう、そういう生き物だと思って割りきるしかないよね」
人生の先輩にこんな助言をいただいたことがある。
「それでもなんとかしたいんです」
私は必死の思いで言った。
「それは悲しいけど難しいよねぇ・・・・」
「嫌なんです」
「嫌って言われてもねぇー、それが男だよ」
「・・・・」
離婚してからも、私は私の知らないところで自分でも把握しきれないくらいの人たちとの熱愛記事を書かれていた。
僧侶? サーファー? ダンサー? 演出家? IT社長?
記事をいちいち読んでいないのでよくわからないけど、でもまったく事実ではない。
私が一緒にいたのは、年下の彼だった。そして2007年の秋、私たちは別れた。
彼に、私以外の別の存在があることを最初に知ったのは、付き合いはじめて半年が過ぎた頃だった。
電話をかけても大抵出ない。携帯メールを送っても、なかなか返事がこない。何度かこんなことが続いた。
私は不審に思っていた。そんなことが続いていたある日のこと。家にいるはずの時間なのに電話に出ない。寝ている時間でもない。 「やっぱり、なんかおかしい・・・・」
私は時間をおきながらも電話をかけ続けた。返事もないし、やっぱり出ない。
あまりの不信感から家を訪ねることにし、家の前から何度も電話をした。
プルルルルル――、プルルルルル――。
応答がない。
プルルルルル――
”留守番電話に接続します”
しつこく電話をかけ続けていたら、携帯を持った本人が家の中から外に出てきた。
私が声をかけると彼は固まった。
「何で電話に――」
言いかけて私は目を疑った。彼は頭に女性用のカチューシャをしていたのだ。
「シーッ!静かにして!」
そう言って、急いで私の腕を取り、家から離れた。
と、そのとき・・・・。向こうから、血相を変えてこちらに向かって歩いてくる女性の姿が私の目に止まった。
「え・・・・誰? おねえちゃん?」
「・・・・お、幼なじみの子だよ」
動揺した様子で話すその人越しに女性は立っていた。
その彼女の目に溜まった涙を見て、私はすべてを悟ったのだった。
一夫多妻制度のある国の妻たちは、どんな気持ちで生活をしているのだろう。
その国にとって当たり前の制度で、そこで暮らす人々は普通に生活しているのかもしれないけれど、
女たちの嫉妬によって争いが生まれたりしないのだろうか。
もし私が一夫多妻制の国やその時代に生きていたら・・・・。
考えるだけで気が変になってしまいそうだ。間違いなく誰かを刺しているような気がする。
そもそも、同時に複数を愛することなんてできるはずがない。いや、実際にはそういう人もいるのかもしれないけど、
私には絶対に無理だ。
「あなたのここが好き。でもあの子のことも好き。あなたにはあの子のこの部分がない。でもあの子にはあなたのその部分がない。だから両方好き。どちらか選べない」
そんなの自分の理想に都合よく当てはめているだけなんじゃないのか!
そんなの愛じゃない!
でも、そのときの私は何を血迷ったのか、許してしまったのだった―――。
自信喪失 (P.121 〜 P.126)
彼は何度も何度も同じことを繰り返した。
もし仮に決まった相手とだったら、彼にとってどうしても必要な存在なのだろうと、私も潔く別れを選択できたのかもしれない。でもそうじゃなかった。次々と新しい存在が現れる。裏切っては誓いを立て、また裏切っては十字架を背負い、またまた裏切っては命をかけ・・・・。そのたびに私の心は引き裂かれそうになった。
「愛が深すぎて怖い」
「はい?意味が分からない。深すぎて怖い?いい加減にしてっ!」
理解ができなかった。怒りが込上げてきた。私の愛が深いというのは、相手の勝手な言い訳にしかすぎないと思った。事実、私の心には愛情というよりも傷つくのを恐れる気持ちと、相手に対する疑いの気持ちしかなかった。
ある日、私のパソコンの電源がつけっぱなしになっていた。自分で消し忘れたのかと思ってパソコンを触ると、ある女性のブログのページが開かれていた。昔会ったことがあり、私も知っている人だった。
「ん・・・・?なんだこれ?」
彼が私の後にパソコンを使ったまま、電源を消し忘れていたのだが、そのブログにアップされていた写真をよく見ると・・・・。そこには、彼の愛用しているものを身につけた、ブログの主である彼女本人が載っていたのだ。
「え―――――!なにこれ!?」
心臓が飛び出そうになった。自分の目を疑った。
彼を呼び出して聞いてみると、「ただの友達だ」と言う。
「私にはそうとは思えないんだけど」
「なんで?」
「だってあなたのもの身につけてるじゃない」
「・・・・・」
「それでも違うって言うなら、今その人に電話をしてみてよ」
そして、彼は、私の目の前でその彼女に電話をしたのだった。
プルルル――、ガチャッ。呼び出し音が鳴って受話器を取る音がするやいなや、
”なんで全然連絡くれないのぉ〜?”
女性の声が受話器から漏れ聞こえてきた。
「お、俺たちただの友達だよね?別に付き合ってなんかないよね?」
彼の声は、明らかに震え、上擦っていた。
”はい?何言ってるの?どういうこと?後悔したくないし、後悔はさせないって言ってたじゃない!ひどい!”
女性の声を私ははっきりと聞いた。そして叫んだ。
「付き合ってるじゃない!」
相手の弱さや甘えを自分なりに理解していたとはいえ、その言動は度を越えていた。
私は完全に自信喪失した。相手の心の問題だけではなくて、自分の愛し方にも問題があるではないだろうか・・・・。
自問自答の日々だった。
心の在り方の問題もあると思うけれど、きっと人は誰といても悩みが尽きない。どんなに愛する人とでも完全に理解しあうことは不可能だと思う。でも、それは悲しいことじゃないと思うし、人はみんな違って当たり前で、その一致しない部分を諦めるのではなく、理解して歩み寄った上で相手との関係を大事に育てたかった。
だからこそ私は、さっさと関係を諦めて離れる、という選択を簡単にはしたくなかったのかもしれない。
もし仮に1%でも乗り越えられる光があるなら、という思いで、何がそうさせているのか根本的な原因を一緒に考えてきたつもりだった。相手の心に問題があるにしろ、私の愛し方に問題があるにしろ、どちらにしても、二人の問題として抱え、向き合っていかなければ解決しないと思ったのだ。
その時期、心理学の本もたくさん読んだ。でも、そこまでする私の姿が、相手にとっては重く、煩わしいものだったのかもしれない。
何をしていても疑いの気持ちが生まれる。疑心暗鬼の塊。電話に出ない、メールの返事がこない。もしかしたら誰かといるのかもしれない。心臓がバクバクする。震えが止まらない。眠るのが怖い。自分に自信がない。傷つくのが怖い。信じるのが怖い。裏切られるのが怖い。
あれもこれも実は嘘ではないのか・・・・。その人のすべての言葉や行動に説得力がなかった。事実、私の不安や勘はかなりの確率で的中していた。
相手を信頼する心なんてとっくに失っていたのに、それを認識することが何よりも怖かった。相手の人間性を自覚するのが嫌だった。私は保証のない光を見ながらも、生活の中心が苦しみになっていることに気が付く。
最終的には涙も言葉も出てこなかった。悲しみが麻痺して痛みも感じなかった。ただ体だけが反応して震えが止まらなかった。
「またか・・・・」
その現実と自分自身に心底辟易した。自分は何をしてるんだろう。自分の中に微かに残っていた”可能性”という光に、静かな諦念の波が押し寄せたとき、私はやっと別れという選択に覚悟ができたのだった。
別れを決断してからは、今までの思いが嘘のように引いていった。
私は一度覚悟が決まったらもう振り返らない。
「精いっぱい、想った。歩み寄った。やれることはやりきった」
そういう気持ちがあったからなのかもしれない。
|
|
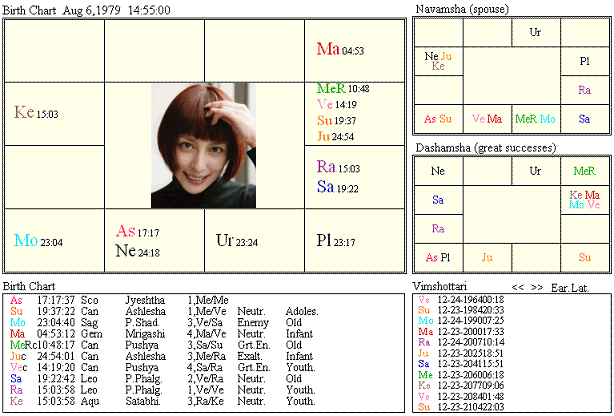
 彼女は最近では、魔性の女と呼ばれるようになり、2008年4月8日に自叙伝フォト&エッセー「紅い棘」(双葉社)を発売して妖艶な姿を写真で晒している。
彼女は最近では、魔性の女と呼ばれるようになり、2008年4月8日に自叙伝フォト&エッセー「紅い棘」(双葉社)を発売して妖艶な姿を写真で晒している。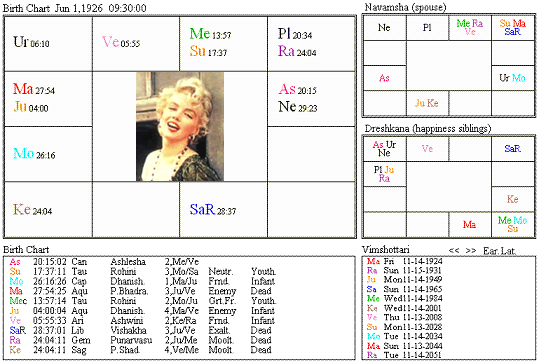
 一方、奥菜恵の場合は、押尾学、藤田晋、山内圭哉など、異性関係を結んでも、幸福な関係が続かないようである。
一方、奥菜恵の場合は、押尾学、藤田晋、山内圭哉など、異性関係を結んでも、幸福な関係が続かないようである。