
志村けんが亡くなってから、志村けんの芸能界での歩みや業績などについて物語る記事がよく目立つのであるが、おそらく志村けんの11室(評価)に木星と土星がダブルトランジットしている効果である。
この記事自体、志村けんについて語っているのであり、志村けんへの評価(11室)を表わすものである。
それで、以下の文春オンラインの記事が私の言いたかったことをよくまとめてくれていた。
|
たけしと何が違うのか――コントで勝負した志村けんは、最後の世代の「喜劇人」だった 2020年3月31日 6時0分 文春オンライン 3月29日、コメディアン・テレビタレントの志村けんが、新型コロナウイルスによる肺炎のため死去した。70歳だった。 25日にコロナウイルス罹患・入院の報道があってからのあまりにも早い逝去に動揺する声が、メディアやインターネット上に広がっている。この動揺は、現時点でまだ未知の部分が非常に大きいコロナウイルスの危険性だけでなく、志村けんというキャラクターの突然の消失を、人々がうまく受け止められていないことに起因している部分が大きいのではないだろうか。 志村は高校卒業間際の1968年より、ザ・ドリフターズの付き人=ボーヤとして、芸能界の世界に足を踏み入れる。その後紆余曲折を経て74年にドリフに新メンバーとして加入。76年に『8時だョ!全員集合』内で歌った「東村山音頭」がウケて以降は、ドリフの既存メンバーをしのぐ人気を獲得していく。 『全員集合』終了後も『加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ』『志村けんのだいじょうぶだぁ』『志村けんのバカ殿様』など冠番組を次々とヒットさせ、70年代後半から80年代にかけての志村は間違いなく、日本で最も人気・知名度の高いコメディアンの一人だった。 同世代のたけしと異なる「キャラクター性に対する姿勢」 志村がスターになってから数年後、漫才ブームのなかで大きな人気を集め、80年代以降にビッグになったコメディアンとして、ビートたけしがいる。後年志村とたけしはテレビ番組で共演しているが、彼ら二人の個性の差異として、キャラクター性に対する姿勢の違いを挙げることができるだろう。 人々が志村を連想したときに必ず思い浮かべるのは、「バカ殿様」「変なおじさん」「ひとみ婆さん」など、コント・キャラたちだと思うのだが、ビートたけしは80年代には「鬼瓦権造」「タケちゃんマン」等いくつかのキャラを生み出したものの、90年代以降「鬼瓦権造」以外のキャラを継続的に身にまとうことは殆ど無くなり、散発的にコミカルな仮装をするだけになっていく。 また、たけしは「昭和四十六年 大久保清の犯罪」(83年、TBS)でそれまでの道化的イメージを裏切るシリアスな犯罪者役を演じ、多数のエッセイ著作で自らの世界観を開陳し、90年代以降には映画監督業を成功させ、当初は漫才師として認知された自身のイメージをどんどん多重化させていった。 対して志村は、コメディ以外の仕事の数が基本的に非常に少ない。人々が思い浮かべる「志村けん」のイメージには重層性が無く、バカ殿や変なおじさんの顔がフワフワとそこに漂っている。 90年代以降、たけしの戦い方が主流になった 端的に言ってしまうと、たけしが展開したイメージの多層化、つまりテレビ的な平板な記号としてではなく、生身の人間としてのリアリティ・奥行を感じさせる重層的なキャラクターの構築こそが、90年代以降の日本のテレビ・コメディアンたちの手本となっていった。 いま現在メディア上で活躍する芸人の殆どが、漫才やコントなど「ネタ」以外での自分の内面や趣味、嗜好を商品として売り込んでいる。80年代以降、テレビがお茶の間から更に深く、家族それぞれの個室にまで入り込んでいったプロセスのなかで、たけしが体現した戦い方こそが最適解だったのだと思う。 志村はもちろん90年代以降もテレビで活躍したが、基本的に彼は「たけし以前」のテレビ・コメディアンだったのではないか。 志村が50~60年代のジェリー・ルイスや20~30年代のサイレント・コメディやマルクス兄弟のファンであったことはよく知られており、彼はしばしば自らのテレビ・コントにそれらのコメディ映画でのギャグをアレンジして落とし込んでいた。志村がやりたかったこと・やれたことの本質は恐らくそういう古典喜劇映画のテレビ的な翻案作業にあり、それは例えばスパイク・ジョーンズの日本的解釈であったクレージー・キャッツらが編んでいたコメディ系譜の最後尾に位置するようなものだったと言えるのではないだろうか。 彼は80年代以降のたけしのような「メディア・スター」ではなく、70年代までの「喜劇人」の最後の世代の人だった。メディア上で自らの人間性の奥行を商品にすることを、志村はしなかった/できなかった。 お茶の間でドタバタ劇を見せてくれた、キャラクターの消失 インターネット以降の世界では、芸人もミュージシャンも作家もみな生身の人間であることをわたしたちは実感として知っている。だが、70~80年代にテレビで活躍しその存在を確固たるものにした志村けんというキャラクターは、その生身の奥行を想像しにくい存在としてのコメディアンの、最後の一人だったのではないだろうか。 だから私たちは、そういう平板な(これは揶揄ではない)キャラクターが消失してしまったことを上手くイメージできない。ミッキーマウスが生々しく死ぬ場面を想像できないのと同じことだ。 70年代までの日本には、お茶の間のブラウン管を通し平板なキャラクターたちのドタバタ劇に笑っていられる状況が、良くも悪くもあった。その残滓の消失を、恐らく私たちはいま実感しているのである。 志村けんさんのご冥福をお祈りいたします。 (コメカ) |
志村けんは、最近の芸人に見られるような私生活を売り物にしたり、女優やタレントとのスキャンダルさえも売り物にして、芸能界に深く根をおろし、事務所の力や芸能界での人脈を駆使して、マルチタレント化して、業界に張り付いて生きていくような所がなかった。
志村けんは、自分の芸、コント一本で、勝負して来たエンターテイナーであり、喜劇役者なのである。
元々ドリフターズという出身母体自体が、喜劇集団であり、ライブで喜劇を見せるグループだった。
ドリフターズが活躍していた時代、特に私生活を売り物にするという発想はなかった。
例えば、最近のお笑い芸人の出世コースと言えば、最初は漫才か、コントで、多少、クリエイティブな才能を示した後は、バラエティー番組や司会業などに進出し、テレビに露出回数が多くなって、知名度が増し、その後は、キャラクター自体が、商品になっていき、あらゆる番組に出まくって、私生活を語り、それで、業界に深く根を下ろしていく。
その段階では、もはや芸は必要ないのである。
もし必要な才能があるとしたら、面白いキャラクターと話のスキルであるが、それは芸とは言えないのである。
同じ芸人仲間にしか分からない私生活上の話、内輪の話で盛り上がって、それをメディア(テレビ)が商品化してくれるのである。
テレビがつまらなくなったというのは、そのような芸人同士の内輪の話をして盛り上がる芸人たちが事務所の力で、テレビに出まくっているからなのである。
テレビ業界は、規制に守られていて、1、3、4、6、8、10、12と非常に少ないチャンネルしかない。
選択肢がないので、視聴者としては、そういう芸人たちの内輪話を聞かされているしかないのだ。
これは特に吉本興業の芸人たちが、こういう風潮を作り出していると思われる。
関西弁を話して、面白いキャラクターであれば、テレビに引っ張り出されて、番組のコンテンツとして活用されるのである。
この志村けんは、2室の支配星がケートゥとコンジャンクトしていて、トークが苦手で、口下手ということもあって、司会業やトーク番組に進出することが出来ず、逆にそれがよかったのか、喜劇を作り続けた。

この喜劇において、バカ殿、変なおじさんなどのオリジナルなキャラクターを作り続けた。
この創造的才能が、志村けんの特徴である。
メディアに消費されて自分の素のキャラクター自体が商品化される芸人との大きな違いである。
占星術的に考えると、これは3室と5室の違いを表わしている。
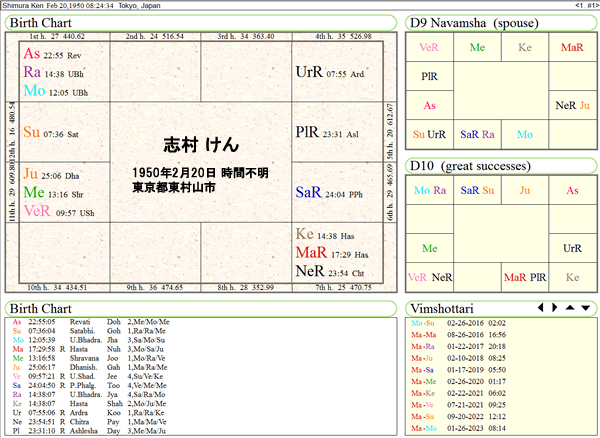
志村けんのチャートを見ると、5室支配の月がラグナに在住して、9室支配の火星と相互アスペクトしており、更に11室から木星、金星、水星の3つの吉星が5室にアスペクトしている。
従って、5室が非常に強いのである。
5室は演劇や舞台芸術を表わすハウスであり、3室よりも格調高く、創造性に溢れるハウスである。
3室から見た3室目のハウスであるため、3室の本質としての特徴も備えており、従って、ダンスやパフォーマンス、芸能といった3室の象意も持っているが、そこにはオリジナルな創造性が溢れ出て来るのである。

だから志村けんは、あくまでも喜劇役者にこだわり続けたということではないかと思われる。
ドリフターズを離れて、自分の看板番組を持っても、そのスタイルは変わらず、そうした創造的活動をある程度、こなして来たので、最近では、バラエティー番組やトーク番組などに呼ばれて出演することもあったかもしれないが、あくまでも志村けんは、喜劇役者であり続けた。

一方で、3室というのは、テレビ、ラジオ、週刊誌などのメディアを表わすハウスであり、これらのハウスが強調される場合、メディアへの露出が多くなる。
そこで事務所や業界の需要があって、キャラクターの面白い芸人というのが消費されるのである。
特にクリエイティブな芸がなくてもキャラクター自体が商品であるため、テレビに出演してコメントなどをするだけでいいのである。
バラエティー番組やトーク番組で、面白い私生活の一つでも暴露するなどして、業界に幅広い人脈を築き、そのうち、映画やドラマにちょい役で出させてもらったりして、一流のエンターテイメントにも参加させてもらう。
こういう芸人の出世コースというのを大手芸能各社が作り上げたのである。
ビートたけし(北野たけし)は、私生活も売り物にし始めた芸人として、志村けんと対比されるが、それでも本当は映画だけを作っていたいが、バラエティー番組や司会業、トーク番組などは、仕事が来るので、仕方なくやっているというようなことを述べている。
テレビ局や広告会社、番組制作会社が持ってくる企画をお金が稼げるから、本当はやりたくもないが、ただこなしているのである。
そこでは、”ビートたけし”というキャラクター商品を売っているのであり、3室のメディアへの露出、メディアを通じて、大衆に消費されるだけの存在にすぎない。
テレビ局や広告会社、番組制作会社などの商業広告、商業メディア(3室)の需要に応えているのである。
然し、本当にビートたけしが、創造的な活動をしていると言えるのは、漫才をやったり、映画を作ったり、”お笑いウルトラクイズ”などの自分の企画番組を作っている時である。
そこで、創造性を発揮できるので、ビートたけしもクリエイティブな喜劇役者の面が十分にあると言えるが、然し、業界の要請に応えて、単にキャラクターを商品として売るような機会も多いのである。
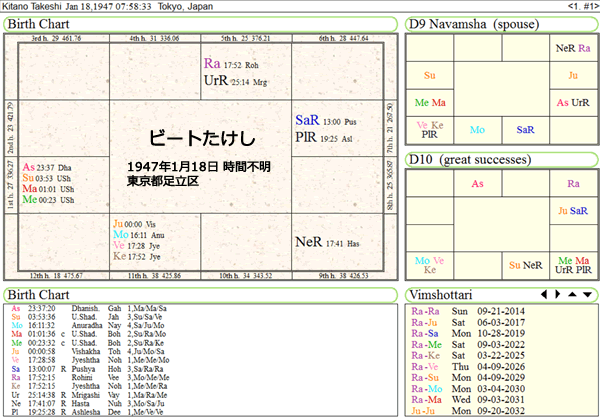
ビートたけしのチャートを見ると、山羊座ラグナで、5室に木星、月、金星がアスペクトしており、5、10室支配のヨーガカラカの金星が5室にアスペクトし、月と木星はガージャケーサリヨーガを11室で形成している。
従って、コントやドラマ、映画などで、俳優も監督もやって創造性(5室)を発揮している。
然し、志村けんやビートたけしが活躍した時代は、日本経済が高度経済成長期を迎え、日本が経済大国となった時代であり、テレビ局や電通などの広告会社、番組制作会社などが、力を持ち、規制にも守られていたので、日本の経済的な恩恵が最も垂れ流される業界であった。
こうした業界が、テレビ番組に登場するコンテンツを求めるので、それで、単にテレビに出演して、キャラクターを売るような仕事が増えて来たのである。
こうした仕事は創造しなくても番組の企画にあわせて、司会をしたり、トークをしていればいいのである。
こうした業界の要請によって生み出される仕事が3室(テレビ、ラジオ、週刊誌などのメディア)の仕事ではないかと思われる。
然し、5室(演劇、舞台芸術)が強調される場合、創造する作品は、劇場やライブハウスなどでもよいのであり、特にメディアによって大衆に消費される必要はない。
芸術性という点で言えば、5室の方が格調高く、3室は消費される質の低いものである。
志村けんの場合、トークが苦手であり、キャラクターだけを売り物とするテレビ出演が出来なかった為に喜劇、コントを作り続けるしかなかった。
その辺りが古典的な喜劇役者と評価される理由である。
志村けんは、私生活を売り物にせずに喜劇役者として、創りあげたもの(5室)だけで勝負をした最後の役者であるという評価はその通りである。
芸能界でも本当に5室の創造的な仕事をしている人は少なく、大抵は、業界の要請で、マルチタレント化し、キャラクターとして、番組のコンテンツに成り下がってしまう芸人が多いのである。
そうした意味で、前回の記事で、私は志村けんの本質は、喜劇役者だと考えたが、それは志村けんが、私生活を売らない、創造的なクリエイター(5室)であり続けたからである。
 ※例えば、「志村座」といったコンセプトは、歌舞伎役者と同じように志村けんが演劇集団の座長であることを表わしている。
※例えば、「志村座」といったコンセプトは、歌舞伎役者と同じように志村けんが演劇集団の座長であることを表わしている。










コメント